
文・秋野未知
キャリア・チェンジを目指し、アメリカに語学留学して日本へ帰国するはずが、あれよあれよと言う間に在米歴11年になってしまったフリーライター・秋野未知、37歳独身。仕事をこよなく愛しながらも、「やっぱり結婚もしたい」を合言葉に、出会いを求めて日々精進する彼女の痛快エッセイ!
- 1 第1話 「パーソナル・クラシファイド掲載事件」
- 2 第2話 「いい男がゲイである確率」
- 3 第3話 「“米食い”白人オトコに要注意」
- 4 第4話 「アメリカにいる困った日本人」
- 5 第5話 「コミットメント症候群」
- 6 第6話 「一軒家願望の行方」
- 7 第7話 「愛すべきゲイの男友達」
- 8 第8話 「友達を友達に紹介しない男」
- 9 第9話 「完璧な彼を持つ恐怖」
- 10 第10話 「養ってもらえる女と、そうでない女」
- 11 第11話 「またしても誕生日の再来」
- 12 第12話 「アメリカの自動車保険おそるべし」
- 13 第13話 「シアトルの冬を乗り切る弱気打開策」
- 14 第14話 「好みの違いと常識の壁」
- 15 第15話 「ゴッドマザーの依頼」
- 16 第16話 「アメリカの歯科請求おそるべし」
- 17 第17話 「ナンパにはやっぱり落とし穴」
- 18 第18話 「サイキックを信じる女達」
- 19 第19話 「大人の女のお断わり方」
- 20 第20話 「独身女のお伽噺」
- 21 第21話 「妙に押しが強い男」
- 22 第22話 「スタンダードな美意識」
- 23 第23話 「ボディー・ランゲージの秘密」
- 24 第24話 「アメリカで上手に生き抜く女達」
- 25 第25話 「割り勘の基準」
- 26 第26話 「意志の強い女」
- 27 第27話 「運転しなくてもいい女達」
- 28 第28話 「ヘザーが泣いたプロポーズ」
- 29 特別企画:独身女座談会「男と女がくっつくには何が必要?」
- 30 第29話 「愛をとるか、金をとるか?」
- 31 第30話 「私の夏」
- 32 第31話 「褒めなきゃならないアメリカ人」
- 33 第32話 「アメリカと肥満」
- 34 第33話 「エル・ワード」
- 35 第34話 「オフィシャルな相手」
- 36 第35話 「オンラインに躊躇する理由」
- 37 第36話 「無防備な出会い」
- 38 第37話 「習慣というもの」
- 39 第38話 「友達の気遣いと私の気遣い」
- 40 第39話 「35歳から死ぬまでに必要な金額」
- 41 第40話 「仕事で“女”を出す女達」
- 42 第41話 「独身女が不動産を入手する条件」
- 43 第42話 「パブリックで話す私生活」
第1話 「パーソナル・クラシファイド掲載事件」
日本人の女友達に、グラフィック・デザイナーのA子がいる。30歳だが見た目は25歳、性格も明るくて楽しいヤツなのだが、やたらせっかちな性分の持ち主で、何事も「ちょっと様子を見て考えてから行動する」ということが苦手である。たとえば、彼女がイリノイ州の大学を卒業するときも、25社に送った履歴書とサンプルの返事を少しも待つことなく、「シアトルって、なんだか行ってみたかったのよね」という理由だけで、最初に連絡をくれた、冴えないデザイン事務所に即就職を決めてしまった。だいたい仕事を決めるときでさえこうなのだから、それがアパートだったり、車だったり、ボーイフレンドだったりしても、同じように非常に単純に決めてしまうのだ。物の場合はすべて「だって、安かったんだもの」であり、ボーイフレンドの場合は、「なんか、良さそうだったから」となる。彼女と知り合って3年が経つが、ボーイフレンドをすぐに見つけるわりには、同じ人と3カ月以上続いたのを見たことがない。当然のように私たち女友達は、「もう若くないんだから、もっとゆっくり考えてから決めなさい」と常日頃から注意を促しているが、当の本人は一向に気にしていないようなのだ。
先日も日本人の独身女友達5人で集まってベルタウンで飲んでいたら、またA子が、「実は、最近おもしろいことになっているのよ」と嬉しそうに話題を振ってきた。聞けば、無料タウン情報誌『Seattle Weekly』と、『Stranger』両誌の「Personal Classified Ad」コーナーに、ボーイフレンド募集広告を出したと言うのだ。「ひえー!」と驚愕する私たちを気にする様子もなく、「やだ、Hなコーナーの方じゃないわよ。普通の人たち用の方。それに、アドを載せるのは無料だったしね」と言う。もちろん否応なしに場は盛り上がった。アドを掲載する方は無料でも、それに応える方は有料という仕組みなので、かなり気合の入った人か、藁にもすがりたい思いの人か、少し頭のおかしな人しかリスポンスして来ないと思うというのが、そこにいた全員の意見だった。しかも、だいたいあのコーナーを一生懸命読んでること自体がすでに問題だ。だが、当のA子は、「と言うことは、みんなも読んでるんじゃないの」と一発釘をさしてから、自分も最初はそう思ったが、結構「Sounds Nice」(いい感じ)な人たちからリスポンスが来たというのだ。しかも、その数、なんと14人! たった1週間しか掲載されない小さな広告に、それだけ多くの人が応えて来たということは、シアトルには予想以上にたくさんの独身男性がいるということである。
このA子の勇気ある行動に驚いたことは言うまでもないが、私たちがさらに驚いたのは、A子がすでにその内の4人と実際に会ったという爆弾発言だった。彼女によると、最初に会ったのはIT関係の仕事をしているトムという白人男性で、マディソン・パークのレストランで夕食をごちそうになったそうだ。翌日に会ったレイという白人男性は銀行勤務で、彼にもダウンタウンで夕食をごちそうになったらしい。3人目は出版関係の仕事をしているダンという白人男性で、海辺の公園を散歩してコーヒー飲んだだけだったそうである。もちろん会った全員に自分の電話番号を渡したそうだ。
「おもしろかったのは、会計士のロブって人。最初に相手の電話番号に掛けて話したときは何かピンと来なかったんだけど、偶然、その翌日のマリナーズのプレーオフ・チケットを持っているから行かないかと言われたから、そんなチャンスを逃しちゃ損だと思って、会社を病欠してゲームに行っちゃった。あー、楽しかった。こんなにいろんな人と会って、みんなにおごってもらえて」と、屈託のかけらもなく喜ぶA子。でも私たちは、開いた口が塞がらない。一呼吸おいてから、法律事務所に勤務する、しっかり者のB子が、「そんな風に知らない人と会って怖くないの? もし、その人たちがサイコ(頭のおかしい人)だったり、ストーカーだったりしたらどうするのよ」と少し叱るような口調で聞くと、「はじめは少し怖かったけど、もう慣れちゃった。それに、そんなこと言ってたら、出会いなんて全然ないじゃない? ほかに出会いの方法があるなら言ってみてよ。ね、ないでしょ? だから、みんなも広告掲載してみたらいいのよ。結構おもしろいわよ」とA子。そう言い切られて、それ以上は誰もあえて反論もせず、結局その夜は、A子が会ったそれぞれの相手のディテールで盛り上がった。
でも、このA子の広告掲載事件には3つの後日談がある。ひとつは、全員と電話番号を交換したのに、結局A子は誰ともステディーな関係にはなれなかったということだ。彼女がちょっと素敵だと思って数週間付き合った会計士のロブとも、「実は、子持ちだったのよね。しかも2人の……」という現実的な理由でNGとなってしまった。自由奔放に生きる彼女には、たとえ離婚はしていても、子持ちの人はだめらしい。
ふたつ目は、いくらA子がおもしろかったと言っても、「やっぱり、もし相手がサイコだったら怖い」、「自分のPRを応募先のテープに録音しなきゃいけないのが嫌だ」などの現実的な理由で、残りの4人はいくら無料でも誰も広告を掲載しなかったこと。だから、現在もみんな独身である。
3つ目は、私が親しい友達夫婦の家に食事に呼ばれた席で起きた。このA子の話を私がおもしろおかしく話しているときに、一体どういう内容の広告を出したのかを聞かれた。クリエイティブな仕事をしているA子の広告の文句は、とても印象的なものだったので、内容を覚えていた私は事細かに説明した。すると、友人のご主人が興奮した口調で、「えーっ! それなら僕も読んだよ。僕、好きなんだよね、あのコーナー。毎週、全部読んでるんだ、女の子の広告のところは」と言ってしまったのである。 「信じられない! あなた、あんな下らないコーナーを読んでるの!?」
結婚9年目のこの夫婦が、そのまま喧嘩を始めたことは言うまでもない。結局、読んでるのよね、みんな。
第2話 「いい男がゲイである確率」
アメリカに何年住んでも未だに慣れないことのひとつが、魅力的な男性と出会ったときに、まず「彼がゲイであるか、否か」という可能性について考えなければならないことである。これは私がホモフォビック(ホモセクシュアルを嫌う人)だというわけではなく(むしろ、私の親愛なる友人たちにはゲイが多い)、自分がどうすることもできない事実により深く傷付くことを避けるための護身術なのだが、これがなかなか難しい。
私は仕事柄、いろんな人と会って話しをする機会が多いので、洞察力は結構優れた方だとは思うのだが、それでもこの件に関する失敗談は後を絶たない。しかも田舎(アメリカ内陸部)に住んでいた頃より、シアトルという小都会に住んでからの方が、「ああ、またしても……」と、がっくり肩を落とした回数は著しく増えている。理由はかなりシンプルである。それは、私の理想とする男性が“非常にアーティスティックで、インタレクチュアルで、センシティブで、洞察力の優れた人”であり、そういう人は都会に住んでいる確率が高く、なおかつアメリカでは、そういう人の多くがゲイである場合がなぜだかとっても多いからなのだ。
ただし、ここでいうゲイの男性とは、俗にいうドラッグ・クイーンのように「おネエ言葉で話したり、女性的な立ち振る舞いをする男性たち」ではないので、そこを間違えてはいけない。それなら誰だって分かる。見た目や立ち振る舞いはもちろん、会話の内容もバック・グラウンドも職業も、それこそ一般的以上に魅力的な男性で、一緒に仕事をしても、食事や遊びに行っても、とびきり楽しいひとときが過ごせる男性たち、つまり世間一般に言う「とびきり上等な男たち」のことだ。
そして、そんな楽しいひとときを重ねるうちに、いつも妙に自然に(でも唐突に)打ち明けられる一言が、「もうキミは気付いているだろうけれど、僕はゲイだから……」なのだ。そしてその発言の後は必ずと言っていいほど、現在彼が置かれている状況について、私がいろいろ相談にのるという展開となる。最初の頃は、その発言によってものすごくコワばってしまった顔をさすりながら、「ははは。もちろん、初めて会ったときから分かってたわよ」などと言い、必死で体勢を整えたものだ。
まるで自分の勘の悪さを自慢するようで情けないが、実は今までに少なくても軽く10回は、このような体験をしたことがある。これらの体験をもとに私が勝手に「いい男がゲイである確率」を割り出すとすれば、約68%~73%というところであろう。ちなみに、相手がバイ(バイ・セクシャル)である場合はさらに分かりにくいが、これはアメリカではよくあるケースなので、何年もアメリカに住んでいれば慣れるし、その傾向もつかめるようになる。
これらの体験から、最近は初対面でもかなり高い確率で、世間一般で言うところの「いい男」が、ゲイ(もしくはバイ)であるか否かを見抜く力がついた(ように思う)。だからと言って、その能力が私の状況を変えたかといえば、ちっとも変わっておらず、今日も私はシングルなのである。
第3話 「“米食い”白人オトコに要注意」
日本人の女友達に、グラフィック・デザイナーのA子がいる。先日、日本人の女友達4人で飲んでいたら、シアトル市内のある有名広告代理店で働くK子が、彼と別れたことを切り出した。さっそく理由を尋ねると、半年ほど付き合っていたジェイ(白人)が、なんと“米食い”君だったことが判明したという。その発言に、一同が「ひえーっ!」と驚いたのは言うまでもない。ジェイは、通常の“米食い”君とは一線を画したタイプで、どちらかというと“米嫌い”に見えるタイプの男性だからだ。
ここで説明しておくが、“米食い”君とは、シアトルで働くシングルの日本人女性たちの間で使われているスラングで(でも、まだ25人くらいしか使っていないと思うけど)、米を主食とする国から来た女性とだけ好んで付き合う白人男性を指す(なかには付き合う前に相手を食べてしまう場合、食べただけで消えてしまう場合もある)。つまり、パンやパスタを主食とするアメリカやヨーロッパ女性の独立心が苦手でうまくお付き合いできず(または相手にされず)、アジア女性ならば常に男性より一歩下がって笑顔で男性の意見に従うという“アジアン・ファンタジー”を胸に抱き、私たち日本人女性にもそれを求めて近づいて来る男たちのことである。通常の“米食い”君は、ルーザー系(Losers)、アニメ・ギーク系(Geeks who love Japanimation)、まったくイケテナイ系(Guys who are not cool at all)、友達少ない系(Guys who don’t have many friends)などから構成されるため、それなりにオシャレで友達も多いように見えたジェイが“米食い”君だとは……と、場は騒然となった。
K子によると、「ちょっとやばいかな」と思いはじめたのは、ジェイが自分のバディたち(親友軍団)の話をしたときだったそうだ。職場で彼と知り合ったK子は、彼と出掛けるときは、いつも2人きりか同僚と一緒だったので、彼のバディたちには会ったことがなかった。もちろん「高校生の頃からの親友たちに会って欲しい」と何度も言われていたのだが、彼から話を聞く限り、その親友たちはK子やジェイとかなり異なるタイプの人たちのようだったし、ちょっとレッドネッキー系な発言も見え隠れしたので、K子はいろんな理由をつけて、ずっと避け続けていたらしい。
でも、その日はやって来た。半年も付き合っていれば避け続けてはいられない。ある寿司屋に集合したK子たちを含む3カップルすべてが、アジア人女性と白人男性の組み合わせだった。その中には、ほとんど英語が話せない日本人女性もいて、その女性はジェイが特に親しいというデイブ(仮名)の奥さんだった。なんかやばい雰囲気だなあと思いながら仕方なく食事をしていたら、男性陣がアメリカ人女性の悪口を言いはじめた。そのあまりのルーザー的な会話にK子は固まったが、“ジェイは違うんだ、適当にうなずいているだけなんだ”と信じ、黙って様子を見ていた。すると例のデイブが奥さんを目の前にしながら奥さんの自慢話をはじめ、そのままアジア人女性の従順さについて話が展開。しまいには奥さんに向かって甘ったるい声で、「ずっといい子にしてないと、グリーンカード取れないよお」と、言ったそうである。そんなことまで言われても、ただヘラヘラ笑っているその女性に対しても同性としてすごく頭に来たそうだが、K子が泣きたいほどショックだったのは、そこにいた全員と一緒になって、ジェイが「そうだよ、いつもいい子でいなくちゃね」と言ったことであった。デイブを戒めなかっただけでなく、そういうバカげた考え方に同調した自分の彼を見て、その瞬間にK子は別れを決意したそうだ。当たり前である。
この話を聞いた後、私たちが過去に遭遇した“米食い君”話が沸騰したことは言うまでもない。(英会話のカンバセーション・パートナー君、“僕、日本語勉強してます”君、自称東洋美術コレクター君など多過ぎてここにはとても書き切れない。)
しかし半年も付き合っていながら、K子はなぜ気付かなかったのだろうか?「気付かなかったんじゃなくて、認めたくなかったのよね、たぶん」とK子。分からなくもない話である。もしそれを認めたら、彼は“世界にひとりしかいないK子だから”K子を好きになったのか、それともK子という個人より“日本人だから付き合いたい”という思いの方が先だったのかという、ある種の人格否定にまで話が発展しそうな問題が浮上してしまう。「でも問題を先送りしたところで、結局傷付いたのだから同じことだったわ」と言い、K子は大きくため息をついた。人のことを心配している場合ではないが、次にK子が出会う男性に心から期待したいものである。
ところで、私自身も“米食い”君に言い寄られた経験が何度もある。K子の経験ほどひどいものはないが、バーや寿司屋のカウンター、バスの車中など“米食い”君との遭遇はどこにでも発生する。そしてたいていの場合、その最初のひとことは、「日本人ですか?」である。だから私は、そうやって唐突に話し掛けてくる白人男性をとても警戒するようにしている。米食い君の定義に当てはまる人にも要注意だ。先日も、定義の見本のような白人男性が遠慮も見せずに「キミは日本人?」となれなれしく話かけてきたので、「そうだけど、私はステレオ・タイプの日本女性ではないから、きっとあなたが聞きたいような答えの数々を与えてあげられないと思うわ」と言ってやった。そこにいた友達みんなが必要以上に盛り上がったので、そいつも少しは懲りたはずだと思ったが、後日、同じ男性が同じバーで日本人らしきアジア人女性の腰に手をまわしながら飲んでいるのを目撃し、呆れてしまった。多くの日本人女性たちに、もっとしっかり相手を見て欲しいと願うばかりである。
第4話 「アメリカにいる困った日本人」
30歳を過ぎたシングルの女性に対する世間の目というものは、残念ながらアメリカにも存在する。
確かにアメリカでは、ゲイのカップル(男同士でも女同士でも)が手をつないで街を闊歩していても立ち止まって振り返ったりしないし、大学にシングル・マザーのクラスメートがいても、「いろいろ大変でしょう?」などと興味津々に事情を聞き出そうとするオバサンみたいな学生もいない。ここでは、そういうことはマナーに反するからだ。その上、“頭が悪いと思われるような質問をすることほど恥ずかしいことはない”という風潮もある。だから普通に常識を持った人であれば、知らない人のプライバシーを干渉しないし、“それぞれの人生観や好みの違い”に対するアメリカ人の認識度は、日本人のそれに比べて間違いなく高いだろう。しかし、そんなアメリカに住んでいても、30歳を過ぎた独身女のプライバシーは干渉されてしまうのである。
とは言っても、これまでのアメリカ生活の中で、アメリカ人にプライベート・ライフを根掘り葉掘り詮索されたことは、相手が私とお付き合いしたいと思っているような特別な場合を除けば、ほとんどない。人のプライベート・ライフを詮索したがる“困った人たち”のほとんどは、ここに住む日本人既婚者の方々なのだ。
先日も、仕事がらみでお付き合いのある日本人の方が主催したパーティーに招待されたので出席した。招待状には通常のことながら、「伴侶、パートナーも、ご一緒にお越し下さい」と書かれていたが、日頃からそういうパーティーに“まだ様子を見ている状態のボーイフレンド”や、“適当な人を同伴する”のが好きではないので、この日もひとりで出掛けた。でも、宴もたけなわになると思った通り、「あなたはお一人なの?」とか「相手を選びすぎなのよ」とか「やっぱり子供だけは作っといた方がいいわよ。急がないとね」などと、まったく無責任なことを言うオバサン化した女性たち(まだ若いのに!)や、「で、どうなの、結婚の方は? 誰かいないの? 知り合い紹介してあげようか、ハハハ」などと発言する男性たちが話し掛けてきた。
はじめて会った人に向かって、いきなり結婚の予定を聞いたり、子供を作れなどと言うような人たちには、本当にいつも驚かされる。すべての人々の価値観が絶対に自分と同じだと信じているのか、相手の気持ちというものを気にしないのか、単におばかさんなのか、その理由は分かりかねるが、どちらにしても困った人たちである。このような質問をされるたびに思うのだが、こういう日本人たちは、パーティーでたまたま同席したアメリカ人にも、私に言うのとまったく同じ質問をしているのだろうか? きっと、していないだろう。彼らもここに住んでいるのだから、ここでのマナーをある程度知っているはずだ。とすると、「日本人同士だからいいよね!」っていう感じなのだろうか。そういうのは分からなくもないが、同じ日本人でも、それが嫌でアメリカに住んでいる人だっているだろうし、相手が答えたくないかも知れないことを公衆の場で質問するというのは、どの国であれ失礼なことだと思うのだ。
そういうわけで一時期は、日本人が大勢集まるパーティーの招待をことごとくお断りしていた。すると今度は「あの人は日本人とのお付き合いを大切にしない」とか、「変わり者だから、いつまでも結婚できないのよ」などと、さらに勝手な詮索をされただけでなく、口に出して言われたりする。私が欠席したパーティーに居合わせた友人のA子は、「あなたの私生活について、かなり適当なこと言ってたわよ。だから、“秋野さんとすごく親しいんですね、知らなかったわ”ってワザと聞いてやったら急に話を変えてたわ。終わってるね、あの人たち」と、笑いながら教えてくれたのだが、言われた本人としてはお手上げである。ただ“1度か2度、パーティーで同席しただけ”なのに、どうして彼らが「私に何人くらい日本人の友人がいるのか」とか、「どういう人と付き合っているのか」なんてことが分かるのだろうか。まったく、困ったものである。そんなことよりも、他に話すべき話題がないのだろうか?
ちなみに、この事件の後、アメリカ人の友人たちに、前述のパーティーでのことを話してみた。その場には10人ほどのアメリカ人がいたが、誰もが「えっ、冗談でしょ?」、「なぜ友達でもないのに、そんなパーソナルなことを聞くの?」と驚いていた。なかには「それ、おもしろい! 僕もいきなり他人にそんなこと聞いてみたい!」と大爆笑している人や、私が作り話をしていると思って、「そういう冗談はやめなよ。信じちゃう人がいるかも知れないよ」とシリアスに言う人がいたりと、かなりの盛り上がりを見せた。少なくても、そこにいたアメリカ人たちには、“親しくもないのにパーソナルなことを聞く”ということは、“信じられないコト”のようだった。
でも、だからといって、そういうアメリカ人たちの常識や反応が、私をこの“お手上げ状態”から救ってくれるわけではない。30歳を過ぎた独身の日本女性の場合、日本人が大勢集まるパーティーに出席してもしなくても、結局はめんどうな目に遭うのである。なぜ私のような状況に置かれている多くの女性たちが、そういう場にできるだけ出向かないようにしているのか、これによって少しでも多くの方に理解してもらえたら不幸中の幸いである。
第5話 「コミットメント症候群」
私のシングル友達の中に、ルックスの良さに定評があるジェイという男がいる。年齢は36歳、フリーのグラフィック・デザイナーでかなりの高収入だが、それをひけらかすようなことはまったくなく、性格もとってもチャーミングで優しい。つまり、どんなパーティーに顔を出しても、そこで彼と初めて会った女性たちの誰かが、後日何気なさを装って「ねぇ、あの彼はシングルなの?」と話題にするようなキャラクターなのだ。
先日みんなで集まって飲んでいるとき、そのジェイが「そういえば、あの彼女とは別れたんだ」と発言した。「えっ、また?」、「どうせ、またお前が切り出したんだろ」、「あー、彼女かわいそう、普通の子だったのに」と、一同はすっかり呆れたが、誰もジェイに「今度は何が問題だったのか?」とは聞かなかった。というのも、そこに居た誰もが、ジェイが彼女と別れた理由を簡単に想像できたからである。ジェイは「将来を共に暮らす約束」というものを「地獄への入口」だと本気で恐れている「コミットメント症候群」の重症患者見本のような男なのだ。
いつだってジェイは、自分が付き合っている女性が、“ほんの少しでも”彼と結婚したい意志を匂わした途端、激しい引き潮のように急速に相手に対する興味を失い、事件後、すぐにその相手と別れてしまう。この場合の「事件」とは、女性がジェイの優しさにうっとりして、「あなたとずっと一緒にいたいわ」などと、うっかり発言してしまうことを指す。
そんな発言ひとつで、それまでラブラブだった彼から突然振られてしまう女性も気の毒だが、もっと気の毒なのは二人が別れた後の状況だ。
驚くほどのスピードで相手から引いてしまうジェイだが、女性(誰であろうが、その時点での元彼女)が結婚願望さえ持たなければ、彼だって一度は好きになったその女性に未練がある。だから、女性が「お願い、また会いたいの」などと電話してくると、意志の弱いジェイはすぐ彼女と会ってしまう。それが別れた半年後というならまだ分かるが、彼の場合、たいてい3日後には再会を承諾し、そこで必ず女性に「よりを戻してほしい!」と泣きつかれるのだ。このパターンが、私の知る限りだけでも5年は続いている。振られた男に「また会いたい」などと電話する女も女だが、ジェイもジェイだ。本当に学習しない男である。
私も含めて、ジェイの友人一同は「たとえ会いたいと言われても、結婚する気がないなら、彼女のためにも二度と会うな!」と言い続け、ジェイは毎回「分かってるよ。僕が悪いんだ」と深く反省する。非常に素直な点も彼の長所である。でも、やっぱり呼び出されると会ってしまい、そうこうしているうちに、女性側はそれまでと変わらないジェイの優しさに包まれて「もとに戻ったんだ」と錯覚し、また「事件」が起きるのだ。そして、女性は非常に困惑し、我々(ジェイの友達)の誰かに泣きながら「私は一体どうしたらいいの?」と連絡してくるのが、毎回起きる悲しい結末である。
ジェイのこの傾向は、今に始まったことではない。本人いわく、「誰にも束縛されないことが最も大切だと考える僕には、どうしようもない衝動」らしい。それでも、ジェイが「コミットメント症候群」だとは気づかずに彼に惹かれ、彼を追いかける美しい女性たちが後を絶たないので、彼の行動に深く傷けられる女性の数は増え続ける一方である。ジェイにしてみれば相手を傷つけるつもりはまったくなく、結婚問題が浮上するたびに、いかに相手を傷つけずに別れてもらうか相当悩んでいるようだが。
30歳代という自分の年齢からだろうが、最近、ジェイ以外にも「コミットメント症候群」にまつわる話をよく耳にする。7年間も付き合っていたアメリカ人の彼から「きみのことは愛しているが、そんなに僕と結婚したいなら、別れるしかないと思う」と言われた私と同い歳の日本人女性の話を皮切りに、ほぼ同様な理由で数組のカップルが同棲を解消したり、別れてしまった。
そんな周囲の状況を久しぶりに会った男友達に話していたら、「そういうキミも、まだやりたいことがあるだの、家庭を持ったら今のようには仕事ができないだのと、なんだかんだ理由をつけて、今まで付き合った相手とみんな別れてるじゃないか。キミこそ、立派なコミットメント症候群なんじゃないの?」と言われてしまった。
うー、それは考えてもみなかった! ジェイのことをこうやって非難している私自身も、実はコミットメントを恐れている症候群患者なのだろうか……?!
第6話 「一軒家願望の行方」
わざわざ改めて言うことでもないが、私は独身である。しかも、仕事はフリーのライターだ。つまり、アメリカでの私のステータスは、「何の保証も持っていない外国人の女」ということになる。こんなことは自慢にもならないが、ダンナがいないから保証人になってくれる人もいないし、合法で働けるが、フリーだから年間の給料保証もない。
そんな私が、「小さくてもいいから、一軒家が欲しい!」という願望に取りつかれてから、早1年が経とうとしている。オープンハウス(売り出されている家が自由に見学できる日)があれば足繁く出掛け、不動産屋さんにだってお会いした。でも、気に入った物件を見つけて、「うぉーっ! 買いたい!」と思っても、今の私のステータスでは銀行のローンが組めないのだ。相手(ローン・オフィサーというご職業の方)に笑われてしまったことさえある。はっきり言って、これはかなり情けない。もちろん、私が用意できる頭金が「ゼロに近い」という事実も災いしているのだろうが、ないものはないのだ。
でも、そんなことでくじけていては、「窓の大きな仕事部屋があって、パティオがある可愛い一軒家」は一生、手に入らないかもしれない。そこで、ちょっと作戦を変更し、会う人、会う人に「いやー、今、すごく家が欲しいんですよねー」と言いまくることにした。「願望をいつも口に出すようにすると、必ずそれが手に入る」という話を聞いたからだ。誰から聞いたのかは覚えてもいないが、「まあ、とりあえず言わないより、言ってみた方がいいだろう」と思って実行することにしたわけである。
そんな折、ある雑誌の仕事で、以前ほかの仕事でご一緒したアメリカ人の男性カメラマンと久しぶりに再会した。かなり儲けているカメラマンなのだが、高飛車なところがなく、明るくて性格もいい人なので、前回の仕事のことやら最近の調子やらと話がはずみ、撮影後に一緒に食事をすることになった。もちろん私はその席でも、例の「いやー、家が欲しくて……」のフレーズを口に出した。すると、そのカメラマンも家を探しているという。「やっぱり一軒家だよ。僕はこういう物件がよくて……」と、彼は一軒家の魅力を力説しはじめ、理想の家を購入するという話題で思いのほか場が盛り上がる中、その日は楽しく食事を終えた。
しかし、その翌日から私の状況は一変した。毎日のように、そのカメラマンから「元気? どう調子は?」とフレンドリーな調子で電話が掛かってくるようになったのだ。そして、家を購入する頭金もないくせに外食が大好きな私の嗜好を簡単に把握した彼は、頻繁に私を豪華な食事に誘い出し(おいしいもの、しかもオゴリとなると絶対に断れない私も私である)、さらにはバンクーバーまで日帰りでおいしいものを食べに行くプランにまで乗せられて(そんなおいしいプラン、断れない)、美食三昧の数週間を過ごさせていただいた。お互いの趣味は食事以外まったく合わないが、仕事も結構似ているし、理想の一軒家の話なら尽きることがないので、それなりに楽しい「ごはんバディ」という友人関係を保っていたわけだ。少なくても、私はそう思っていた。「稼ぎの少ない私にいつもご馳走してくれてありがとう」と。
そして突然、その日が来たのである。彼が「サプライズがあるから」と、車で私を迎えに来たのだ。どこへ行くのかと聞いても秘密だというので、私はまたおいしいものが待っているのかと思って、ウキウキして車に乗っていた。しばらく走って、シアトルの某新興住宅地にある可愛らしい家の前に車が止まると、彼は満面の笑みを浮べてこう言った。
「僕の新しい家にようこそ。この家なら絶対にキミが気に入ってくれると思って買ったんだ。キミの仕事部屋もパティオもちゃんとあるよ。サプラーイズ!!」
たぶん、こういうことを本当の「サプライズ」というのだろう。これには腰が抜けそうになると同時に、全身が凍りついてしまった。きちんと「お付き合い」もしていないのに、相手と一緒に住むための家を先に購入してしまう人がいるなんて、私のような凡人には予想もつかないことであった。さすがアメリカ、いろんな人間がいる国である。しかし、いくら一軒家が欲しくて、しかも購入する金さえなくても、私だって「そうですか、じゃあ、お言葉に甘えて」という訳にはいかない。私にも、今までひとりで頑張って生きてきたプライドがある。いつか出会いたいと夢見る、自分にとっての理想の男性像だってある。彼はとてもいい友人だけれど、残念ながらこの先、一緒に暮らしていくなんて想像もできない相手なのだ。
とにかく、そのときは丁重にサプライズのお礼を述べ、その後、きちんと時間をかけて私の気持ちをご説明させていただき、その結果として、素晴らしい「ごはんバディ」と「一軒家」は私の生活の中から消滅した。後で分かったことだが、私が家を欲しがっていたことを、彼は「私は早く家を買って、そこで家庭を作りたいと思っている」と理解してしまったようである。ああ、言葉って難しい。
この事件によって私が学んだことは、「人様に、自分が一軒家を欲しいなんてことをペラペラと話すもんじゃない」ということである。うーん、今度はまた別の作戦を考えなくては……。
第7話 「愛すべきゲイの男友達」
シアトルに住んでいて良かったなと、しみじみ思うことがある。その理由のひとつにあげられるのが、素敵なゲイの友人たちと出会えたことだ。
地元の方ならご存知の通り、シアトルにはゲイが多い。もちろんサンフランシスコやニューヨークの多さとは比較にならないが、シアトルの街の規模と総人口を考えたら、この街のゲイ人口密度は非常に高い。そのため、わざわざゲイバーへ出掛けたわけでもないのに、私の男友達のほとんどがゲイである。この街で普通に生活する中で自然に友達になった独身男性の多くが、「たまたまゲイ」だったのだ(少なくても私の生活においては)。
私のように30代も半ば近くなると、古くからの女友達はたいてい結婚しているし、仕事と子育ての両立で大忙しという人も多い。だから仕事が終わって「ちょっと軽く飲みに行きたいな」と思ったときに、以前のようにピピッと携帯に電話して呼び出せる女友達が年々(いや、月々か)少なくなってきた。以前はあれほど「出掛ける時には絶対に誘ってよね!」と言い、たまにうっかり誘わなかったら超不機嫌になっていた女友達でも、「うーん、すごく行きたいんだけど、突然誘われても子供が……」なんて言ったりしちゃうのだ。これはかなり淋しい。なんだか自分だけ取り残された気分になってしまう。そんなときに期待を裏切らない最高の飲み友達となってくれるのが、ゲイの友人達なのである。
同年代の女友達とは違い、ゲイの友人達はパートナーができても、それ以前と変わることなくずっと一緒に遊んでくれるところが素晴らしい。もちろん彼らだって仕事もあれば、プライベート・ライフもあるので、予定が空いていなければ来てはくれないが、たいていの場合、呼び出したらすぐ飛んで来てくれる。突然電話しても、「えー、そんな急に言われても……」なんてダウナーなことは言ったりしない。その上とってもセンシティブなところもいい。ちょっと落ち込み気味の時に電話した場合でも、素早くこちらの気分を察知し、「だめだめ、そんな気分の時にひとりでいたら落ち込んじゃうから、今すぐそっちに行くよ! 持って行くのは赤ワインでいいよね?」などと優しいことを言い、元気づけに来てくれる。シングルの私には本当に心強い友人たちなのだ。
中でも特に親しい友人のケリーとは、年齢も同じだし、趣味も職種も似ているのでかなり頻繁に会っているが、彼ほど楽しくてヘルプフルな連れはなかなかいない。たとえば一緒にショッピングに出掛けて洋服を選ぶ時には、「それ太って見えるから、やめなよ」とか、「これはダメ。こんなの着てたら頭悪いと思われるよ」などと、ものすごくはっきりとポイントを指摘してくれるし、映画を観に行くとなれば、普通の男性ならバカらしいと嫌がるハッピー・エンドのロマンティック・コメディーだって喜んで一緒に観てくれる。料理の味にもこだわるからレストラン選びもハズさないし、アート・ギャラリー巡りやミュージカル鑑賞も大好きだ。ついでに言えば、ケリーはルックスもいいし、頭もキレる。つまり、彼は絵に描いたような完璧なバディなのである。
先週末には、ケリーが一緒に住んでいるパートナーのボブが休日出勤で留守だったので、彼らがよく通っているおすすめのスパへ一緒に連れて行ってもらった。ふたり揃って優雅な半日コースを施術してもらい、終わってからシャンパンを飲むというゴージャスな休日を過ごしたのだが、こんなことは女友達とでもなかなかできることではない。いつもに増して、とっても楽しかったので、シャンパン・グラスを傾けながら彼に言ってみた。
「あーあ、いつも思うんだけど、ケリーが私の彼だったら最高なのになあ」
すると彼は、美しい顔に満面の笑みを浮べて、当たり前のようにこう言った。
「まったく、何を言ってるんだよ。いくら僕がキミのことを愛していても、僕は今さらレズビアンにはなれないよ」
ああ、ややこしい。でも、そうよね、あなたはそう考えちゃうのよね。まったく、私のシアトル生活はどうしていつもこんなにややこしいのかしら……。
第8話 「友達を友達に紹介しない男」
シングルの女友達T子(32歳)には、誰が見てもT子の彼だと勘違いしてしまうほど仲の良い男友達がいる。
その男友達、ロッド(仮名・36歳)は売れっ子のウェブデザイナーで、全米でも有名なロックバンドのオフィシャル・サイトなどを手掛けたりしている。業界にも顔が広く、パーティー好きなロッドとT子は、1年ほど前にあるバンド関係のパーティーで知り合って意気投合。以来、ロッドは毎日のようにT子に電話をかけ、お互いの家でごはんを食べたり、映画やパーティーに一緒に出掛けたりしている。私達が女友達で集まるときにもT子にくっついてロッドが来るようになったので、T子の友人達は必然的に彼と友達になった。女友達の集まりだと知っていても顔を出してしまうロッドは、確かにちょっとウザいが、話もおもしろいし、T子が好きならまあ仕方ない。なによりも、これでようやくT子もシングル・ライフから脱出か、と周囲の期待は高まっていたのである。
そんなT子と先日、久しぶりにロッド抜きで飲んだ。そろそろロッドとちゃんとお付き合いしてもいいんじゃないのと振ると(そうすれば彼も落ち着き、女友達の集まりには来なくなることを期待しつつ)、意外にもT子は、「ロッドと一緒に遊ぶのは楽しいけど、絶対に付き合う気はないわ」と強い口調で跳ね返してきた。なんでもロッドは、彼女の友人全員の携帯番号を持っているほど彼女の生活に入り込んでいるのに、彼女のことは彼の友人に絶対に紹介しないそうである。そういう人は根本的に信用できないと言うのだ。
あれだけ親しい友人であるロッドがまさかT子を自分の友人たちに紹介していないとは知らなかったので、これには驚いた。人を人に紹介することが一種の礼儀でもあるようなアメリカ社会において、これはかなり問題である。まるでT子の存在を彼の友人たちに隠すような行為ではないか。T子が立腹するのも当然である。
しかもロッドには友人がとても多い(ように見える)。私たちが一緒にいるときも、たいてい彼の携帯は学生のそれのように鳴りっぱなしだし、「俺の友達が○○で……」という友人話も非常に多い。どこかのバーに行っても、いつも誰かしら彼の知人に遭遇するので、彼はしばらく相手と話をしてから私たちのテーブルに戻ってくるというパターンが日常化している(いやー、そういえば私達もそういう相手側に紹介されたことがないかも知れない)。それなのに、1年以上もあれだけT子と仲良くしていながら、ロッドの業界仲間や昔からの友達を、T子が「たったひとり」しか知らない(それも偶然に会ってしまったので紹介しないわけにはいかない状況だったらしい)というのは絶対におかしい。
そのうえ、T子が知っているその「たったひとり」の友人AとT子が直接連絡を取ることを過度に嫌がるというのだ。「あいつは問題が多い」などと理由を付け、T子がAに用事があると言っても連絡先を教えないらしい。また、彼の携帯に頻繁に電話を掛けてくるKay(仮名)という女性がいるのだが、T子が「今度紹介してよ。みんなで一緒に食事でもしようよ」と言っても、絶対にイエスと言わず、「Kayはちょっと変わっているから」などと言って会う機会を作ってくれないそうだ。つまり、ロッドの友達にはT子を紹介しないが、「T子の友人達」の集まりには顔を出すというダブル・スタンダード状況だ。
なぜ、ロッドはそんな行動を取るのだろう? T子以外に親しい女性でもいて、その事実をT子に隠しているのだろうか。それに対してT子は、「私が別の女友達の存在を知ったら、彼と距離を置きはじめると勝手に思い込んでいるのかも知れないわね。でも基本的には、中身が子供なのよ。私と彼の友達が、彼を飛び越えて仲良くなってしまうことが嫌なの。だからあれほど必死で阻止する。つまりは自分に自信がないんじゃないかな」などと妙に冷静に語るのである。
もちろん、そんな男とは誰だって真剣に付き合いたくはない。30代も半ばになって、そんな高校生のような行動を取る人がいると思うと、ちょっとがっかりというか、なんだかこわい。T子によると、そういう行動をとってしまう大人ってアメリカ、特に大都会に結構多いのだとカウンセラーにも言われたそうだ。うー、なんだか最近、まともな男達が日々少なくなっているような気がするんだけれど、それは私の周囲だけなんだろうか。
第9話 「完璧な彼を持つ恐怖」
最近、その数が確実に減ってきてはいるが、私の「シアトル在住日本人独身女友達」のひとりに、某有名企業M社で働くS子がいる。現在30歳。明るくて、楽しいことが大好きな彼女は、いつでもアフターファイブの予定がいっぱいだ。19歳でアメリカに留学して以来、4年制大学を卒業し、転職を繰り返しながら、結果的に自分の力で移住を果たした。日本人アクセントがない英語を話し、仕事も順調、しかもルックスだって結構いい。
結婚を夢見る魅力的なS子が、なぜ未だにシングルなのか? そればっかりはわからない。しかし、常に「私は絶対に幸せをつかむ!」と強気な彼女の唯一の問題点をあげるとすれば、男性に対してかなり節操がないという点であろう。
周囲の誰もが懸念しているのだが、S子は基本的に「ひとりで過ごす時間」がとっても苦手である。仕事を持つシングル女性の大多数が楽しんでいるようには、「ひとりで過ごす時間」を楽しめないそうだ。だから結果的に、「いつも誰かそばにいて欲しい」ということになり、節操がないと思われるような行動に走るのである。
それならば、一般的に見てもモテるのだから、「適当に相手を見繕って結婚してしまえばいいのに」、と大多数の方は思うであろう。私たち友人一同もそう思っている。しかし、残念ながらその作戦はいつも失敗に終わる。「いつでも誰かにそばにいて欲しい」と言っているくせに、「誰か」が見つかると、S子はいつも相手の希望はさておき、「自分が彼としたいこと」を強引に押し通してしまうからだ。口調はソフトでかわいらしいが、S子の強引さはかなりのものである。周囲がどれだけ忠告しようとも、S子自身にまったくその認識がないのも、さらなるOuch!(痛っ!)である。
そのため、たとえ強い結婚願望を持つ男性と出会ってお付き合いを始めても、必ず「残念ながら僕とキミとは見ている場所が違うようだ」などと、オブラートに包んだような非常に穏やかなセリフと共に、男性達は去って行ってしまうのである。ここ数年の間で、私はS子のボーイフレンドと“友人として親交を深めては、ある日を境に二度と会えなくなる”という残念な経験を、少なく見積もっても5回はしている。
ところが、そんなS子に素晴らしい彼ができたのだ。周囲の誰もが驚くほど、まさに絵に描いたように完璧なボーイフレンドである。その彼、アンディ(仮名)はかなりのスポーツマンだが、クラブやバーに出掛けるのもアウトドアも大好きで、友人も多く、ルックスは抜群。高収入だし、とてもフレンドリーで、彼女の友人達にも親切で優しい。たちまちS子の女友達みんなのお気に入りになった。とにもかくにも「完璧にチャーミングな奴」なのだ。
S子がアンディと付き合って、かれこれ半年が経った。これはS子にとって記録的な快挙である。若くて元気いっぱいなアンディは、S子の望むことを何でもオモシロがって受け入れ、ふたり揃って毎日のように遊びまくっている。まさにS子にぴったりだ。彼女の友人である私達と一緒に飲みに行っても、アンディはいつだってS子の肩を抱き、彼女を気遣ってとてもスイート。言うまでもなくS子は「もう、毎日楽しいことばかりで最高!」とノリノリである。付き合い始めてから一度も口喧嘩すらしていないとふたり揃ってノロケさえする。「すごすぎるぞ、アンディ! 完璧だ!」と周囲も沸いた。そして、そんな理想的な日々を送る幸せなS子の前に、突然その事件が起こったのである。何の前触れもなく。
彼が突然、切れたのだ。チャーミングで、スマートで、楽しいことが大好きで、とってもハンサムなアンディが、突然マジに切れてしまったのである。
それはS子がアンディの家で、いつものようにビールを飲みながら、その夜に予定されたイベントを『Seattle Weekly』でチェックしているときだった。アンディが、「ねえ、○○なんて、こんなイベントがあるよ。おもしろそうだね」とS子に言い、S子はいつものように「ふーん、でもXXXっていう、こっちの方がもっと面白そうじゃない?」と、相槌を取るくらいのカジュアルさで、思ったことをそのまま口に出した。すると一瞬の沈黙のあと、彼が突然、手にしていた雑誌を床にバーン!と叩きつけ、大声で「FXXX!!! いい加減にしろよ! もうキミの好みばかりを聞くのはたくさんだー!! FXXX you, bxxxh!!!」と、発狂してしまったのである。
あまりに突然の展開で、まったく事態が飲み込めないS子は、「へっ?」って感じで、しばし唖然としていた。しかし、そんなS子をまったく無視して、それから何と約1時間に及び、アンディは自分の想いを吐き出すように叫び続けたそうだ。その怒涛でまるで部屋が揺れているように感じた、とS子は語る。いつも笑顔を絶やさない、絵に描いたようなチャーミングなアンディ、がである。そして彼は、さんざん叫び狂った後、S子にこう言ったのだ。
「悪いけど今すぐここから出て行って、2度と遊びに来ないで欲しい。もうキミとは一切付き合えない。連絡も取りたくない。僕の人生の中から消えてくれ」と。
「あまりにもショックで涙も出ないわ……」と淡々と語るS子を囲んで、私たちは全員固まってしまった。彼を知っていただけになおさらだ。普通なら、自分の彼女の言動に対して何か思うことがあれば、付き合っているのだから、その都度その旨を相手に伝えて問題を解決していくはずだろう。しかも一般論として、日本人よりもアメリカ人の方が自分の思ったことをすぐ言葉に出し、話し合って解決策を見つけようとする傾向が強い。だが、彼はきっとそれができない性格だったのだろう。S子の女友達は全員、S子の「me, me, me, give me more」という自己中キャラにすっかり慣れているし、彼女にはほかに良いところがたくさんあるので、S子の「ミーミーミー攻撃(笑)」は、私たちにはそれほど大した問題ではない。だから、誰ひとりアンディがそこまで追い詰められていることに気付かなかった。
結果として、彼は「毎日のように会っていた自分の彼女」に対して「半年間にも及ぶ長い間、言いたいことをずーっと自分の中に溜めていた」ので、「ある日、それが極限に達して完璧に切れてしまった」のである。英語の表現なら“The end of the rope"ってとこだろうか。でも逆に言えば、アンディがS子にも私達の前でも「常にとっても魅力的」で「常に完璧な彼」でいられたのは、「嫌だと思ったことを一切口に出さないで極限まで溜めるから」かも知れない。いつも素敵な男でいるために……。でも、少なくても私は、どんなに素敵でもマジ切れするような男とは一緒に暮らせない。
とにかく、この事件はS子の心にはもちろんのこと、私達の心の中にもドデカイ波紋を作った。深く落ち込んだS子を励ましながら、何日も費やして私達が出した非常にシンプルな結論は、「完璧すぎる彼と出会ったら要注意」という、バカみたいにそのまんまな教訓だけである。
第10話 「養ってもらえる女と、そうでない女」
このところ毎日のように、アメリカ人の男友達が電話を掛けてくる。この男友達とは以前数年間付き合っていたので、いうなれば私の元彼である。私の友人の中には「何年も付き合っていた元彼と友達でいられるなんて信じられない。そんなのは偽の関係よ!」とムキになる奴もいるが、喧嘩別れをしたわけでもなく、将来設計を話し合う頃になって「仲良しだし、一緒にいて毎日楽しいけれど、やっぱりふたりの求めている何かがお互いちょっと違うよね」と、冷静に話し合って別れたので何の修羅場もなく、「お互いに何でも話せる一番親しい友人のひとり」というポジションに、ストンとはまっている次第である。
とにかく、その彼がこのところ毎日(日によっては1日2、3回)携帯にまで電話を掛けてくる理由は、私に愚痴りたいことが山ほどあるからだ。「今、付き合っている日本人女性が、一体何を考えているのか全然わからない。別れたいんだけど、別れてくれないし……」というのが根本的な彼の愚痴なのだが、私の彼女でもないのに、そんなことは私の知ったことではない。だから、そうつっぱねると、「でも、とにかく話だけでも聞いてくれよ、今日もこんなことがあってさ……」という感じになって、結局は話を聞かされてしまうのである。
私と出会うまで日本人とは一度も付き合ったことがなかった彼だが、私が日本食好きで料理はほとんど日本食しか作らなかったうえ、日本が嫌いでアメリカに来たわけではない日本人だったために(日本を知らない彼にやたら日本自慢をしていた)、彼はすっかり日本びいきになってしまった。そのため、私とはいろいろあって別れたものの、その後に好きになった女性はふたり続けて日本人。「お願いだから米食い君にはならないでくれー!(注:過去コラム参照)」と、彼にいつも懇願している私だが、その責任の一端は私にあることも否めない事実である。
彼にとって最初に付き合った日本女性である私も、一般的に見て相当変わった女だと思うが、私と別れた後に彼が付き合った女性も、私とは違う意味でかなり変わっていた。「私、何もできないの」というのが口癖で、いつも人を下から見上げるようにモチモチっと話す姿が特徴的な人だった。結果として彼はその女性と数回デートして別れたのだが、それから1年くらい経って付き合い始めた今度の女性はもっと変わっていて、彼が真剣に愚痴っているのに思わず大笑いしてしまうほど、私の友達の中には絶対いないタイプなのである。
その日本女性はバツイチで40歳。現在14歳の子供がいるが、写真で見ると子持ちだとは思えないほどの美人である。女優の佐藤友美(知ってるかなあ)によく似ている。でも、何と、「生まれてから一度も働いたことがない」らしいのだ。40歳にして、バイトさえしたことがない人がいるという事実に私は素直に驚いてしまったが、日本の実家がとても裕福で、別れた旦那さんと実家がすべての生活費と養育費とおこづかいをサポートしてくれているそうだ。21歳で結婚し、26歳で1人息子を産み、その子を育てながら訳あって33歳で離婚。現在は「日本にいても別にやりたいこともないから、子供をアメリカの学校へ通わせたい」という理由で、彼女自身はアメリカのホテルと日本の実家を3ヵ月ずつ(3ヵ月ならビザがいらないので)往復しているそうである。いやー、そんなオイシイ人生があるのか、と私は驚愕したが、まさか自分の元彼がそんな境遇の女性と出会うことになるとは思わなかったので、私はそれなりにワクワクして状況を見守っていたのである。
彼が教えている絵画教室に彼女の息子が参加したので、この美しい日本女性と出会ったのだが、初めて会ったときはベルビュー辺りに在住する一流商社員の奥様だと思ったらしい。でも会った途端に彼女が、自分がシングルであることを彼に伝えて来たので、彼は彼女の積極性に驚いたそうだ。デートに誘ったわけでもないのに、初対面の人に自分から「私、独身で、時間がたくさんあって……」などと、自分の事情をペラペラ話す人はアメリカでは珍しい。とにかく、その彼女の積極的な言動をきっかけにデートをしてみることが決まり、3回目のデートで「アメリカにいる間は、あなたのアパートに住まわせて欲しい」と言われたそうだ。(すごいな、そういうことを言っちゃっていいのか、3回目のデートで!と、私は思ったが、人それぞれいろいろあるのだろう。そういうことを言える人こそが人生の勝者になるのかも知れないしな。どう思う、皆の衆?)
しかし、そうして彼の苦悩が始まった。息子を連れて、スーツケースを持った彼女が彼のコンドにやって来たのは、初めて会ってから1ヵ月も経っていなかった。それから、すでに2ヵ月が経ち、私のところに毎日電話を掛けてきては、「超美人だけど会話もつまらないし、愛情も生まれない。どうやって温和に出て行ってもらったらいいか?」と、相談をしてくる。「いいじゃない? 成り行き上、こうなったからには金持ちなんだから家のことをいろいろ面倒見てもらえば?」と、聞き流していたのだが、「それがさ、金持ちほど金のことを気にしないのか、俺が面倒みるものだと思い込んでいるのか、滞在費は一切払わないし、家事もできないんだよ。金も貰ってないのに料理も洗濯も俺がしてるんだぜ」と彼。「ひえー、何それ?」と驚きながら聞いてみると、離婚する前は住み込みのお手伝いさんがいて、離婚してからは実家かホテル暮らしなので、彼女は家事をやるという心構えすらないらしいのだ。彼女の中には最初から、男ができたら養ってもらうという決まりがあるのかも知れない。私のような根っからの仕事人(貧乏人?)には信じられないが、彼女はそんな彼の苦悩を気にする様子もまったくなく、家事もせず、かと言って外に仕事にも行かず、一日中、家で刺繍やトール・ペインティングをしたり、たまにブランドものの洋服や靴を買いに行ったりする日々を送っているらしい。
彼の苦悩よりも、あれほど文明が進んだ日本で3ヵ月毎に暮らしている女性の中に、このような女性が実際に存在するということ自体の方が私には興味深々なのだが(独占インタビューでもしたいくらいである)、彼は「彼女の頭の中がどうなっているのか俺にはわからない。子供もいるから、そう邪険に出て行ってくれとも言えないし、一体どうしたらいいんだ!? 後1ヵ月我慢して帰国するのを待てってことなのかー?」状態に陥っているのである。
「帰国する日を指くわえて待つしかないんじゃないのー? はっはっはっー」と、もちろん言った、私は。まあ、嫌なら最初から断ればいいものを、「あんな積極的に、あれほどの美人から一緒に住みたいと荷物を持って来られたら断れないよ、お前だって、そういうのわかるだろ?」なんて、呑気なことを言っていた彼が悪いのだろうから。「とにかく3ヵ月毎に日本に帰るんだし、もっと自由に暮らしたいなら、素直にそう言って出て行ってもらいなさい」と言う私に、「それが言えたら、もうとっくに言ってるよ。彼女はキミみたいな性格じゃないから、そんなこと言えないし。あー、俺の思っていた日本女性と彼女は全然違ってたー!」とドン底に落ち込んでいる男友達の声を聞きながら、「じゃあ、あんたは一体どんな日本女性を思い描いてたわけ?」と聞き返すと、何の躊躇もなくこう言ったのだ。
「キミのように俺の好きなことをすべて自由にやらせてくれて、一緒にいて楽しくて、料理上手で、理知的で、仕事もバリバリできる働き者。でも……」と、彼はここで一息ついてから続けた。「キミよりも、ずっと気が長くて、気の弱い女の子」
これを聞いて私が激怒したのは言うまでもない。「お前は米食い君かー!? そんな都合のいい女がいるわけないないだろー! お前の愚痴なんて今後一切聞いてやらん! もう電話掛けてくるなー! 一生、米だけ食ってろー! そんなにフラフラしてるから私にも逃げられたんだぞ、わかってるのかー!」と、電話口で唾を飛ばしながら怒鳴り散らす私に対して、彼は冷静に言った。「あのさ、何度も言うけどキミのこの勝気さとワークホリックさえなきゃ、キミは完璧なんだぜ、Sweetie。相変わらずわかってないなー。このままじゃ、マジで婚期逃すぜ、baby。まあ、誰ももらってくれなくて困ったら俺がもらってやってもいいけどな」「お前なんかに養ってもらわなくても私はちゃんと生きて行けるわよ、バカにすんな! だから結局別れたんじゃないの!」「何言ってんだよ、もらったとしても、養わないぜ。お前は元来、養ってもらう器じゃないからな」 「ちょっと待ちなさいよ。養ってもらう器じゃないって、どういうことよ?」「それはさ、例えば今の彼女は絶対に養ってあげないとダメっていう感じだけど、お前の場合は……」 「ふんふん、それで?」
というわけで、彼から持ち掛けられた相談が、最終的にはいつも私の欠落性格が婚期を逃すことへの助言となって帰ってくるという結果となるのだ。何なんだろう、これは? でも、きっと他人が聞いたら信じられないような正直な発言(罵倒か?)の繰り返しによって、私たちの友情はずっと続いているのである。だから、何でも話せる元彼を男友達に持つということは、いい女友達やいいゲイ友達を持つのと同じくらい自分にとっては大切でイイものなのかも知れない。
P.S. とりあえず、彼は子持ちの彼女に「申し訳ないが、出て行って欲しい」と言う決意をしたらしい。幸運を祈る。
第11話 「またしても誕生日の再来」
恐ろしいことに、この度、また誕生日を迎えてしまった。いい加減、この歳になると今まで毎年あれほど、「さーて、今年のバースデーは誰と何をして過ごそうか!?」と腹の底から気合いを入れて企画していた年に一度の大イベントが、まったく「イベント」ですらなくなり、むしろ「誕生日なんて、もう来なくていいよ」という状態にまで陥ってしまうのだから困ったものである。
30歳を過ぎた独身女性なら、ほとんどの人が誕生日の再来に関して同じような経験をしているとは思うが、「イベントにまでする必要はなくても、ひとりで過ごすのはやっぱり嫌よねー」って感じは少なからずあると思う。だからと言って、「誰でもいいからそばにいて欲しい」と言えるほど単純には割り切れないところが、賢い30歳代女性の複雑な部分でもあるだろう。まあ結婚はしていなくても彼やパートナーがいるならば、少なくても落ち込むことはないだろうが、私のように正真正銘のシングルの場合、「再び誕生日を迎える」ということに多少なりとも「ああ、またかよ」という、ちょっとしたネガティブ・フィーリングがあるはずだ。
だから、私は30歳をとうに過ぎていたのにもかかわらず、去年まで毎年かなり大勢の友人を呼んで大々的に自分のバースデー・パーティーを開催していた。しかも主催者は自分である。「まさに開き直り」と言い切って何の語弊もないが、騒いでヘベレケ(古いな)に酔っ払った方が、ひとりで落ち込むよりずっといいと思っていたのだ。
しかし、さすがに「この度さらに、またひとつ歳を取る」に当たり、私は今までとはまったく別の案を考案してみたのである。去年よりもワンランク・アップした女性を目指すべく、今年の誕生日はパーティー開催案をスパッと却下し、自分の内側と見つめ合うための「インナートリップ・デイ」とすることに決めたのだ。「なんだかんだ言っても私は大人なのよ。大人の女なのよ。パーティーやってる場合じゃないわ。瞑想よ、ヨガよ、自分の心と正面から向かい合うのよー!」と、単純にそう思ったからである。普通この歳になれば、日常生活の中で毎日ちゃんと自分と向かい合っている人がほとんどだろうから、胸を張って大声で言うほど「すごいアイデア」ではないのだが、その時の私にとっては、それは「すごいアイデア」だったのだ。
とにかく私はすっかりこのアイデアに酔いしれて、さっそく誕生日当日に「瞑想教室」と「ビギナーズのためのヨガ・クラス」を2本立てでブッキングした。こういうクラスに1日参加しただけで心の状態が変わり、瞬く間にワンランク・アップした女性になれるとはさすがの私も思わなかったが、やらないよりはやった方がいいに違いない。だから「もしかしたら予想以上に大きな変化が訪れるかも知れない」、「オーラが溢れて幸せな気分に包まれるはず」……などとワクワクしながら、非常にポジティブな(浮かれた)気持ちで誕生日の当日を迎えたのである。
しかし、期待しまくって参加した「瞑想教室」は、何だか「シアトル中の不思議な人達大集合!」という感じの集まりであった。たぶん教室の選択肢を間違えてしまったのだろう。もう少し健康的というか、「とにかくリラックスしましょうね!」的なラフな集まりを想像していたのだが、妙に神経質というか、形にこだわる頭デッカチな瞑想教室だった。クラス終了後に、インストラクターから「どうだった? とってもリラックスできたでしょう?」と聞かれて、「うーん、何だか逆にすごく疲れちゃいました」と正直に言ったら、「それは、あなたがまだオーラを感じる力がうんぬん……」としつこく引き止められてしまい、ますます疲れてしまった。
それでもその後は、近所で評判の新しいヨガ教室へ向かった。せっかくの誕生日に、ちょっとしたことでメゲてはいられない。これもワンランク・アップのためである。でも瞑想教室とは違い、予約していたヨガ教室は誕生日を理由にちょっと奮発した(値段が高い!)だけあって、インストラクターも素敵な人だったし、雰囲気も音楽もとてもいい感じで気分がすっかり明るくなった。その上、ビギナーズ対象だったので、運動オンチで化石のような体だと言われている私でも何とか1時間半のクラスを無事に終了でき、非常にリラックスしつつ、明るくポジティブな気分のまま誕生日を過ごすことができた。だから夜になって友人達が次々と掛けてくれたバースデー電話にも、いちいち「ヨガはいいよ。うん、結構楽勝だったよ。何かこう、気持ちが生まれ変わるって言うのかな。やっぱり私はこれからよ、ってポジティブな気分になれたしね」などと、ワイン片手に優雅に(得意気に)1日の感想を述べながら、自分の選択に酔いしれたのである。何だかんだ言っても「年齢なんてたいしたことじゃない」と思える、とても前向きな誕生日を過ごすことができたのだ。
翌日も私は「すっかり生まれ変わったような心地良い感覚」に包まれながら、非常に快調な1日を過ごした。何だってうまく行くような、実にいい気分だった。そして、まるでそんな私をおとしめるかのように、そのまた翌日に突然「あれ」がやって来たのである。今まで自分にはまったく関係ないと思い込んでいたコトが、遠慮も前触れもなく、いきなり。
30歳代半ばに差し掛かった女性ならば、ここまで読んで既におわかりの方も多いかと思うが、なんと遂に私にも来てしまったのである。「丸1日以上遅れて起きるひどい筋肉痛」が……。確実にまたひとつ歳を取ってしまった事実を、私がこの日、どれほど実感したかは言うまでもない。ああ、私のインナートリップへの道は続く、いや、続かざるを得ない……。
第12話 「アメリカの自動車保険おそるべし」
このところ複数の取材旅行が重なり、長い間、自宅を留守にすることが続いた。と、書くと、まるで今をときめく人気ライターのように聞こえるかも知れないが、それは大きな間違いである。売れているライターは毎日のスケジュールが多忙過ぎて、長期取材なんていう体力だけが勝負で実入りが少ない仕事を受ける暇などないからだ。だから、こんなことは自慢にもならない。
まあ、それはさて置き、ひとり暮らしだと長期で自宅を空ける際に困ることがたくさんある。それなりに可愛がっている観葉植物の世話もできないし、アパートの傍の路上に停めっ放しの愛車の行方も心配だ。お金に余裕があれば、ホテルマンばりの立派な管理人がフルタイムで常駐している高級コンドに住み、完璧なセキュリティーがついたガレージに車を保管し、「たまには部屋の換気もしてちょうだいね」などと言いながら管理人にチップを弾めば済むことなのだろうが、私のような平民にそんな解決法はありえない。また、たとえ高級コンドは最初から除外したとしても、もともと予算がないのでアシスタントも、メイドも雇えない。しかも自宅兼仕事場ではルームメイトも入れられないし、かといってアメリカ人の旦那もいない私のような状況の場合、長期で自宅を留守にするのは本当に面倒なのだ。
そういう訳で、平民で独身の私はここ数年、近所に住む親友のケイトに留守中の部屋の管理を頼んでいる。彼女が留守にする時は彼女の部屋を私が管理するというシンプルなバーターだ。「30歳を過ぎたら持つべきものは信頼できる独身の女友達」とよくいうが、まさにその通りだと思う。こればっかりは、30歳を過ぎて外国でひとり暮らしをしている人達だけがわかりあえる、骨のずいまで染みわたったアメリカ暮らしの教訓のひとつであろう。
さて、長期で留守にする際に困ることは多々あるが、なかでも一番困るのが留守中に届く各請求書の処理である。もちろん請求書の精算をすべて銀行の自動引き落としにすればいいのだろうが、アメリカ生活を始めてから今まで、なぜか自動引き落としに関連したトラブルに多々遭遇している私は、今でも原始的に毎月チェック(個人小切手)を各請求先に郵送して支払っている。今まで遭ったトラブルを思えば、チェックで支払う手間の方がずっとマシだからだ。
だから私は留守中にポストに溜まった郵便物と観葉植物の世話を頼んでいるケイトに、請求書だけは開封してもらって、その支払いまでお願いしているのだが、そこまで根回ししても穴が開くときは開く。彼女だって忙しいし、だいたい他人に自分の請求書の支払いまでお願いするなんて、とんでもないことなのだ。でも彼女はいつも通り、あるひとつの請求書を除いては、滞りなく管理してくれた。自動車保険の支払い日にだけ、数日遅れてしまったのだ。しかも、これは私から彼女への指示ミスで起きたので、単に私の不在が原因なのだが、これが泣いても泣き切れない結末を生んでしまったのである。
シアトルでのひとり暮らしの中で、車はなくてはならないもののひとつである。留学生のような短期海外生活者ならば車がなくても何とか生活できるだろうが、仕事を持って自立した独身女性なら、「ねえねえ、ちょっと重い物を買いたいから車出してえー」などと、用事ができるたびに猫なで声で男友達にねだる訳にはいかない。それこそ自立の基本である。よって私のように1,500ドルで購入した超中古のボロ車であろうとも車を所有することが必要になる訳だが、そのためには自動車保険を支払わなければならない。ついでに言うと、その保険の支払い金額はかなり高い。でも支払い義務があるので私は毎年きちんと支払っているし(1ヵ月毎よりも1年毎の方が安いので)、保険会社も「どこよりもセーブできる」というテレビCMでおなじみの有名な会社と長年契約している。今回は留守中のゴタゴタで、ほんの少しだけ(しつこいようだが正確には3日)支払いが遅れてしまっただけなのだ。
その悪い知らせは、クタクタに疲れ切って長期取材から帰宅した当日の私の元にいきなり届いた。自動車保険会社から自宅の留守電にメッセージが入っていたからだ。どうやら私が支払った金額が足りないと言う内容だったので、「ちゃんと支払ったのに失礼な奴だ!」と憤慨しながら私はすぐ電話を折り返した。
すると電話に出たお姉さんは美しい声で淡々と、「お支払いが弊社に到着した時には支払い期日を過ぎていましたので、ペナルティとして現在のお支払い金額は以前の倍額となっております。ですから不足分をお支払いください」と言うではないか! 倍額なんて車本体より高い金額だ。当然だが私は、アメリカに何年も住んでいるがこんなことは一度もなかっただの、長期で留守にしていた状況だの、今まで無事故無違反であることだの、アメリカには同情とか情状酌量というメンタリティーはないのかだの、そんな意地悪なことを言うなら他の保険会社に変えてやるだのと、長時間にわたって、それはそれは強靭に食い下がった。だが、お姉さんは優しい口調でこう言い放ったのだ。
「お気持ちはわかります。しかし、どう言われましても、残念ながらこれは規則です。故意でなくても、またその期間中に不在だったとしても、保険のない車を所持していたことは変わりません。また、今後少なくても2年間に渡り、お客様の新しくご請求させていただくことになる保険金額は変わることはありません。支払い滞納履歴が経歴データから消えることはありませんので、他の保険会社に変更なされてもこの履歴がコンピューター上に表記されますので、どの会社にお掛けになっても今までのようなお得な金額は提示してもらえないはずです。お疑いになるのであれば、どうぞ他社にもお問い合わせください」
この長時間に及ぶ電話での戦いを終えた瞬間の私の頬を、一粒の熱い涙が静かに流れ落ちていった。この悲しみの深さを分かち合える人が存在するならば、すぐにでもその人にすがりたいような心境だった。先にも言ったが、電話を掛ける前から長期出張を終えたばかりの私は既に立っていられないほどクタクタに疲れていた。しかも、苦手な電話での戦いの山場で相手が発したキメ台詞。保険に関する法律をよく知らない私はボロ負けである。貧乏だからこそ、加齢に鞭打ってまで頑張った体力勝負の長期仕事から得た収入が、その仕事に出掛けたために「3日間支払いが遅れた」結果として数年後の履歴消滅予定日まで支払い続けなければならない高額ペナルティに根こそぎ吸い取られて行くなんて……。苦しかった長い冬の間の出稼ぎ肉体労働を終えて、家族が待つ田舎の家に帰る途中、運悪く地元駅前で暴漢に襲われてしまった人の気持ちとでも言えば、少しは私の悲しみの深さを分かってもらえるだろうか。
ああ、何年住んでもアメリカのシステムには訳がわからないことが多過すぎる。たかが3日じゃないか(しつこいか)!? たまに思うのだが、アメリカ生活には「慣れたと思う頃に必ず何かの落とし穴が待ち受けていて、また振り出しに戻されてしまう」という妙なパターンがあるような気がする。ひとり暮らしの経験者なら、きっとこのパターンに思い当たるふしがあるはずだ。振り出しに戻されて、また一から立ち向かうことの繰り返し。だから、渡米した途端にアメリカ人と結婚しちゃった日本人の女友達に、「なんでいつも秋野ばかりが面倒に巻き込まれるのかねえ。どっか抜けてんじゃないのお」などと笑いながら軽く流されると、「何言ってのよ! 銀行や保険会社との交渉とか、車の修理工にぼったくられた金を取り戻す喧嘩だとか、自分ひとりで最初から最後まで全部英語でやってから言ってよ!」と、思わず言い返したくなるほどムカついてしまう私の気持ちも、“またもや振り出し経験者”なら(しかも振り出しに戻った数が多ければ多いほど)、きっとわかってくれるに違いない。
しかし、外国で生活しているのだから、困難があって当然だ。確かに納得いかないし、くやしい。でも、これも勉強だと思って明日からは笑顔で何とかがんばろうと思う(健全な青少年に生まれ変わったような気持ちで)。そのくらい腹の底から気合いを入れ直さなきゃ、倍額にされた保険金の支払いに今後2年間も立ち向かう自信なんて持てないからである。ああ、貧乏暇なし、さらに金なし。こんな不憫な私を助けてくれる救世主は、はたしてこの広いアメリカに存在するのだろうか?
編集部より:今回の秋野未知と同様の経験をして気持ちが分かち合える読者の方、または秋野の現状を救える可能性のある保険会社勤務の方がいらっしゃいましたら、どうか編集部へご一報ください。
第13話 「シアトルの冬を乗り切る弱気打開策」
シアトルの冬は、シングルにはかなり辛く厳しい季節である。雪こそ降らないが、毎日ドンヨリとした陰鬱な空気が街を包み込み、冬時間も災いして夕方4時くらいにはすっかり暗くなってしまう。結構寒いので、夜が長いといえども外食や夜遊びにも出不精になりやすい。しかも、そこに畳み掛けるように“サンクスギビング+クリスマス”という家族持ち中心の特大イベントが続くので、気分はすっかり滅入りがち……というシングルは多いはずである。
少なくても、私は滅入る。基本的に単純な人間なので、悪天候やイベントの有無に簡単に左右されるからだ。でも、私のシングル友達一同も「シアトルの冬って本当に落ち込むよね」と毎年言っているので、みんなそれぞれ冬に対して思うところがあるのだろう。しかし、たかが天気や家族イベントごときで弱気になっていたら物事は好転しない。弱気はいけない。弱気になると、ろくなことがない。特大イベントが放つ、あの温もりにつられて、好きでもない男の家族からの「お呼ばれ」をうっかり受けてしまうという失敗だってしかねない。そういうセッティングに参加してしまった後に待ち受ける苦い後始末を経験済みのシングル諸君なら、「弱気がいかにマズイ結果を生むか」ということを、しっかりと思い出せるはずだ。だから、木枯らしに吹かれてちょっぴり淋しくなったとしても、特大イベントのお呼ばれだけは女友達か、好きな男からの招待だけを受けるように心掛けよう。特にクリスマスは、軽い気持ちで男友達の家に呼ばれて行ったら、ツリーの下に好きでもない男のお母様から自分への特製手作りプレゼントがカード付きで用意されていたり、ディナーの席上で将来設計についての意見を求められたりというバツの悪いケースが多発しやすいので、入念な注意を払いたい。
まあ、それはいいとして、少なくても私の周囲にいるシングルの友人達は、この季節を幸せな気分で乗り切るための打開策をそれぞれ生み出しているようだ。たとえば某有名IT会社でプロジェクト・マネージャーをしているケイティ(36歳)は、冬なら夏よりも忙しくないから内装に凝る時間がたっぷりあるなどと言って、グリーンウッドに小さな一軒家を購入した。もちろん私達全員が壁のペンキ塗りなどを手伝わされた訳だが、「どうせ、みんな暇なんだから、丁度いいイベントじゃない?」と、ケイティは大はしゃぎしている。また、旅行好きなフリー・デザイナーのステイシーは、「ディプレッシブな季節なら旅行も我慢できるから、今しかない!」と一大奮起して、UWが開催する社会人対象の夜間エクステンション・コース(なんと約3,000ドルもする)に応募し、この冬は新しい技術を取得するために毎晩クラスと宿題に追われて大忙しの日々を送っている。そうかと思えばPR会社に勤務し、モデルのようなルックスを持つエイミー(31歳)は、何を思ったか「冬になったから、私ベリー・ダンス始めることにした」と発言。現在は週に3日も夜のクラスに通い、激しく腰を振っているらしいが、「本格的な全身運動だから気持ちも体もスキッとするわよー! みんなも一緒にやらない?」と、冬のシアトル在住者とは思えないほどの爽快感を周囲に振りまいている。
普段から大人しいエイミーが、突然ベリー・ダンスという熱いダンスを習い始めたのも驚きだが、もっと驚かされたのは、先日の『Seattle Weekly』に“シアトルで指折りのクール・ガール”だと記事にまでされた人気者のジュディ(仮名・35歳)の行動だ。普段からモテるにもかかわらず、冬になった途端に突然ある出会いサイトのメンバーになり、今では毎週のように違う相手とコーヒー・デート(笑)を繰り返している。「みんなが家にこもって今後の展開なんかも真剣に考えたりする季節だからこそ、焦らずじっくりと相手を探せると思うのよ。それにもう“結構ナイス・ガイ”っていうのは嫌なの。“すっごいナイス・ガイ”を見つけたいの」というのが本人の談だが、これもまあかなり興味深い“冬越え策”だと思う。ジュディが“すっごいナイス・ガイ”を見つけられるかどうかは別として、あまりにもエンターテイニングな彼女の「今週のコーヒー・デート結果」を聞くためにガールズが集合する「ジュディを囲む夕べ」(単なる飲み会)が最近頻繁に開催され、私達の長い夜をかなり楽しませてくれるので、ジュディの奇行がほかのみんなもハッピーにしているのは間違いない。
私の冬の弱気打開策はと言えば、単純極まりないがあえて鬼のように仕事量を増やすことである。訳が分からなくなるくらい忙しくしていれば、天気やイベントにつられて落ち込む暇がないからだ。小学生でも考え付くような弱腰な逃げの手だが、これがなかなかうまく作用しているので私的にはよしとしている。しかも、サイクルというのは不思議なもので、なぜか忙しい時に限ってお誘いも増えるから、まさに一石二鳥なのだ。
通常なら誰も働きたくないと思うアメリカのホリデー・シーズン中に、フル稼働するという私の体制は非常に需要が高い。先日のサンクスギビング4連休も誰もが働きたくないという最中に、どうしてもこの期間中でないと困るという取材依頼が舞い込んだので喜び勇んでお受けした。内容はサンクスギビング期間にも特訓を受ける熱血スポーツ選手をミネソタ州の田舎街で徹底取材するという、ジムにだって1年に1度しか行かない運動嫌いの私には最低の仕事だった。しかも連休を返上して働くから通常よりギャラが高くなるのはカメラマンだけ(ライターは世の中に腐るほどいるからな)。はっきり言って、どんなライターでも断るようなカス仕事だが、連休だからこそ働くことを目的とした私にはもってこいの日程だった。
それなのに事情を知らない編集者が、私の境遇を気の毒に思ってか、「連休明けにその選手がNYで検査を受けるので、それも流れで取材してきてね」というプレゼントをくれたのだから、神様はやっぱりどこかにいるのだろう。確かにミネソタ州の田舎街にある小汚いホテルでサンクスギビング・デー当日を過ごした際には、「私の人生って何? 一体いつまでこんな生活が続くのよ?」などと、まだ若いカメラマンを相手に当たり散らしてワインの大瓶をひとりで開けた私だが、連休が終わる頃には、「わーい、次はNY! 都会、都会!」と浮き足立ち、その選手の取材もそこそこにNYでは大学時代の友達や同業者達を誘って毎晩朝方まで飲み明かすという大変充実した数日間を送らせていただいた。ちなみに今年のクリスマス期間中(12月20日から28日)も、誰もやりたくない仕事を胸を張って引き受けることが決まっている。たとえ業界の掃除夫だと同業者一同に笑われようとも、陰鬱なシアトルの冬をひとりで悶々と過ごすよりは忙しくしている方が健康的だ。こんな風に考えるのは世の中で私だけかも知れないが、つい弱気になって“ポリティカリー・インコレクト”なお呼ばれにノコノコ参加してしまうよりはずっといいと思っている。
何度も念を押すようで恐縮だが、本当にシアトルの冬は暗くて、重くて、寒くて陰鬱である。でもシングル諸君、天気や家族イベントごときで弱気になるなよ。ほかのシングルのみんなも毎日それぞれに頑張ってることを思い出しながら、この冬の間にさらなる英気を育み、春が到来するその日まで何とか前向きな気持ちをキープして乗り切ろう!
第14話 「好みの違いと常識の壁」
親しい女友達みんなが口を揃えて言うことのひとつに、「秋野はかなり変わった男が好きだから、私とは絶対にバッティングしなくて安心」というセンテンスがある。言い換えれば「こいつの男の好みは極端に変だから、何があっても同じ男を取り合う可能性がない最高の女友達」ということなので、別に褒め言葉でも何でもないのだが、確かに私はかなり長い間シングル生活を送っているが自分の女友達と同じ男を取り合った経験は一度もない。
どう変わっているのかと改めて聞かれると、自分ではそれほど変わっていると思わないので答えに困るのだが、他人から見ると私は「どう考えても、この男と付き合うにはリスクが多過ぎる」という、何かしら大きな問題を抱えたタイプの男性を好む傾向が強いようだ。こう書くと私が不倫を好む傾向にあると勘違いされるかも知れないが、それは違う。不倫はいただけない。リスクと言っても不倫や子持ちのバツイチ男ではなく、今までの経験から統計すると「世間の流れに相反するタイプ」、要するに「バッド・ボーイズ系」や「一匹狼系」の男が私の好みのようだ。もっと簡単に言えば、大企業勤務のビジネスマンや弁護士のように仕立ての良い高級スーツを着て、ベンツやBMWに乗っている人が一番苦手なタイプである。そういう人々のことを悪く言っているのではなく、私とは価値観が合わないだけなのだが。
たとえば大勢の女友達とベルタウンのバーか何かで飲んでいて、みんながあるひとりの男性客のことを密かに目配せしながら話題にする際に、私だけが「なんであんな男が素敵なのよー? あっちの人の方がずっといいじゃない」と発言して、その場をしらけさせることが多々ある。今までに何度、女友達から「あんた本当にどこかオカシイんじゃないの?」と言われたかなど、多過ぎて回数を数える気にもならない。人の好みはそう簡単に変えられるものではないし、逆に私の好みの違いこそが、大切な女友達との関係を円滑に保ってきた秘訣なのかも知れないと思うことさえある。
先日も、人の好みの違いを思い知らされる事件があった。仕事がらみのディナー・パーティーにどうしても出席しなければいけない状況が訪れたのだ。しかも同伴で出席のうえ、レストランで着席のパーティーで、招待客の中で日本人は私ひとり。最悪の事態である。以前のコラムでも書いたが、私は極力「同伴で」というパーティーには顔を出さないようにしているのだが、これに限ってはどうしても出席しなくてはマズい状況だった。
女友達を同伴したところで出席者から違う意味での注目を浴びるだけだろうし、そうかと言ってひとりで行くのも浮いてしまう。そこで私は、男友達の中で一番親しいブラッドを連れて行くことにした。落ち着きはないがオモシロイ奴なので、彼が一緒ならつまらないパーティーでも楽しめるだろうし、「ただ飯」だと聞けば喜んで参加するはずだ。早速、ブラッドに電話して誘ってみると、「しょーがねーなー、お前の頼みなら行ってやるか。その代わり礼は弾めよ。高いぜ」と言いつつ、すっかり行く気になっている。いつも通り口は極めて悪いが、そういう奴なのだから仕方がない。だから「じゃあ、日程が近づいたらまた連絡する」と言って電話を切った。しかし、そのことを女友達に伝えたら、みんなが「悪いことは言わないから、それだけはやめとけ」、「あいつを連れて行くなら最初から出席しない方がいい。常識がないと思われる」などと言われ、大反対されてしまった。
その理由はわからないでもない。ブラッドは、いい歳をしてまだ髪の毛をパンキッシュに立てて、黒いスライダーの皮ジャンを愛用し、4レターワードを使わずにセンテンスを構築することができないうえ、ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder・注意欠陥多動性障害)である。でもADHDを持つ大人にはとても楽しい人が多く、彼も確かに数え切れないほど問題はあるが超オモシロイので、私はいい友達だと思っているが、世間にはそれを「オモシロイ」とは思わない人の方が多いのだ。
愛すべき女友達から手厚いお叱りを受け、ブラッドを連れて行ったら彼の言動がパーティーで大問題になるだろうということは理解した。「じゃあ、どうしたらいいのよー!」と頭を抱えているときに、まるで私の部屋をモニターしていたかのように、ブラッドの親友のデイブが「ヘイ、元気? 今週は何してるの? みんなで飲みに行かない?」と電話を掛けてきたのだ。最高のタイミングである。
デイブは見た目こそ冴えないが、明るく真面目で有名企業に勤務し、真っ赤なBMWのコンパーチブルに乗り、出張の際の飛行機はいつもファースト・クラスという、まさに私の好みの対極に位置する男である。そして数少ない私の男友達の中で唯一、一般的に見て「ちゃんとしていると思われる男」だ。だから、「こんなことをお願いすると彼に借りを作るようで嫌だなあ」とは思いつつ、苦しい状況に負けて「あのさ、今週の木曜日、私をエスコートして○○のディナー・パーティーに一緒に行ってくれない? ブラッドを連れて行くわけにはいかないし」と正直に言ってみた。するとデイブはふたつ返事で「そういうパーティーじゃ、ブラッドはマズいよな(笑)。光栄だよ。もちろん行く。何時に君をピックアップすればいい?」と言ってくれるではないか。話が早いのはいいことだ。そういうわけで、私はデイブとパーティーに出席することにした。それを聞いた女友達一同も、「あー、良かった、良かった。デイブならバッチリよ」と、ホッとした様子であった。
しかし、デイブと一緒にパーティーに出席してみると、事態が予想外の方向へ展開した。出席者のほぼ全員が、冴えないデイブのことをなぜか極上の男のように高く評価し、ディナーが終わり次第そそくさと退散しようと打ち合わせていたのに、「こんなカッコイイ彼がいるのをなぜ今まで隠していたのか」、「彼とはどこで知り合ったのか」、「どのくらい付き合っているのか」など、どんなに私が「何度も言いますけど、彼は友達です」と言ってもデイブを中心に話が展開してしまう。確かにデイブは良い奴で、それゆえ友達なのだが、なぜ大勢の人が彼を「かっこいい」と言うのか私にはわからない。逆に彼ならば周囲に溶け込んでしまって誰も気に留めないと思ったから連れて来たのに、そんな私の様子にはお構いなしといった感じで、デザートを食べ終わっても退散できないほど宴は盛り上がり、私にとっては非常にアンコンフォタブルな状況になってしまった。他人の好みというのは本当にわからないものである。
そんな状況下、私のケータイが鳴った。ブラッドだった。とっさに「ああ、ちょうど良かった。今デイブと一緒なんだけど妙な流れになっているから、すぐ電話を掛け直すよ。この後3人で飲もう」と言うと、ブラッドは「さてはお前、結局デイブとディナーに行ったんだな! 俺が食うはずのタダ飯をデイブが食ったのか? デイブ出せ! 奴のせいで飯を食い損なった」と怒鳴っている。そう、私はブラッドにキャンセルの電話を入れるのをすっかり忘れていたのである。「しまった!」と思った時には既に遅すぎた。ブラッドは、いつでもその場の状況をわざわざややこしくしてしまう。だからこそ、このパーティーに連れて来なかったのに、「ここにだけは絶対に来ないでよ!」と、私が言い終わる間もなく、「今から、俺もそっちへ行くからな」と言い残して一方的に電話を切り、10分もしないうちに本当に会場に来てしまったのだ。信じられないほどオモシロイ奴である。でも、残念ながら世間はそれをオモシロがってはくれない。
私の名前を大声で連呼しながら突然登場したブラッドに対して、出席者一同が非常に困惑した様子を見せていたのは言うまでもない。その恐ろしく冷めた反応を見たとき、「女友達の助言はいつでも正しい」と私は改めて認識した。ああ、愛すべき女友達。しかし時すでに遅し。
ブラッドが乱入して来たときはパーティーがほぼ終了していたこともあり、ナイスなデイブはそれほど驚いた様子も見せず、「やあ、ブラッド。ちょうど良かった。これから一緒に飲みに行こうぜ!」とスマートに笑顔で対応し、ギャーギャー訳のわからないことをわめき散らしているブラッドを連れ、私たちは3人揃って素早くその会場を後にした。しかし、この乱入のせいで結局は何のために私はわざわざデイブを同伴して来たのかわからなくなってしまった。
その後の3人での飲み会は結果としてとても楽しかったので(もちろん私の行動はさんざんなじられたが)、「一瞬やばいかと思ったけど、めでたし、めでたし!」と思ってホッとしていた。しかし、後日、出席者のひとりから私たちが退場した後、「あっちが彼女の本当の彼なのかしら?」、「いや、いくら何でも、それはないはずよ」、「でも普通パーティー会場にまで迎えに来ないわよね」、「どうしてあんな素敵な人と来たのに、あの妙な……」と、私の男友達の話題で持ち切りになったと知って、私は再びアンコンフォタブルな状況に陥るはめになった。
なぜブラッドはだめで、デイブならいいのか? こんな事件が起こらずとも、私だってファースト・クラスにBMWの方が、パンクでADHDよりも常識的に考えて受けがいいことくらいわかるが、そんなにアカラサマな反応をしなくても……と思ってしまう。両者とも私の愛すべき数少ない男友達なのだから。少なくとも私を取り巻く狭い世界では、全く性格も好みも違う異性3人が仲良くやっているのだから、世の中から社会性や協調性という「既成概念」や各国の「常識」という壁がなくなれば、もっと楽に生きられるはずだ(そうなれば戦争も起こらないかも知れないと極端に短縮して物事を考えるバカは私だけだろうが)。でも、たとえ常識の壁はなくなっても、各人の好みの差異がなくなると女友達と男を取り合うという別の争いが起こるだろうから、「好み」だけはそれぞれが違うものを持ち続けた方がいいかも知れない。
第15話 「ゴッドマザーの依頼」
私自身がシングルなので、私の周囲には30歳代で結婚していない女友達が結構たくさんいる。だからと言って「結婚していない私の女友達」の全員に彼がいないわけではない。このうちの半分は数年一緒に住んでいるパートナーがいるし、なかには10年も同じ彼と一緒に住んでいる友人もいる。
でも、そのうちの誰もが「彼と結婚はしない」と言い続けているから不思議である。文化や習慣や法律が日本とは異なるアメリカだからかも知れないが、「結婚なんて紙の上の問題だから」とか、「結婚していないから、いつまでも恋人としての緊張感が損なわれなくていい」とか、「離婚するのが嫌だから」などと、それぞれ理由は異なるが両者同意のもとで「結婚はしない」と決めているカップルが案外多い。それではふたりの関係がうまくいってないのかと思うと、これがとても仲良しなのだから、他人の関係や他人の価値観は本当に興味深いものである。
先日も、日本人である私には驚いてしまう事件が起きた。アメリカ州立の某大学在学中に数年間一緒に暮らして以来の悪友であるフランス人のミッシェルから、いきなり早朝に国際電話が掛かってきたのだ。
「Good morning! What’s up, girl? どう、元気? 新しいボーイフレンドは見つかった?」と、受話器を思わず耳から遠ざけてしまうほど元気な彼女の声に叩き起こされた私は、「元気だけど何時だと思ってんのよ。何か事件でもあったわけ?」と不機嫌な対応で電話に出た。すると彼女は、「そうなのよ! ねえ、何だと思う? 実は内緒にしていたニュースを直接伝えたかったからメールじゃなくて電話したの」と、弾んでいる。「こんな早朝から何言ってんのよ。まさか結婚するわけじゃないでしょ?」とブツクサつぶやく私に、彼女はいきなり、「ううん、結婚はしないけど、私ママになるの! それで折り入って相談したいことがあるから、ちょっとフランスに来てくれないかなと思って……」と言うではないか。もちろん私は衝撃ですっかり目が覚めた。彼女と知り合ってだいぶ経つが、ずっと「絶対に結婚はしない。でも35歳までに子供だけは産む」と妙なことを言い続けていた。何でも、結婚というシステムに彼女は同意できないらしい。しかし、元来の子供好きだ。だからと言って、まさか本当にシングル・マザーになるとは思っていなかったので私は本当に驚いてしまったのだ。
さらに驚いたのは、その状況である。子供の父親は私も長年知っているミッシェルのボーイフレンド、ミゲル君。アメリカ人の彼はアメリカ在住。10年近く住んだアメリカに嫌気がさしてフランスに帰国した彼女と、今でもアメリカ在住の彼は1年に約3カ月をどちらかの国で一緒に過ごすという遠距離恋愛をしているのだが、「結婚はしたくないが子供が欲しい」という彼女の長年の願いが叶い、晴れてご懐妊したという。「ちょっと、ミゲルもあんたも何を考えてんのよ! 子供はどうなるの? あなたの家族だって反対してるでしょ?」と、慌てる私にミッシェルは、「彼は結婚しようと言ったけど、私は絶対にしないわ。私ひとりでも子供ときちんと生きていけるし、家族も賛成しているから問題ないの。それに彼とはこれからも付き合っていくし、出産にも立ち会う予定よ」と言う。ほかの人はどうか知らないが、この話を聞いて少なくとも私はとっても混乱してしまった。
「そんな簡単に行かないでしょ? この先、一体どうするつもりなの?」と、食らいつく私に彼女は淡々と、「フランスではそれほど珍しいことではないし、独身の親には国から少し援助も出るから経済的にも心配いらないわ。それに私のママも叔父2人もみんな子供がいるけど結婚してないし、みんな幸せよ」と言ってラチがあかない。私にはシングル・マザーとして働きながら子供を育てていく自信などまったくないが、彼女は自信満々だ。
「とにかく、何とかしてすぐそっちに行くから、よく考えるのよ!」と、そういう訳で私は大急ぎでフランスに飛んだ。ちょうど仕事が入っていなかったうえに航空会社のマイレージが溜まっていたことにも助けられたが(笑)、最愛の悪友の一大事である。「いきなりシングル・マザーになるなんて、友人としてどうやって支えてあげたらいいのか……」と、いろいろ考えながら乗り継ぎの末に南フランスの田舎の空港に到着した。しかし空港に私を迎えに来たミッシェルを見て、私は驚愕した。彼女はすでにほぼ妊娠8ヵ月という超妊婦だったのだ。
「ちょっと、なんでこんなにお腹が大きいのよ! 折り入って相談したいなんて言ったくせに、もう産むしかないじゃないの? どうして今までずっと私に黙っていたのよー!」と、ギャーギャー叫ぶ私を一笑して彼女は、「あんたが何言うかわかっていたから、安定期まで妊娠していることを黙ってたのよ。相談したいのは産むかどうかではないわ。とりあえず家についてから話すから」と言い、私を引っ張って彼女の実家へ連れて行った。
彼女の実家に到着すると、ご丁寧に一家勢揃いでの熱烈なお出迎えを受けた。ミッシェルと同居した期間が長かったので彼女の家族全員が私のことをすでに何でも知っていて、私がはるばるアメリカから彼女に会いに飛んで来たことをとても喜んでくれた。しかも、私の大好物のフォアグラや、ダックにプラム、年代物の赤ワインと地元の名産物を揃えた素晴らしい宴の席まで用意されていたので、私は相槌以外にはほとんど何も言えないまま宴を満喫し、しまいには酔いつぶれて寝てしまうという、一体何をしにフランスまで来たのかまったくわからない状態となってしまった。
でも、ミッシェルの家族と数日を一緒に過ごすうちに、家族全員が「ミッシェルがシングル・マザーになると決めたこと」を心から祝福していることが理解できた。心配性の私には、子供の父親が結婚を申し込んでいるにもかかわらず結婚しないという意志がなかなか理解できなかったのだが、「人それぞれ幸せの価値観は違う」と笑顔で繰り返す家族の言葉に、いくら海外に住んでいても文化の異なる人達と交流するたびに新しい発見や学ぶことがあるものだと改めて考え直した私であった。本当に人生日々発見である。
明日はアメリカに戻るという夜の最後のフォアグラ、いや晩餐でのこと。宴もたけなわとなり、私はまたしてもかなり酔っ払っていた。これで本場のフォアグラを食べるのも最後かもしれないと大切に味わっている私に、ミッシェルのお母さんが「ところで、ミッシェルの親友であるあなたにお願いしたいことがあるのよ」と、話し掛けてきた。「ウイ、なんですかあ?」と、浮かれながら調子良く聞き返すと、お母さんはこう言ったのだ。「ミッシェルはあなたのことを心から信頼しているし、私達家族もあなたがどんな人なのかよくわかったわ。だから、あなたにミッシェルの生まれて来る子供のゴッドマザーになってもらいたいの」
それを聞いた私が固まったことは言うまでもない。名物のフォアグラを食べさせるために私をアメリカから呼んだわけではなく、折り入っての相談とはこのことだったのだ。これは大変名誉なことである。だがゴッドマザーとは、万が一ミッシェルがこの世からいなくなった場合、彼女に代わって子供の面倒を見る人のことである。ミッシェルが生きていても、その子供が洗礼を受ける日の同席はもちろん、誕生日やクリスマスや入学式や卒業式やエンゲージや結婚式にいつもお祝いを包み、子供の成長を第二の母として見守り祝福する人なのだ。
しかし、自分の子供すらいない私にゴッドマザーなどという大役が務まるのだろうか? 彼女は大事な友人なので大役そのものに異議はないが、現実的に言って私のような貧乏ライターが、悪友の子供が成人するまでの膨大な年月の間にしばし海外へ出掛け、途切れることなくギフトや祝儀を包み続けることが経済的に可能なのだろうか? しかも、私はクリスチャンでもないのだ。
とんでもなく重要な責任を負う事態である。ああ、どうしよう? 何て答えsればいいのだろう? あたふたしながら、とりあえず「大変名誉なことですが、突然のことなのでこの場ですぐにお受けしていいものなのかどうか……。私はクリスチャンではないので、いろいろとわからない部分もありますし、だいたいクリスチャンではない私がゴッドマザーっていうのも……」と、お茶を濁すというか、まったく答えになっていない答えを返してしまった。
するとお母さんは、「そんなことは大丈夫。形式上のことだから、どうだっていいの。大切なのは誰がなるかということだから、そんな大袈裟に考えなくていいのよ」と、いとも軽くおっしゃるではないか。「いやー、形式上のことだなんて、それは違うでしょう、お母さん。ハッハッハー」という感じでとりあえず笑い飛ばし、とにかく子供が生まれるまでに決めてくれという結論に至ったので、そのまま宴を楽しんで幕を閉じた。
そうこうしてアメリカに戻って約2週間が経ったが、私はまだ返事ができずにいる。そして彼女の子供が誕生する予定日は刻々と近づいている。果たして私は自分の子供がいないまま、悪友のゴッドマザーになるのであろうか?
第16話 「アメリカの歯科請求おそるべし」
第12話「アメリカの自動車保険おそるべし」を掲載した後、大勢の読者の方から「私も同様の経験をした。がんばって!」、「この保険会社に電話してみて!」という励ましのメールをいただいた(各人にお返事が書けなくてごめんなさい! でもとっても感謝しています)。そして読者の方に紹介していただいた保険会社の中から某社と新規契約をし、数ヵ月後、見事に「以前の倍額保険金額」の地獄から脱出を図り、トラブル以前より$50増しという保険料に落ち着くことができた。すべて読者の皆様の温かい応援のおかげだと感謝の日々を送っていた私だが、先日またもや大変な事件が起きてしまった。歯がものすごく痛み出したのである。
その歯痛は何の前触れもなく突然やって来た。幼少の頃から「あなたの歯は弱いから気をつけてくださいね」と近所の歯医者さんに注意されていた私は、歯医者の値段が高いことで有名なアメリカに住み始めてからというもの、毎日歯医者さん推薦の電動歯ブラシを使用して歯を磨き、歯医者さん推薦のフロスを使ってフロスティングをし、さらにバクテリアを殺すため、マズい薬で口を30秒ゆすぐという3点セットのケアを行い、そのうえ半年ごとに歯医者に$100も支払って歯垢落としのクリーニングにも通っていた。それなのに突然、歯が痛くなってしまったのだ。だから「私って、何でこんなについていないんだろう」と自分の歯質を非常に恨んだが、恨んだところで歯痛は止まなかった。
ちょうど半年検診の時期だったので、痛み止めの薬を飲みながら速攻で歯医者に予約を入れ、数日後に歯医者に行った。すると歯科医は、「うーん、この状態はひどいですねえ。前回のクリーニングの際にも、痛みがなくても早めに治療をした方がいいと申し上げましたが、やはりあの時に治療をしておくべきでしたね。治療を要する歯が隣接して4本もあります。すぐに治療しましょう」と言うではないか。「ちょっと待ってください! 確かに右上全体が痛むのですが、本当に4本を全部治さなければいけないんでしょうか? 治療費も高いでしょう?」と、真剣にビビると、「このように隣接した歯がすべて何かしらの問題がある場合は、一度に治療した方が結果的には安いんです。それにあなたが加入している歯科保険会社と提携していますから、ほかで治療するよりは安いはずですよ」と説明された。
そうは言われても歯科保険から補助される金額は治療前の時点では「あくまでも推定金額」であり、実際の補助額は正式請求後にしかわからない。だから、ものすごく迷ったのだが、その数週間後に州外への長期取材が予定されていたうえに、一刻も早く痛みから逃れたかった私は迷った挙句、「やっぱり痛くて仕方がないので、悪い歯を全部治療してください」と、治療に踏み切ったのだ。
出張中に痛んだら大変なので、出張日に間に合うようにキツキツの日程で予約を入れ、まず歯科神経の専門医の下で2本の歯の神経を抜いた(2日間の合計治療時間約5時間)。その後、自分の歯科医のもとで神経を抜いた2本の歯に隣接する別の2本の歯を治療して、4本の歯にクラウン(半永久的にかぶせる歯の冠)の型を取り、一時的なクラウンを装着。そして出張日前日に歯医者に戻り、でき上がってきた自分の歯と同色のクラウンをかぶせて(3日間の合計治療時間約6時間半)、無事4本の歯の治療が終了した。
歯の痛みもまったくなくなり、見た目も美しくなった歯を見せながら満面の笑みで歯科医の受け付けカウンターに立った私の顔から笑顔が消えたのは、その請求金額の合計を見た瞬間である。歯科神経専門医からの請求額が$2,960、自分の歯医者からの請求額が$3,764.50、つまり合計でなんと$6,724.50という金額だったのだ! 「目玉が飛び出る」とは、まさにこのことである。私は両手で何度も目をこすり、ゼロの数がひとつ間違っていないか100回くらい確かめた。でも、何度見ても請求書の合計金額欄には電飾でも施したかのように「$6,724.50」という金額が輝いている。長い間アメリカに住んでいるが、そのとき私は思わず日本語で、「信じらんない! こんな私が約7千ドルも払えるわけないじゃないのぉぉぉー!」と人目もはばからず叫んでしまった。
あまりの金額の多さに狼狽し、自分の経済状況を説明しているうちに年甲斐もなく涙まで流してしまった私を見て、受け付け係のお姉さんは、「そんなに心配しないで。保険会社が一部を負担してくれるし、自己負担金額に関しては分割支払いのシステムもあるから。そんなに苦しいなら、通常は現時点で予想される自己負担額を今すぐ支払ってもらうのだけれど、あなたには特別に保険会社がうちに支払った後で自己負担額を請求してあげるから」と、言いながら慰めてくれたが、だからと言って合計金額欄に書かれた数字は減少しない。今までのアメリカ生活で、このとき以上に「34歳にもなって私には歯医者の支払い能力さえない」と落胆したことはなかったが、働き続けなければ生活できないので、落胆した気持ちを抱えたまま翌日からの長期出張に出発した。保険会社からの負担金額料にすべての望みをかけて……。
そして、その日はやって来た。歯医者からの請求書が届いたのだ。気を引き締める時に、田舎のおばあちゃんがいつも「フンドシの紐を引き締め直して気合いを入れるんだよ」と言っていたが、まさにこういう時に使う言葉なのだろう。腹の底に力を込めて、私は請求書の封を切った。そして、その瞬間にまたもや熱い涙が一筋、私の頬をツーっと静かに流れ落ちていったのである。
保険会社から歯医者に支払われた金額はたったの$1293.60だった。つまり、私の自己負担額は締めて$5,430.90である。一体、私は何のために毎月の歯科保険料を支払っていたのだろうか? それよりも、今まで私は一体何のために加齢にムチを打ちながらも、ほかのライターさんが嫌がって笑い飛ばす「業界のカス仕事」を引き受けてまでアメリカで仕事を続けてきたのだろうか? もうアメリカで仕事することは諦めて日本に帰り、どこかの編集プロダクションに就職して保険に再加入した方がいいのではないか? 日本ならこんなバカげた請求額はあり得ないし、英語が話せるライターってことで収入だって今より少しは上がるかも知れない。
そんなさまざまな思いが頭の中を駆け巡り、自分の人生の選択を「思いっ切り間違ってしまったらしい」と、ひとり泣きながら自分の頭を作業机に何度もゴンゴンとぶつけて悔やんだことは言うまでもない。保険会社に何度も電話して「お願いだから、もっと支払ってください! 私は無力ながらも一生懸命生活しているんです!」と懇願してもみたのだが、もともと非常に安い保険に加入している私の状況下では、すべて無駄に終わった。自身のアナーキー型の性質から普段は有名企業各社を「貧乏人の敵だ」などと言って敬遠しているくせに、この時ほど「ああ、私もマイクロソフトの正社員になりたい!」と、心の底から願ったことはなかった(注:事実は知らないが、社員になると治療費全額負担の保険がいただけるとの噂)。でも、たとえ天地がひっくり返ったとしてもEメールとワード以外のソフトを使用できない私は絶対にマイクロソフト社の社員にはなれないし、マイクロソフト社も私みたいな原始人を雇用する必要などまったくないので、そんなことを願っても仕方がない。だから、その時の私には机に頭をゴンゴンぶつけるしか術がなかったのである。
歯医者の支払いとアメリカ生活の理不尽さから逃れるために日本に永久帰国してしまおうかとも真剣に考えたのだが、周囲の理性ある友人達が、「いくらなんでも、それだけは止めておけ。一生、アメリカのブラックリストに載ってしまう」、「今まで頑張って来たのだから、私の定期預金を崩して、その金を貸してやる」などと口を揃えて応援してくれた。そう言われても、それぞれが大変な局面を迎えているシングルの大切な友人達から金を借りるわけにはいかない。金の切れ目は良縁の切れ目である。
友人達にそこまで応援されて、私も腹をくくった。日本にいる親や親戚を心配させることだけは避けたいので、どんなに困っても金銭に関する頼みごとだけはしないと決めている海外在住独身女の気合いは持ち続けなければならない。そこで、「もう一生、結婚しないかも知れないから、いつかシアトルに一軒家を自力で購入するための頭金に」と思って、実はひとり密かに過去4年間に渡り、毎月$100ずつ積み立てていた全財産の$4,800と端数の$30.90を支払いに一括投入し、残りの$600は「すいませんが、分割支払いで……」と、お願いして支払い手続きを済ませたのである。
こうして私が過去4年間に渡ってアメリカで密かに育んできた「一軒家願望」は惜しくも破り去り、なけなしの貯金も見事にゼロに戻ってしまった。でも、夢を抱きながらコツコツ貯めていた貯金のおかげで、アメリカのクレジット・カード会社による恐怖のブラックリストに自分の名前が掲載されることもなく、大切な友人から金を借りることもなく、私の4本の歯は美しく治療され、分割払いの残金も$500を残すばかりとなった。「めでたし、めでたし」と、言いたいところだが、正直言ってこれからの生活は本気で危ぶまれる。5年前に$1,500で購入した愛車が壊れでもした日には一巻の終わりだ。しかし、そうかと言って、こんな私を救ってくれる王子様が白馬に乗って突如私の前に現れることはまずあり得ないと思われるので、たとえ「業界のカス仕事」と笑われようが、ちょうだいした仕事に日々精を尽くし、非常に早めに「おいしい仕事」にあり付ける日を前向きな気持ちで待ち望んでいる次第である。
編集部より:シアトルで格安のいい歯医者を知っている方がいましたら、今後に備えてぜひ歯質の弱い秋野未知に歯科医情報を教えてあげてください。
第17話 「ナンパにはやっぱり落とし穴」
シアトルにもようやく春がやって来た。毎年のことだが、夏時間になると夜になってもなかなか日が暮れず、仕事の後でも思いっきり外で遊べるので、突然周囲が色めき出す。「これだけ昼間が長いとデートでもしていないと間が持たない」「みんなが外で楽しんでいるのに一緒に過ごす相手がいないのは耐えられない」などと言い、シアトルで働く私の独身女友達(ほとんどが30歳代)はみんな「今年こそ、私は頑張るわ!」と、気合いを入れている。
そこで浮上するのが「どうやって素敵な男性と出会うのか?」という問題だ。でも、この答えが簡単にわかるなら、私を含めた仲間の誰もが現在独身ではないはずである(笑)。
先日も数人の独身女達で集って食事をしたのだが、「ねえ、もう春よ。素敵な人がどこかで私に声を掛けてくれないかしら?」と、ため息交じりに看護婦B子が切り出した。もちろん、みんな彼女の気持ちには同意したが、「でも、この年齢になると、声を掛けてきた相手をちょっとイイなと思っても、そう簡単にデートの約束はできないよね」「うん、ナンパしてくる男はやっぱり信用できない」「自分と付き合っても他の女に同じことしそう」などと、「ナンパをするような男はいただけない」という方向で話が展開していった。しかしB子は、「でも、たまたま本当に自分を見初めてくれる人がいるかも知れないじゃない!?」と食い下がり、「果たしてナンパで相手のことがわかるのか?」についての論議が始まった。
そんな中、優秀な公認会計士で超美人のC子(34歳)が、「それ、まさに私のケースよ」と、ボソッと発言した。「あれ、C子? あの彼との出会いってナンパだったの?」と聞くと、「そう。しかも、もう終わったわよ」と言うではないか。C子の彼はかなり素敵な男だったはずだ。「みんなにも同じ失敗をして欲しくないから話すけど……」と言いながらC子が話してくれた内容はこうである。
彼女がダン(仮名・39歳)と出会ったのはベルタウンのスタバだった。この場所自体が既にナンパ勃発地なので(笑)、C子が女友達に彼との出会いの詳細を今まで隠していたのもうなずける。とにかく、そこでタイムスを読んでいた彼女にダンが突然声を掛けて来た。イタリア製のスーツを着たスマートな感じの男性だったし、貿易の仕事で日本にも何度も行っているという彼の話が楽しかったので、その場で長らくおしゃべりして最後に電話番号を交換したそうだ。
もちろん、出会った翌日に彼から電話が掛かって来て、早速ディナーに誘われた。場所はウォーターフロント。高級レストランである。高価なワインをボトルで頼み、当然のように彼がすべて支払ってくれた。しかも、その翌日も別の高級レストラン、そのまた翌日も別の高級レストランへと誘われ、「これでは、まるでシュガー・ダディ?」と思ってしまうほどゴージャスなデートを続けたそうだ。ふたり共お酒が好きで、バーやパーティーにもよく一緒に出掛けた。頭もいいし、仕事もできるし、金銭的にも成功を収めているし、友人が多くて社交家だし、日本文化への理解も深い彼。かなり彼に惹かれていたC子だったが、それでも、「まだ彼をよく知らないのだから」と考えて慎重な行動をとっていたらしい(つまり、彼の家には行かない、自分の家にも呼ばないなどということ)。
しかし、そんなある日、彼から「実はヘッドハンターから声が掛かったので急に会社を移ることになった。サンディエゴへ引っ越すけれど必ず会いに来て欲しい」と言われたのだ。そう言われても、C子は「コミットメントもしていないのに、ノコノコと彼に会いに行っていいものか?」と悩んだ。だが、そのC子の元に彼からファースト・クラスの往復航空券が送られて来たのだ。彼が引っ越して残念に思っていたし、「そこまで押してくれるならば」と、休暇を取ってC子はサンディエゴに向かったのである。
もちろん彼が空港へ迎えに来てくれて、彼のBMWのコンバーチブルに乗り込み、彼の住居に到着した。するとそこは美しいビーチ沿いに建つ高級コンドで、ジムやスパはもちろん、海を見ながら入れる住民専用の屋外プールまで付いていた。それから約1週間、C子が夢のような生活を送ったのは言うまでもない。まず、朝起きると彼はすでに仕事に出ており、ダイニングには朝食とラブレターが用意されている。ブラッディー・マリーを飲みながら階下のプールでくつろぎ、昼になると彼が会社から一旦戻って来て、ふたりで高級レストランへランチに出掛け、映画館かショッピング・センターへ彼女を車で送ると、また彼は会社へ戻り、夕方彼女をピックアップして、夜はまたレストランや観劇に出掛ける……という、映画「プリティー・ウーマン」(古いな、私も)のような生活だったらしい。
「ここまで自分を大切にしてくれるならば、真剣に将来のことを話し合ってみようかな」と、C子は考えた。そして、明日で楽しかった休暇も終わってしまうという夜、外出先からふたりで彼のコンドに戻り、ワイン片手に音楽を聴きながらリラックスしたひとときを過ごした。「そろそろ、今後のことを切り出してみようかしら」と、C子が思った途端、彼がゴソゴソと何かを取り出そうとしている様子が目に入った。「えっ、まさかエンゲージ・リング? ああ、どうしよう……」と、C子は一瞬にして期待に胸を膨らませた。だが、C子のその期待は、無残にも予想をはるかに超えるショックと置き換えられたのだ。
彼がゴソゴソと取り出したものは指輪ではなく、なんとコカインだった。長年アメリカに住んでいるC子は、「金持ちの若手エリートの一部が様々なドラッグを常習していて問題になっている」という話をもちろん聞いたことはあったが、まさか彼がそのひとりだとは考えたことすらなかった。しかも、動転している彼女に向かって、彼は、「どう、C子も一緒にやらないか? そんなに驚くことはないよ。こんなことは僕ら、いつもやってるし、別に何でもないことだからさ」と、まるで、それを得意がっている少年のような無邪気な表情を浮べながら笑顔で言うではないか。「冗談じゃないわよ! あんた、ただの金持ちのバカじゃないの!」C子はそう言い放ち、彼の美しい頬を思いっ切り引っ叩いた。
「とにかく、すぐに荷物をまとめて逃げるようにシアトルに帰って来て、それっきりよ。その後、彼からも一度も連絡は来ないし、引っ越してくれてよかったと思っているわ。でも、あれ以来なんだか怖くて、素敵な人にナンパされても二度と電話番号を教えないことにしたの」と、C子。この話を聞いて、数分前まで「誰か素敵な人に突然、声を掛けてもらいたい!」と叫んでいたB子は、すかさず前言を撤回した。そして一同は揃って頭を抱えながら、「こんな話を聞いた後に、私たちはこの春、一体どうやって誰かと出会えばいいのよぉぉぉぉぉ!」と口々に騒ぎまくり、ハッピー・アワーが終了する3分前にひとり2杯ずつの特製マティーニをオーダーして、その夜は閉店まで飲み倒したのである。あぁ、本当にどうしたら私達は素敵な男性に巡り会えるのかしら?
第18話 「サイキックを信じる女達」
今から数年前のことになるが、私が当時一緒に暮らしていた男は、まさに“絵に描いたような”ヒッピーなアメリカ人だった。夜遅くまで髪を振り乱して働いていた私とは異なり、彼は毎日のんびりと抽象画を描き、鳥のエサのようなグラノラと無農薬野菜を食べ、風邪を引いてもヨガに通ってハーブで治し、酒を一滴も飲まずに“グレイトフル・デッド”(笑)を聴くような人だったので、他人の「気」や「オーラ」を読み取れるようなヒーリング系の友人を非常に多く持っていた。その彼が、私の誕生日に「サイキック・リーディング」をプレゼントしてくれたのである。
正直言って当時の私はそんな理解し難いプレゼントよりも、もっと単純なものが欲しかった。誕生日くらいは普段行けないような高級レストランで食事をしたり、彼がいつも近所で勝手に摘んでくる野花ではなく、花屋で購買した豪華なバラの花束をもらったりしたかったのだ。でも、そんな低俗で浅はかな私に向かって、彼が「世の中には目に見えないことがたくさんある。特別な能力がないのにあると言う人も確かに多いけれど、この彼女(サイキック)の力は本当にすごいんだよ」とあまり熱心に語るので、「まあ、これもひとつの経験かも」と、疑心暗鬼なまま渋々とそのサイキックに会いに行ったのだ。「他人の好意を邪険にしてはならぬ」程度の軽い気持ちで。
でも、その1時間半後(セッションは1時間)、私はあまりの驚きによってアホのように大きく口を開けたまま帰宅した。「どうだったあ?」と嬉しそうに尋ねる彼に、「何で他人が私のことをあんなに知ってるわけ? あんた先に会って私のこと全部彼女に言ったでしょー?」と大騒ぎしたのだが、「神に誓って絶対に言ってない!」と言い切るので、余計に私は混乱してしまった。
その驚くべきサイキックとのセッションはこうだった。私が名前と誕生日以外、まだ何も自分のことを話していないのに、タロットを片手に一方的に私の職種、仕事内容、彼とのプライベートな問題、日本の両親の状況などを言い当て(しかも誰にも言っていないことも含めて)、そのうえ私の仕事の今後の展開などを呆然としている私に向かって20分くらい早口で話し続けた。そして突然「さて、今日あなたが私に聞きたいことは何かしら?」と涼しい顔で聞いたのだ。そこまでの内容を聞いて驚愕しているところに突然自分に振られた私は、「あ……、あの……私はいつか幸せになれるんでしょうか?」と、今時の小学生でもしないようなマヌケな質問をしてしまった。
するとサイキックは目をつぶり、「うーん、さっきも少し言ったけど、あなたは仕事で頻繁に他州へ行くようになって……あ、ちょっと待って。アメリカ以外の国、カナダとかヨーロッパにも行くのも見えるわね。とにかく飛行機に乗って飛び回わるような忙しい状態になるから、今のうちから体を整えないとダメよ。でも、あなたがやりたいと願っている内容の仕事が自然に来るようになるから幸せになる。だけど残念ながらお金はついて来ないわね(笑)。やっと貯金ができても、まさかと思うような出費が続くからお金持ちにはなれないけど(注:過去コラム第12話&第16話参照)、生活はできるわよ」と言ったのだ。それを聞いて私は「仕事がうまく行くのは嬉しいけど、やっぱり私の人生は仕事だけなのか」と不安になった。すると、その様子を察したのか「それから、今の彼は街を離れるから別れることになるけど、その後も親友関係がずっと続く。その後、こういうルックスでこういう感じの人とこういう状況で出会うので……(注:個人的な理由により具体例は割愛)」などと、すごいスピードで彼女は話し続けた末、最後にセッションを録音したテープをくれた。そのテープがなければ、現場でパニック状態に陥った私が覚えていた話は「その後、こういう人と出会う」という部分のみだったに違いない(笑)。とにかく、私は初めてのサイキック経験ですっかりボーッとなってしまったのだ。
そして、それから約1年が経つと、驚いたことに本当に他州や海外へ出張しなければならない仕事が続けて来るようになったり、当時の彼が他州へ引っ越すことになって私が彼に付いて行かない決断をしたり、その後しばらくしてサイキックが言った状況下で新しい男と出会ったりと、基本的に彼女の予言通りの結果となってしまった。サイキックに会った当初は何だか妙に恥ずかしくて彼と親友にしかその話をしていなかったのだが、結果的にものすごく当たったので飲んだ席での笑い話として周囲の人々にそのサイキックの話をするようになった。すると、どうだろう。私の友人だけでも未婚既婚にこだわらず、この数年間で10人以上が彼女に会いに行き、それぞれが「ひえー、信じられない!」という経験をしたのである(サイキックが当たったということ)。
なかには、「あなたは今どうしても信じたくないようだけれど、その男は二股かけているから絶対に別れた方がいい」と言われて、周囲の友人全員がサイキックに同意しているにもかかわらず激怒してしまう奴がいたり(注:後日になって男が二股かけていた現場を目撃して別れた)、「こんな仕事に就くと言われたけど、当てもないしピンとこないわ」と言っていた奴が、突然降ってきた仕事に転職したら半年後にサイキックが言った通りに仕事の内容が変わったり、「残念ながら離婚するけど大きなお金が入るから生活の心配はいらない」と言われて数年来悩んだ末に離婚を決意したら「2ベッドルームの1軒家が現金で3軒購入できるような金額」を手にした奴とか、とんでもない話が続き、私の周囲(注:十数人しかもシアトルのみ)では大変な騒ぎになった。
でも、この話をするたびに周囲の人々がそのサイキックに会いたいと言うので、「これではまるでエージェント」だと思い始めた私は、いくら酔っ払ってもその話をするのを控えていたのだが、先日、友人R子が落ち込んでいるのを慰める飲み会の席で、「わかるよ、その気持ち。私だって情けないけどあの時サイキックに会っていなければ今頃もう日本に帰国してたかも知れないもん」とポロッと言ってしまった。すると、その席にいた人みんなが「何それ? 私も会ってみたい!」と言い出し、日本人とアメリカ人の合計5人が2週間以内に順次それぞれアポイントを取ってしまったのだ。
たとえ人種が異なっても、独身女達はみんな「他人に将来を見てもらうなんて確かにバカげているかも知れないけど、やっぱり今後の仕事や結婚のことを一度は聞いてみたい」という不安材料を持っているのだと思う。だからこそ、その場に居合わせた全員がサイキックに会いに行ったのだろう。でも、結果として各人が非常にポジティブなセッションを体験したし、各アポイント当日の夜にみんなで集って「何を言われたか」を祝賀するイベント(単なる飲み会)を開催する流れもでき上がったので、それが楽しいイベントに発展したのだから損はなかったと思う。
そういうわけで最近は、"What a pathetic we are!"(なんて哀れなの、私達!)を合言葉に、サイキックごときに「なけなしの金」(個人面談1時間$75税なし。録音テープ付き)を払ってしまった自分達のことを「バカよねー!」と笑い飛ばしながらも、誰が何て言われたかで非常に盛り上がる日々を送っている。ちなみに、偶然にも私達全員が「いつか自分にぴったりのMr.Rightに出会うことができるか?」と尋ねて、「晩婚だけど、こういう状況でこういう人に出会うから心配いらないわよ」と言われたので、彼女は「晩婚者全員に同じことを言っている可能性がある」とも言えるわけだが(笑)、それで気持ちが明るくなって将来の希望が持てるなら、それは「あり」ではないかと思う次第である。
私は自分のことを一般に言う「大企業に勤務する頭の良い人達」ほど頭は良くないけれど、心底からのオバカさんでもないと思っているので(もし、そうだったら自分独りで仕事をして海外で生きていけないと思うから)、「サイキックに言われた自分の未来がすべて正しい」とは思わない。自らが「ポジティブな気」を持っていれば、優秀なサイキックであればその人の「良い気」とか「強い気」の部分だけを簡単に読み取って言葉にするのではないかと思っているだけだ。でも目には見えないし、多くの人はくだらないと思うかも知れないような小さなイベントによって、私を含む独身女友達全員が「自らが描き続ける小さな希望を持って一生懸命アメリカで独身生活を続けていける」ならば、それで$75の価値は十分にあると思うのだ。いちばん大切なことは、それぞれの状況にかかわらず、みんなが希望を捨てずに前向きに生き続けるということだからね。
※文中に登場するサイキックについてのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
第19話 「大人の女のお断わり方」
嫌いな男や自分のタイプではない男から誘われた時、30代の女性としてどのようにお断わりするべきだろうか? 「相手を傷つけることなく、きちんと意志を伝える」というのは、思いのほか実行が難しい行為である。
20代の頃は、多少は相手の気持ちやプライドを傷つけない断わり方を考慮してはみても、大多数の女の子たちは結局のところ自分の意思とプライドを100%優先させる断り方をしていたように思う。古い記憶になるが、私が東京で働いていた20代前半頃は「悪いけど、私あなたのこと嫌いなの」と意地悪に突き離す同僚や、「私があなたに釣り合うと思うわけ? 冗談でしょ」などと高飛車に振舞う先輩などが周囲に大勢いた。「いくら何でも、その言い方はひどい」とは思いながらも、私自身、興味のない男の子からのプレゼントは受け取るけれど連絡はしないとか、女友達と一緒にご馳走にはなるけれどデートはしないとか、かなり調子に乗った女だった。あの頃は「若い」という事実だけで許されることが山のようにあったのだ。もしも、私が現在も独身である理由を神様が、「あのときの悪行が今、しっぺ返しとして戻って来たのですよ」と言ったとしても、私には言い訳する余地さえない。
とにかく、残念ながら私は30歳というボーダー・ラインをとっくに超え、世間でいう「大人」になってしまった。だから何事も大人として立派に振る舞うべきなのだが、思ったことをすぐ口に出してしまうので、大人に欠かせない「別の意味を含んだ言い方や行動」をするのが苦手である。なかでも私が特に苦手とすることのひとつが、冒頭にも書いた「嫌いな男に対しても思いやりのある気持ちを表しつつ、美しくお断わりする」という行為だ。自分の気持ちをはっきり伝えないと相手との間に誤解が生じるし、逆にあまりにもきっぱり断わると相手を逆上させかねないので非常に高度なテクニックが要求される。
そういう難しいことを、私の周囲の女友達は上手くやっているようだ。日本よりもずっとオープンに見えても、実はアメリカにも「含み言葉」や「含み行動」が溢れている。だから私も、アメリカ人の女友達の言動をよく観察し、彼女達からアメリカ的な大人の振る舞いを学ぼうと試みてきた。しかし、英語がネイティブではないからかも知れないが、どうも上手くいかない。「できるだけ相手を傷つけないように」と相手の立場を気遣えば気遣うほど、必ず悪い結果になるのである。
先日も、そんな私に厄介な問題が発生した。同じ大学に在籍していたアメリカ人、ジョージ(仮名)から数年ぶりに突然Eメールが届いたのが始まりだった。成績優秀だったジョージは大学院の博士課程を卒業後、某大学で助教授の職に就いたが、作家になって執筆活動に専念する夢が捨てきれず、退職して心機一転シアトルに引っ越すことにしたという。メールには、「シアトルにはキミしか知り合いがいないし、街に慣れるまでいろいろ助けて欲しい」と書かれていた。「なぜシアトルなんだろう?」とは思ったが、私は知人として普通に常識ある対応をし(シアトルは住みやすいとか、文化レベルがなかなか高い街だとか)、2ヵ月程の間に数回メールを交換した。そして、ジョージは本当にシアトルに引っ越して来た。だが、それから毎日のように彼から「キミ以外に友達もいないし、映画でも行かない?」「コーヒーでも飲まない?」というメールや、留守電にメッセージが入るようになった。しつこいくらい頻繁にだ。
引っ越して来てすぐに連絡をもらった時は、その後の展開を想像もせずに近所のコーヒーショップで再会してしまった。何年振りかに会ったジョージは相変わらずナイーブな感じの人だったが、特別親しかったわけでもないので話題もそれほどなく、私は1時間ほどで席を立った。初日から「さっさと帰る」というサインを見せたのだが、その後もしつこく誘われて、仕方なく2度目に会った時にカジュアルな口調だが唐突に、「お互い物書きだし、こんなに話の合う僕らにロマンティックな将来はあると思う?」と聞かれたので、私は間髪入れずに笑顔で「それはないと思うわ」と返答した。笑顔で対応するのが大人なのだ。そして、この発言により彼の意図が見えたので、それ以来、彼から連絡が来ても無視するようにした。
それでも「どうして僕のメールに返事をくれないの?」と執拗に連絡してくる彼を少し不気味に感じ始めた私は、友人のリンダ(37歳)に「ねえ、こういう人からこういうメールが頻繁に来るんだけど、どう書いたら迷惑だとわかってくれると思う? 大学時代の知人だから足蹴にもできないし……」と相談した。美しい才女リンダは、常日頃から興味のない男性からのアプローチに対して細心の注意を払い、「自分はあなたに興味がありません」という言動を顕にしている女だ。私もよく彼女の態度を見ているが、リンダは誤解されるようなそぶりを男性に一切見せることなく、いつもフェアである。その彼女が、「相手は元助教授だし、大人なんだから一般常識通りに“残念だけど忙しいから会えないわ”と書き続ければ、迷惑だというサインが伝わるわよ」と言うので、私はその通りに対応した。
でも、ジョージからのメールと電話攻撃は終わらなかった。本心では「夏は仕事のカキイレ時で忙しくて、あんたと会ってる時間なんてないんだよ。いい加減に気付け、タコ!」と言いたかったのだが、私は大人らしく毎回「出張続きで忙しいから残念だけど会う時間はありません」と礼儀正しく答え続けた。すると、しばらくして恐ろしいことが起こったのだ。ジョージが、なんと自作の詩を私に送りつけるようになったのである。往々にして詩を書く男というのはナルシストが多いが、詩を一方的に他人に送り付けるという行為はかなり重度な問題である。しかも、彼の詩はお世辞でも良く書けていると言える代物ではなく、自己満足の賜物といえるような少女趣味な作品だった。きっと彼はすっかり自分を見失ってしまったのだろう。その詩に加えて、「目を閉じていてもキミの瞳と体が僕の目から離れない。キミは本当に美しい」などと、今時の幼稚園児でも言わないようなメールを送ってくるようになったのだ。
この事態を重く見た私の友人たち(男女数人)は、「付き合っている人がいるし、このようなメールを送られても困るので今後はメールや電話は遠慮して欲しい。あなたの今後の幸せを願っています」という、いかにもアメリカ人が書きそうな内容のメールを出せと私にアドバイスし、仕方なく私は指示に従った。しかし、「大人として正しいお断り方」に乗っ取って書いたメールは、彼の炎にさらに油を注いでしまい、さらなる恐怖メールが次々と送られてきたのだ。
「何を言ってるんだ? キミに彼がいるかどうかは僕にとってはまったく問題ではない。僕らには将来があり、キミと僕は結ばれる運命にある。だから僕はシアトルに引っ越して来た。僕の声はキミの耳に雷のように激しく届くはずだ」
「キミからの拒否を意図するようなメールを受け取ったが、キミの言い回しはどうもはっきりしない。幸せになってとはどういうこと? 僕は僕らの将来について話し合いたいだけなんだ。近いうちに10分でいいから僕と会って、まずキミを抱擁させて欲しい」
どの国にも妄想に取り付かれた人はいるとは思うが、外国でひとり暮らしをしている私はこのメールを見て鳥肌が立った。でも、同時に彼がナイーブさを理由にしながら非常に自己中心的で、私の意志表示をまったく受け入れようとしないことに対して、ものすごい怒りが湧き上がった。大人としての意志表示はやわらか過ぎて、相手も大人でなければ何も伝わらないのだ。
「奴は大人じゃない」。そう思った私は、自分の怒りのすべてをコンピューターに向かって書きなぐると受話器を取り上げ、ジョージの家に電話を掛けて一方的に大声で書いたものを読み上げた。Fワードを連発する私に対して、彼は状況がつかめずアワアワしていたようだったが、私は今まで言いたかったことを全部一気に読み終えると、「人の気持ちを読み取る努力をしなければ作家になんてなれないわよ! とにかく二度と連絡しないで!」と叫び、受話器を高く振り上げて電話機に何度もゴンゴンと叩き付けた。自慢するわけじゃないが、これほど発狂したのは久しぶりだった。
その結果、数年前ガレージセールで購入した私の電話機は見事に壊れてしまったが、その後はジョージから詫びと言い訳を記したメールが数通届いたものの無視していたら連絡が来なくなった。「めでたし、めでたし」だが、最初から自分の本心をはっきりと伝えていたら、こんな厄介なことに発展しなかったのではないかという思いが残った。私には、一般に言う「大人の女としてのお断り方」が、自分が「いい人」だという立場を守るために思ってもいないきれいごとだけを並べているように聞こえてしまうのだが、そう思うのは私がそれを上手くできないからだろうか?
P.S. 先月号で話題にしたサイキックは多忙につき、現在新規クライアントを受け付けていないそうです。あしからず。
第20話 「独身女のお伽噺」
先日、知り合いのバースデー・パーティーで、一際目立ったオーラを放つ美しいアジア系アメリカ人女性と出会った。満面の笑みを浮べながら私に話し掛けてくれた彼女の名前はエイミー、台湾生まれのチャイニーズ・アメリカンだ。
エイミーはそのパーティーの主役であるバースデー・ボーイの婚約者で、先日プロポーズされたばかりだと言いながら、左手に輝くセンスの良いダイヤの指輪を嬉しそうに見せてくれた。結婚式まであと数ヵ月。幸せの真っ只中にいる女性というのは本当に美しいものだが、彼女のその夜の輝きは同性から見ても普通じゃない美しさだった。こちらの気持ちまで明るくなるほどの彼女の笑顔に引き込まれ、全然知らない人なのに「本当におめでとう!」、「お幸せにね」という言葉が心の底から湧き出たほどである(笑)。
しかし、話し始めて数分もしないうちに、彼女がいきなり「今だから言えるけれど、実は私、何年もまったく出会いがなくて、もう自分は結婚できないのだと諦めていたの。だから本当に嬉しくて……。だって出会いを待ち続けて43歳にもなって、ある日、突然理想の男性と出会って結婚するなんて信じられる?」と言うではないか。どう見ても30歳代半ばにしか見えない彼女が43歳だという事実に驚愕している私を気に留める様子も見せず、エイミーは「その理想の彼とどのように出会ったのか」を一部始終語り出した。
見た目は誰がどう見ても30歳代だが、実際には40歳をとうに過ぎてしまったエイミーは友人達に「いい加減、インターネットの出会いサイトに入会したらどう?」と気遣われ続けるような毎日を送っていたそうだ。でも「いつか必ず理想の男性と“出会うべきして”出会える日が訪れるはず」だと信じていていた彼女は、「保守的だと言われても出会いサイトは嫌なの」と断り続け、仕事に打ち込みながら、どうにか前向きに毎日を過ごしていたという。
そんな彼女がある日、女友達と某有名コーヒーショップでお茶をしていると、背が高くてハンサムなアジア人男性が店に入って来た。「まあ、ものすごく私好みの男性!」と、その瞬間から彼女の目は彼に釘付けになった。しかも彼が、偶然にも女友達の真後ろの席に座って書類を手に仕事を始めたので、エイミーは彼の横顔から目が離せず、少女のように胸がドキドキしてしまったという。まさに一目惚れである。だから「そんなハシタナイことをしたのは生まれて始めてだった」そうだが、女友達が帰っても彼女はその場に残り、携帯から仕事先に電話を入れて、「私の携帯番号は853-XXXXです」と、なんとか彼が聞き取ってくれることを願いつつ、非常にゆっくりとクリアーに自分の番号を電話に向かって繰り返すという小細工までしてしまったそうだ(笑)。でも、残念ながら彼はそれを全然気に留める様子もなく、彼女も仕事に戻らねばならなかったので、仕方なく席を立って上着を着たその瞬間、初めて彼が自分を見ていることに気付いた。エイミーは彼の方を見ることができないほど緊張し、ジャケットのボタンをはめる自分の手が震えてしまったそうだ。でも突然、そんな自分の行為がとても恥ずかしくなり、そのまま逃げるように店を出てしまった。
しかし、彼女は翌週の同じ曜日の同じ時間に、そのコーヒーショップに戻ってみた。彼がその店の常連ならば、また同じような時間に現れるかも知れないと思ったからだ。でも1時間以上待っても彼は現れず、彼女は「いい歳をして私は何をしているのかしら……」と、自分の行為が情けなくなって店を出た。それでも、なぜか一目見た彼の面影が忘れられない……。そんな自分の想いを女友達に相談すると、「名前も職業も知らない男性を想ってもどうにもならないでしょ? そんな偶然は忘れた方がいいわよ」と真剣に言われ、さらなる自己嫌悪に陥り落ち込んでしまった。
翌日、その女友達から連絡が来た。「ところで以前から延び延びになっていた例のブラインド・デートのこと覚えている? ようやく今日あなたのメルアドを相手の親友に教えたから連絡が来ると思うわ。私はその男性と会ったことはないけれど、友人がとても素敵な人だと太鼓判を押しているから、上手くいくといいわね」と言う。エイミーは気が進まなかったが、「いつまでも変なことを気にしてないで、前に進まなきゃだめよ」と励ましてくれる女友達の行為に対してお礼を言った。
早速、紹介された男性からメールが来たので、それに返信するという形でメールを交換し始めた。相手にほとんど何も期待していなかったエイミーだが、その男性から届くどのメールも非常に紳士的で知的なうえ、お互いの趣味も合うことがわかってきた。2週間ほどメールを交換した後、「知人の紹介でもありますし、一度会いませんか」と誘われて、初めて実際に会う約束をした。そして約束の日、彼女が待ち合わせの店のドアを開けると、約束した窓際の席でひとりの男性が新聞を読んでいる。それを見てエイミーは固まった。その男性は例のコーヒーショップの彼だったのだ。
「オー、マイ・ガーッド!!」と大声で叫んでしまったのはエイミーではなく、彼女の話を黙って聞いていた私と女友達である。そのパーティーの参加者全員を振り向かせたほど、年甲斐もなく激しいリアクションをしてしまった。それはともかく、エイミーの話はまだ続くのである。
彼を見たエイミーは“これ以上動揺できないほど”動揺してしまい、一旦手にしたドアを閉めて外に飛び出した。そして何度か大きく深呼吸をして自分の体勢を立て直し(笑)、再度ドアを開けて、ゆっくりと彼の前に歩み寄った。「私、エイミーです。お会いできて嬉しいわ」と、緊張しながら自己紹介を終えると、彼女は思い切って切り出した。「私、クイーン・アンにある○○コーヒーショップで5週間前にあなたと会っているの。覚えていないかしら?」と、その時の状況を細かく彼に説明した。すると彼も「あっ、あの時の!」と思い出し、その後は信じられないほど話がはずんだ。なんと初めてデートしたその当日のうちに、「近い将来、結婚したいと思うか」「子供が欲しいか」「クリスチャンか否か」など、それぞれが望む結婚の条件や、お互いのパーソナルなことなどを話し合ってしまったそうだ。しかもお互いに信じられないほど、相手がお互いの「理想の人」に限りなく近いことがわかったという。そしてふたりは毎日デートを続け、結果としてエイミーは、コーヒーショップで一目惚れした男性から、出会って3ヵ月後にプロポーズされたのである。
「だからね、43歳の独身女性にもお伽噺のような出会いが現実に起こるのよ。あなたも自分の理想の人と運命的に出会う可能性を絶対に諦めちゃダメよ」と、私の手をしっかりと握り締め、輝くような笑顔でエイミーは言い切った。まるで同志を勇気づけるかのように。そんな熱い彼女の言葉に対して、「確かにあなたには起こったけれど、私にはそんなお伽噺は絶対に起こんないと思う」と一瞬、捻くれそうになったが(笑)、諦めかけていた希望が見えた喜びを単純に受け止めて「いやー、なんだか今日はイイ話を聞いたなあー。ねえ、皆そう思わないー?」と上機嫌な私の呼びかけに、周りにいた独身女友達がみんな妙に真剣にうなずいていたのが印象的な夜だった。幸せな人は本当に美しい。しかも、エイミーは「私の身に起こったことは30代半ばを過ぎた独身女性には元気の出る話だと思うから、あなたのコラムに本名を使って書いても構わないわよ」とまで言ってくれたのだから、本当に素敵な人である(笑)。
第21話 「妙に押しが強い男」
私の女友達のひとり、アメリカ人のミリーは誰がどう見ても37歳とは思えないほど若くて美しい独身女性である。彼女は某有名企業に勤めるITアナリストで推定年収は約1,000万円。独身でありながらすでに一戸建ての立派な家を所有し、さらに独身女性のハウスメイトを入れて自分のローンの支払いを補いつつ、妙な男が寄り付きにくい生活環境を維持するという安全まで確保している非常に堅実な女性だ。
ミリーほど賢くて美しくて優しくて金銭面でも成功していると、当然だがいろんな男性が言い寄って来る。しかも彼女は仕事がバリバリできるのに、プライベートになるとサクセスフルな白人女性とは思えないほど気が弱く受身になるので、多くの男性達にいつも追い掛けられている。なかでもミリーと10年も前に別れた元彼のブライアンは、今でも半年毎に彼女にプロポーズをし続けているほどだ(この様子には私のような他人ですら見ていて気の毒になる)。しかし、ミリー自身はブライアンのような熱心な男が周りに大勢いるにもかかわらず、いつも溜息まじりに「あぁ、はやく良い人に出会って結婚したいわ」と言っている。
なぜミリーは未だに独身なのか? 女友達が彼女にその質問をすると、彼女は決まって穏やかな笑顔を浮かべながらこう言うのだ。
「だって結婚相手も私と同様にとても敬虔なクリスチャンでないとダメだもの。でも私の教会には素敵な独身男性がいないから出会いがないの。ブライアンのことは今でも大好きだけれど彼はクリスチャンではないから仕方がないわ。私のために洗礼を受けると言ったこともあるけれど、彼が本心から神を信じられないなら洗礼を受けても意味がないから」
私はキリスト教信者でもイスラム教信者でもないので、信仰が愛情よりも大切ということを実感するのは正直言って難しいのだが、本人にとってはそれが一番大切な条件ならば仕方がないというほかないだろう。
しかし先日、そんなミリーに、熱心なクリスチャンの独身男性が突然アプローチを掛けて来た。ケンという39歳のこの男性は、仕事の関係でミリーの通う教会の近くに引っ越して来て、教会の催しを通して彼女と知り合ったそうだ。初めてのデートの後、ミリーにその感想を聞いた時は「彼はとても誠実なクリスチャンだし、真摯に相手の話を聞ける“聞き上手な人”で、優しくて紳士的だったから次回の誘いも受けたのよ。彼のことをもっと知りたいし、まずは友人として始めてみようと思って」と話し、とても嬉しそうだった。
やっと彼女にも条件の合う男性が現れたと周囲の私達も喜んだ。しかし、その約1ヵ月後に彼女に会った時には、なぜか事態は急変していた。人間不信にでもなったかのように落ち込んでいる彼女をなぐさめようと理由を聞いた私達も「えっ、そんな男いるの?」と、驚いてしまったのだが……。
ミリーの話はこうだった。ケンとの2回目のデートは1回目同様、信仰の話やお互いの将来の夢など楽しい会話を交わしたのだが、3回目くらいから雲行きが怪しくなってきたそうだ。ケンはまるで人が変わったように、自分の話しかしなくなった。それも、ミリーにはまったく興味のない話を延々と続け、彼女が丁寧に「私はそういう話は苦手なの。ごめんなさい」と何度話題を変えようと試みても「いや、僕は今これについて話したいんだ」と強い口調でミリーを遮り、いつまでも話し続けたこともあったそうだ。
その時は「今日は少し機嫌が悪いのかも知れないわ」と思って前向きに流したものの、ある日のデートでは、もっと困ったことが起きた。ふたりで車に乗っていた際、何の前触れもなく彼が突然ミリーの手をガッと握って来たのだ。私には手を握られるくらいたいした問題ではないように思えるが、信仰心の厚い彼女はそういうことが許せないので「私たちは友人なのだから、こういうことは困るの。手を離してください」と真剣に訴えた。すると彼は「僕は今こうしたいんだ。だから離さない」と言って、さらに強く握り、彼女が何度引っ張って手を抜こうとしてもビクともしない。そういう紳士的ではない態度が許せない彼女はとても不快な気持ちになったが、気が弱いのでそれ以上何も言えず、10分くらいして彼が自分の話に夢中になった瞬間に何気を装って手を引き抜き、その場を切り抜けたそうだ。
ようやくレストランについて食事を始めると今度は政治の話になった。彼は「キミはどの政党を支持しているんだい?」と聞いてきたので、他人に自分の政治的な考えについて述べることが嫌いなミリーは、その旨を彼に伝えて話題を変えてもらうように頼んだ(彼女は親しい女友達とでさえ政治の話をするのは知り合って何年か経ってからだ)。それなのに彼は頑として話題を変えず、しつこく同じ質問をしてくる。そこで彼女は「そんなに話したいなら、あなたの考えを先に話して」と切り替えした。すると彼は「僕はキミの考えを先に聞きたいんだ! 僕が自分のを話す前に!」と非常に熱くなって声を荒げたので、彼女は周囲の人の目が気になってとても恥ずかしい思いをしたそうだ。
「宗教の話は合うけれど、こんなに強引な人とはもう会えない」とミリーは思い、その次の誘いは丁寧に断った。断られた彼は深く反省し、「そんなつもりはなかった。でもキミがそう感じたのなら、もう二度と強引な話し方はしないからまた会って欲しい」と懇願するので、その説得に負けて彼女はまた彼と出掛けたそうだ。強引な部分さえなければ、かなり彼女の理想に近い人だったからだ。
しかし、残念ながら彼は変われなかった。その日、ミリーは翌週に他州に住む古くからの女友達が自分の家に泊まりに来ることが楽しみだという話をしていた。そして「彼女が来るから、明日は新しいマットレスを買いに行く予定なの」と言った時のことだ。
「ちょっと待って。なぜキミが彼女のためにわざわざマットレスを新調するんだい? そんな必要はまったくないよ」と、かなりムッとした口調で彼が言い返してきた。「はぁ?」と思いつつ、彼女は優しい口調で「私が用意したいのだから問題ないのよ」と返すと、彼は「いや、キミはマットレスなんて買う必要はない。買っちゃダメだ。まったく何を考えているんだ。そんなの金の無駄だよ!」と、なぜだか妙に熱くなっている。また始まったと思った彼女はすぐに話題を変えたが、彼は一向に引かず、何度ミリーが話題を変えてもマットレスの話に戻してしまう。ミリーはお金にはまったく不自由していないし、持ち家なのでゲスト用のマットレスは以前から欲しいと思っていた。だから「私が買いたいから買うのよ」「いや、絶対にそんなもの買っちゃダメだ!!」「なぜ、そんなことにこだわるの?」「大事なことだからだよ! マットレスなんて必要ない。ソファーか床に寝てもらえばいいじゃないか!」「私のゲストなのに、なぜあなたがそんなことを言うの?」「僕が必要ないと言ってるんだから、マットレスなんて必要ないんだ!」と、ふたりのやり取りはすでに会話ではなくなり、自他共に認める温和なミリーは初めて彼にこう言った。
「私、人と争うことがとても苦手なの。あなたもクリスチャンだから同じだと思っていたけれど私の思い違いだったようだわ。申し訳ないけれど、あなたのように強引な人とはお話できないわ」
すると彼は火山のように逆上し、「僕のどこが気に入らないんだよ! えっ?えっ? どうなんだ、言ってくれよ、おい、ちゃんと答えてくれよ!」と、なりふり構わずわめき立てた。それを見た瞬間、ミリーは逃げるように素早く店を出た。そしてタクシーをつかまえて、なんとか家に逃げ帰った。
だいたい39歳にもなった大人が、他人の家のマットレスごときにとやかく言うなんて信じられないが、そういう男性が存在するというのは恐ろしいことである。ただ、彼がそういう男だというサインはかなり早い時点で出ていたのだから、そのサインをあえて無視したミリーにも今回は少し問題はあった。だからこそ彼女は今、自分の選択眼に対する自信をすっかり失い、とても落ち込んでいるのだ。このショックから立ち直るには、まだ少し時間が掛かるだろうが、とりあえずミリーはこの事件の後、自分が理想とする男性が持つ条件に「強引ではない人」という一行を加えた。彼女の次の出会いが「温厚な人」であることを、私達友人一同、心から期待している。
第22話 「スタンダードな美意識」
数年来の女友達、キャシーの職業は「アーティスティックなフィルム・メーカー」である。つまり、生活は苦しくても映像を制作し続けているという奴なのだが、いつも興味深い内容の作品を作るので私は彼女が大好きだ。先日、そのキャシーが「最近、おもしろいドキュメンタリー映画を制作しているから、ちょっと手伝ってよ」と連絡してきた。以前にも彼女の撮影を何度か手伝ったし、「おもしろい」という言葉に弱い私は、誘いを受けた途端に「うん、何でもやるよー!」と内容もよく聞かずホイホイと了承した。
指定された撮影現場であるキャピトル・ヒルの某バーに到着すると、カメラマンや照明マンが忙しそうに機材をセッティングしているところだった。早速、私も腕まくりをして何か手伝おうとするとキャシーがやって来て、「おっ、来てくれてありがと。そこに座って酒でも飲んでてね。今日は私のオゴリだからさ」と私に声を掛けた。「なんで手伝いに来たのに酒を飲むのよ?」と聞き返すと、彼女は「だって今日はあんたを撮るんだから、準備ができるまでリラックスして欲しいのよ」と言うではないか。
「えっ? 私を撮る!?」。そういえば電話でそんなことを言われたような記憶の断片もあったが、いつもの冗談だと思って適当に流してしまっていたのだ。とは言われても、私は撮影の裏方を手伝ったことはあるが、自分を撮られたことは一度もない。そもそも何で私が彼女の作品に“出演”しなければいけないのか?
ギャーギャーと騒ぐ私に、キャシーはこう説明した。「だから、もう言ったでしょ。今回の作品ではアメリカに住む女性達が自分の身体に対してどんなコンプレックスを持っているかを取り上げているの。“人は見かけによらない”という部分を前面に出したいのよ。あんたはいつも自分の体重を気にしているようだから、その理由とかをカメラの前で話して欲しいわけ。私の質問に答えるだけだから簡単よ。じゃ、頼むね。カメラ回すよ」。
そういう訳で、私は友人のカメラの前でなぜか自分の身体に対するコンプレックスについて赤裸々に語らされることになったのである。私のような図太い性格の人間があれほど緊張したのは、アメリカで初めて試験を受けたとき以来かも知れない。とりあえず緊張を解すために好物の赤ワインをガブガブ飲みながらインタビューに答えたのだが、1時間のインタビューでボトル1本近くは飲んだと思う。しかも、タダだったし(笑)。
かなり酔っ払ってしまったので具体的なことはあまり覚えていないが、結果としてインタビューは結構楽しかった。キャシーはアメリカ人なので、私が自分の体重を気にしていることをいつも不思議に思っていたらしく、「あなたはアメリカのスタンダードでは痩せている部類に入るのに、なぜ自分をデブだと思うのか?」という点に質問が集中した。そして、それに関する質問に対して私はなぜか妙に燃えてしまった。何でも好き勝手に答えてくれと言うので、本当に好き勝手に答えた(笑)。たとえば「アメリカと日本のスタンダード・サイズは全然違う! 私は渡米以来10キロも太ってしまったから、今や日本では“かなりデブ”の部類に入り、ワンサイズ展開で押し通すオシャレなブティックではサイズが小さ過ぎて欲しい洋服がひとつも買えない。前回、日本に帰国した際は自分のふくらはぎが太過ぎてファスナーが最後まで上がらず、欲しかったロングブーツも買えなかった。そんな体験を繰り返している私をナイス・プロポーションだというアメリカ人の方が変である。私だって子供体型になるほど細くなりたくはないが、ロングブーツが買えないほど太ってもいられない。そもそも太っているのは身体に良くないし、アメリカ人は全体的に太り過ぎなのだ」と、いうようなことを話したように記憶している。今考えるとお恥ずかしい限りだが、言ってしまったことは仕方がない。酒の力というのは本当に恐ろしいものである(笑)。
キャシーだけでなく、現場にいたスタッフは全員アメリカ人だったので、私の発言がすごく面白かったらしい。彼らが一番驚いていたのは、私が数年ぶりに日本に帰国したとき、私の姿を見た父親が「お父さんもこんなことは言いたくないが、もしかして、お前はアメリカで肥満病に掛かってしまったのだろうか?」と真剣に心配したというエピソードだった。それを聞いたスタッフたちは驚愕していたが、本当の話である(お父さん、心配させるほど太ってごめんなさい)。ともかく、アメリカ人にはこの日本人サイズの感覚がわかりにくいのだろう。しまいにはインタビュー中なのにスタッフのひとりが熱くなって、「日本のサイズは、いくら何でも小さ過ぎるよ。華奢な身体なんて子供みたいで全然セクシーじゃないぜ。なんでそこまで痩せる必要があるんだよ」と発言してしまい、一旦インタビューを中断しなければならない状況さえ生まれてしまった(笑)。
仕切り直した後、今度は「自分の身体のどの部分が好きか? 嫌いな部分はどこか?」と聞かれたので、私はちょっと気取り口調で、「うーん、強いて言うなら好きなのは胸かな。西洋人のように大きくないけど形はいいから。嫌いなのはお尻。アフリカ象みたいに垂れてるから」(笑)などと答え続けた。撮られている本人は自分の様子が見えないので結構何とでも言えてしまうものだが、もし、その現場を見ている日本の人がいたら「お前、いい加減にしろよな!」と怒られてしまうようなインタビューだったと思う。
でも、まぁそんな感じでインタビューは終了し、そのまま流れでスタッフ全員と酒を飲んだが、やっぱり話題は「日本人とアメリカ人の美意識の違い」に終始した。中でも多くのアメリカ人の男性スタッフが不思議がったことのひとつが「日本人の若い女性(特に短期留学生)の歩き方」。誰かが「どうして日本人の女の子たちは妙に狭い歩幅で、しかも内股で歩くのか? 美人でもあんな歩き方ではみっともなくて可哀想な気すらする」と発言すると、まるでセキを切ったように男性陣が一斉にコメントをはじめ、「それ、俺もすごく不思議に思ってた」「何で友達が注意してあげないのかな」「きっとみんな、アメリカの靴のサイズが合わないんだよ」「もしかして足が細過ぎて体を支え切れないのかも」「バカ、そんなはずないだろ」「でも、みんな鏡くらい家にあるだろ」「それにしても本当に変な歩き方だ」と、おしゃべりな私でさえ発言するスペースがないほど沸いていた。
しかし、改めて言われてみると、“内小股”でペタンペタンとミュールの音を高らかに鳴らしながら街を歩いているのは日本人の若い女の子ばかりのような気がする。そういえば以前にも日本人女子学生の集団と街ですれ違った時、一緒にいたアメリカ人の女友達に「どうしてあんな風に歩くのかしら? かわいそうに」と言われたことがある。その時は「きっと、あの歩き方が日本ではクールなんじゃないの?」と適当に笑い飛ばしてしまった気がするが、その友人はなぜか彼女達に少し同情しているような様子だった。
さて、実際のところはどうなのだろうか? 日本では“内小股歩き”が美しい歩き方であり、女性が胸を張って颯爽と歩くのは、もうイケてないことなのか? 今度、日本に帰国するときは「最新の平均体重」だけでなく「最新の女性の歩き方」もリサーチする必要がありそうだ。でも、まぁとにかく身内の友達の間だけでもこれほどまで論議を醸し出すのだから、「文化の違い」とは面白いものである。
第23話 「ボディー・ランゲージの秘密」
先日、アメリカ人の男友達のカート(33歳)、チャッド(34歳)、ケビン(37歳)の3人と久しぶりにお酒を飲んだ際、全員共通の友人である日本人女性T子(36歳)のことが話題に上がった。アメリカ生活歴が長く、英語もうまいT子は、話し好きで明るく誰にでもフレンドリーで、驚くほど友達も多い。彼らも私もT子とは数年来の付き合いになるが、彼女はいつ会っても楽しくお酒が飲める素敵な人だ。だが、その夜の男友達3人の会話を聞いた私は驚いた。彼らが、T子はお酒が入るといつも複数のアメリカ人男性に自分から誘いを掛けるというのだ。
どちらかと言うとT子は“身持ちが堅い”方で、常に男に媚を売るタイプの女性ではない。しかも私は、彼女には片思いだが好きな人がいることも知っていたので、かなりムッとして「ちょっと、みんな失礼だよ。勝手な想像でそんなことを言うなんてヒドイじゃない? 彼女はそういうタイプの女性じゃないわよ。きっと偶然にそう見えただけ」と言い返した。すると、彼らは「俺らも友達のことを悪く言うつもりは全然ないよ。ただ、あのボディー・ランゲージはどう見ても……」と、その理由を私に説明し始めた。
カートによると、「T子はいつも、すごく“タッチー”」だそう。チャッドの見解では、彼女は“知り合いの男性と会話中、必要以上に相手の身体に触る”らしい。ひと言で“身体”と言うと少々誤解を招くかも知れないので詳細に書くが、それは相手の「二の腕」や「ヒザ」、「腿」、時には「腰」だそうだ。しかも彼女の場合、話の内容に夢中になって“うっかり”相手の腕をパシッ!と叩いてしまった感じではなく、いつも“かなりソフトなタッチ”で人の二の腕に手を添えてくると言うのである。
他人に何かを説明することがうまいケビンによると、「二の腕という場所は結構微妙だから“触り方”によるけれど、いくら相手が友達でもヒザや腿はプライベートな部分だから、他人のヒザに触るという行為は相手にすごく興味があるか、好きだという意思表示になる。どの国でも大抵そうだと思うけど、腿や腰にまで手を回したら、できれば相手とベッドを共にしたいという意思だと受け取られても当然だよ。だから話している最中に相手のそういう部分に触るのは、その人を誘っていることになる。キミが言うように彼女がもし無意識でやっているなら、改めるべきだ。意図的かどうかにかかわらず、ここではその仕草に意味があるんだから、誤解されても文句は言えないよ」と、言う訳である。
そう言われて私も思い出したのだが、確かに彼女はよく男性(と言っても知り合いや友達)の二の腕を触る。男友達の膝に手を置いて話し込むことも多いし、男友達に冗談でからかわれた後の仕返しに(だと思うが)彼のわき腹をくすぐるようにつかみ、その男性が妙に驚いたのを見たこともある。ある時彼女が、髪を染めたばかりの男友達を褒めていた時に、自分の手を彼の髪に入れてかき上げたのを見た瞬間は、さすがに私も驚いた。でも、パーティーやバーで、アメリカ人の女の子達がT子と同じように気軽に相手に触れるのを頻繁に見掛けるので、アメリカではこれは“あり”なんだろうと思って流していたのだ。むしろ私は、「アメリカ生活が長くなれば、外国人でも自然にこうなるのかも知れないな」と漠然と思っていた。
そういう訳で、親しい男友達の指摘を聞いて私は少し混乱してしまった。話に夢中になってふと置いてしまった手の位置が、大きな誤解を生んでしまうとは! 特に独身女性にとっては、かなりの痛みを伴う誤解である。「どうしても相手に触りたいなら、二の腕じゃなくて肩。手を置いても友人に誤解されないのは肩だけじゃないかな」とケビン。そう言われてみれば、アメリカ人はよく肩に触る。そうか、肩ならいいのか……。
しかし、ここはアメリカだ。ちょっとした知人との挨拶でもハグ(抱擁)をしてしまう国ではないか。他人と身体をぴったりくっつけ合う“ハグ”は問題なくて、“たかが二の腕にそっと触れる”のが問題になるとは、まったく不思議な国である。ちなみに、私は長年アメリカに住んだ今でもこの“ハグ”が苦手で、パーティーや街中で知人と会った際にいつも「この人とはハグをするような仲か否か」という一瞬の判断に非常に悩み、しばしタイミングを逃してギクシャクしてしまう状況を生み出すことが多い。何年も住んでいるのに情けないが、いつも迷ってしまうのだ。
でも、この“ハグ問題”は、日本人の私だけが悩んでいる訳ではなく、アメリカ人の間でもかなり奥深い問題らしい。もちろんアメリカ人は自分の家族やパートナー、親しい友人とならば悩むことなくハグをする。だが、パーティーで一度だけ会った人とか、友達の友達など、“微妙な知り合い度レベル”の人とバッタリ出くわした場合、大抵の人が「この人とはハグするべきか否か」という決断を瞬時に行うそうである。
「そんな時は、一瞬にして相手の出方を先に見る。相手が両手を広げようとしたら、すかさず自分も広げるんだ(笑)。それから、たとえ相手のことが嫌いでも、相手がハグしようとして来たら絶対に受けるしかない。それはマナーだ。しなきゃ相手にすごく失礼だし、するべきじゃない相手にしたら変な奴だと思われるから本当に難しいよ」とカークが言うと、他の2人もすかさず同意していた。どんな行為をしても基本的に何でも許されるグランマ(おばあちゃん)でもない限り、ほとんどの常識あるアメリカ人は多少なりとも「この人とハグをするべきか否か」という判断に悩まされるようだ。なかなか奥深い。
すっかり話が反れてしまったが、T子のボディー・ランゲージに戻そう。とにかく私は、T子は相手を誘惑しようとしている訳ではなく、無意識に人を触ってしまうだけだと思う。もしくは、アメリカに住んでいると「日本人は自分の気持ちをはっきり表さない」と言われることが多いので、「アメリカでは、このくらいフレンドリーに相手に接するべき」だと思っているのかも知れない。どちらにせよT子は、自分の行為が自動的に誘惑していると思われるものだと知っていたら、あえて人前でやるような女性ではないのだ。
その上、この男友達。みんなT子と結構付き合いが長いのに、なぜ今まで誰も本人に指摘しなかったのだろう? それを彼らに聞いてみると、「いや、だって彼女が本気で誘惑してるとしか思わなかったから(笑)。それに人が好きでしている行為に口を挟むのは失礼じゃないか」「まあ、センシティブなことだしな。大人同士だったら普通は友達でも言うことじゃないよ」「人の恋路は邪魔できない」などと言っていた。彼らはT子が意図的にやっていると思っていたのだから、こういう対応は大人として当然なのかも知れない。私はなんだか「誰でも知っている大事なことを、自分ひとりだけがずっと知らなかった」ような“ちょっと置いてきぼりにされた気分”を久しぶりに感じてしまったが、ずっと知らないよりはマシだろう。だから、「また新しいことを学んだのだから良しとしよう」という前向きな気持ちに戻り、“他人に誤解されないボディー・ランゲージ”を完璧に身に付けるべく頑張ろうと思っている。いや、それより状況に応じて“どちらにでも素早く対応できる”完璧なコントロール技術を身につけた方が、独身女性には便利かも知れないな(笑)。
第24話 「アメリカで上手に生き抜く女達」
某社に勤務する日本人の女友達S子(35歳・独身)が「かなり落ち込んでいる」と聞き、シングルの友人達が集ってS子を夕食に誘った。日本で商社に勤務していたS子はキャリア・チェンジを目指して退職し、商社勤めで貯め込んだ金を使い果たしてアメリカの大学に留学。卒業後すでに5年もアメリカで立派に会社勤めをしているにもかかわらず、未だにシェアー・ハウス(1軒家に数人で同居し安価に住むシステム)に住んでお金をセーブし、現在も日本に住む両親の生活費を助けるために毎月仕送りを続けている頑張り屋さんだ。
だが、その夜のS子は心身共に疲れ切っていた。なんでも「他人の親切を利用しまくる日本人の女の子達」との対応で、真面目にコツコツ働いている自分が嫌になってしまったらしい。最近の日本の状況はよく知らないが、アメリカには人の親切を利用してまで自分の得になるように行動しようとする輩が残念ながらたくさんいる(それをアメリカン・ドリームへの近道だと考えるのは間違いである。アメリカでもそういう奴は嫌われている)。だから、S子から具体的な内容をまだ聞いてもいないのに、「あちゃー、多いよね、そういう子。本当にムカツク!」「他人に迷惑を掛けていることすら気付かないヤツも最悪」「もっと悪いのが、人を利用しておいて気付かないふりをする要領のいい女よ」などと、同席者が一斉に話し出すという異例の事態となった。「とりあえず、まずはS子の話を聞こうよ!」と誰かが仕切った時には、すでにかなりの時間が経っていたと思う。
姉御肌でありながら優しくて面倒見のいいS子の元には、彼女の人柄を慕って20歳代後半から30歳代前半の日本人独身女性達が、よく相談を持ち掛けてくる。こういうことは在米歴が長くなれば、よくあることだ。誰だって困っている同胞を助けてあげたいので、S子は「お金を貸して欲しい」という相談以外は基本的にすべて親身になって相談を聞いてあげている。彼女は知り合いが自分の家に突然アポなしで押しかけて来たとしても手料理まで作って振舞ってあげるような親切な女なのだ。
ところで、前述の“お金を貸す相談以外なら”という部分を読んで「お金くらい貸してあげれば?」と思った人は、外国暮らしがまだ短い可能性が高いだろう。外国暮らしが長い独身女性達の間では“相手がどんなに困っていてもお金だけは貸してはならない”という暗黙のルールがあるからだ。“金の切れ目は縁の切れ目”とは本当によく言ったもので、アメリカで貸したお金が返って来ることはほとんどない。独身の外国人女(注:私達のこと)が他人に貸せる金額など所詮しれたものだが、それでも“そのお金がないと非常に困ってしまう生活状態”を何とか必死で保っている私達のような人間に向かって、「頼むからお金を貸して欲しい」と泣きついてくる人は、“多くの場合”、親からの仕送りが切れた学生か、アメリカ政府が就業ビザを出してくれなかったか、突然職場を解雇されてしまったか、他人の倍以上に頑張って仕事をする気など最初からないという人たちである。
友人を大切にしながら真面目にコツコツと外国で暮らして来た独身女達は、お金がないことがわかっている女友達に泣きついて金を借りようとはしない。なぜなら、自分が友人に泣きついたら、相手は元々ほとんどない貯金を解約してまで助けてくれようとするのが最初からわかっているからだ。それなのに、「本当は日本に帰国する片道航空券代はあるのだが、他人からお金を借りてでもアメリカに残りたい」という自分勝手な人達に限って友人や知人からお金を借りようとする傾向が高い。そして、そういう人達にお金を貸した場合、たいてい返って来ない。彼女らは遅かれ早かれ、結局日本に帰国することになり、「日本から必ず送金するから」と言いながら二度と連絡が取れなくなってしまうからである。貸し借りが2国間にまたがってしまうと、借りたまま逃げる相手も人間として多少恥ずかしい気持ちはあるだろうが、貸してあげたのに自己負担で掛ける入金催促の国際電話やEメールを送り続けなければならない努力もかなりの心労を伴う。日々の生活もあるので、いくら催促しても送金がないと徐々に催促を続けることが億劫になり、自分の気持ちも情けなくなってくる。結局、催促することを諦め、「貸した者が負け」という結果に陥ることを海外生活が長い多くの人が経験しているので、これが“教訓”として伝わっているのだろう。私自身も過去に苦い思い出があるが、S子も彼女の目の前で泣き崩れた知り合い(注:友達ではない)が気の毒でお金を貸したが逃げられてしまったという経験者なので、それ以後、現金だけは絶対に貸さないようにしているそうだ。
さてS子の話だが、先日、常日頃から頻繁にS子に連絡をしてくる年下のE子(30歳)が、「どうしても相談したいことがある」と電話を掛けて来たそうだ。どこか要領のいいE子からの電話を、S子はできる限り「申し訳ないけれど、このところ仕事が忙しくて……」と言って断るようにしているそうだが、E子はチャーミングというか甘え上手というか、「ホームシックだと思うのだけれど、S子さんが作るおいしい手料理がどうしても食べたいの」とか「S子さんのアドバイスが聞きたいの」などと言い、何度断っても根気よく電話を掛けてくる後輩だという。そうかと言って、いつS子の家に遊びに来てもワインの1本も持って来ず、「今、お金がなくて……。手ぶらでごめんなさい」と、しょんぼりと謝るので、S子はE子が気の毒になって「いいのよ、そんなこと気にしなくて」と言い、いつも手料理やワインを振舞ってしまうそうである。「そんなに皆の面倒を見ていたら今にS子が破産しちゃうわよ」と心配する私達に向かって、「私も自分の生活がキツイから正直言って困るけれど、この人は自分よりももっと大変なんだと思ったら断れないわ。誰だって“本当に”困っていなければ他人に自分の恥を相談しないでしょう」というS子。根っから“いい人”なのだ。
その日もS子はE子のお願いを一旦は断ったそうだが、E子が「死ぬほど困っているので、お願いだから話を聞いて欲しい」と懇願するので会うことを承諾した。だが、困ったことにE子の話は「これ以上切り詰められないほど生活を切り詰めているのに、給料が安くて食べるものまでセーブしている。どうしたらアメリカ生活を続けていけるか」という内容だった。それを聞いたS子は心底気の毒になり、現金は貸せないが、夜中まで掛かってできる限りのアドバイスをして、最後に「困った時はいつでも私の家にご飯を食べに来て。それくらいしか私にはできないから」と言って励ましてあげたそうだ。そして、その後数カ月間に渡り、E子は週に3回はS子の家に晩御飯を食べに来たそうである。
だが、ある時を境にE子がピタリと晩御飯を食べに来なくなった。E子からの連絡が途絶えて1週間ほど経った頃、E子のことを心配し始めたS子の元に別の日本人の女の子、T美が「相談したいことがある」と言って訪ねて来た。訪ねて来てしまった人を邪険にするわけにもいかないので、彼女を家に入れて話を聞き始めると、T美は肩を落としながら、「実は2週間ほど前に開かれたE子のハウス・ウォーミング・パーティーで出会った男性とデートし始めたのだが、彼は他の女性とも会い続けているようで……」と話し出したそうだ。それを聞いたS子は驚いた。T美が付き合い始めたい男性の話にではなく、“E子のハウス・ウォーミング・パーティー”という部分にである。
「ねえ、T美ちゃん。E子ちゃんのハウス・ウォーミング・パーティーで彼に会ったと言ったけど、E子ちゃんはどこかへ引っ越したの?」とS子が尋ねると、T美はこう言った。「えっ、S子さん知らなかったんですか!? E子はベルタウンのすっごく可愛いコンドミニアムを買ったんですよ。親からも結構頭金を援助してもらったって言ってたけど、羨ましいほど素敵なコンドでした。E子本人は“独身だからコンドくらい持っていないと心配だから”なんて言ってましたけどね(笑)。パーティー自体もかなりゴージャスで、料理もワインも……」
S子は、私達の前で「その後、T美が話していたことをほとんど覚えていないほどショックだったわ……」と、肩を落としてつぶやいた。自分の生活も苦しいS子が、「お金がないから助けて欲しい」と嘆くE子に晩御飯を食べさせてあげている間に、E子はちゃっかりコンドミニアム(日本でいうマンション)を購入し、そのお披露目パーティーまで開催していたのである。しかも、これだけ世話になったS子を招待さえしなかったのだ。そんなことがあっていいのだろうか!?
もし、E子がコンドを購入することをS子に打ち明けていたらタダ飯にはありつけなかっただろうし、S子をハウス・ウォーミング・パーティー招待したら、S子の親切を利用してお金を貯め込んでいることが周囲にバレてしまう。だから自分がコンドのためにお金を貯めていたことをS子に隠していたのだろうが、いくら何でもあんまりである。S子は自分のコンドを購入する貯金どころか、小さくても自分だけのアパートに住みたいのにシェアー・ハウスで我慢しているという厳しい状況下を生きている女なのだ。そんなS子に対するE子の行為は人の道を外れていると思えるほど非道だと感じるのは、私達だけなのだろうか?
「それじゃ、その子は自分の得になるためだったら手段を選ばないってことじゃないの!」「こういうヤツが多いから真面目に生きていることがバカらしくなる時があるのよね」「まるで他人に親切にする人間の方が人生の“負け組”みたいで理不尽極まりないわ!」などと、S子の話を聞いていた全員がかなり熱くなったが、しばらくすると「でもね、私も実はこの話に似たようなことを何度も経験しているの」「ホントは思い出したくもないけど、私もあるのよね」と、各自がポツポツと経験談を語り出し、S子を励ますつもりだった食事会がすっかり重い雰囲気に包まれてしまった。
だが、普段はめったに発言しない大人しいN子が、ふいに「みんな長くここに住んでいるから、似たような経験をしているのよね。でも、私達は今まで何とか他人に迷惑を掛けずに生きて来たんだし、“目に見えない大切なこと”を失ってまでアメリカで暮らす必要はないと思っている以上、私達は大丈夫よ」と、妙に落ち着いた口調で語るのを聞いて、一同は一瞬にして再び元気になった。私を含めて本当に単細胞な女達である。「そうよね、N子の言う通りよ。自分にとって大切なものを見極めたいと思ってアメリカに来て、人間として大事なものを失ってしまうなら海外で生きて行く必要なんてないもんね」「同感。人生一度きりだもの。人の道を外さずに自分が大切だ思うことを信じて生きていかなきゃね」と、途端に全員が前向きな発言をしながら、みんなで大笑いし、勢いでさらなるワインボトルを2本も空けてしまった(笑)。
人の道を外してでも世の中を上手く行き抜こうとする困った輩が周囲に大勢いるうえに、いつまで経っても自分達の日々の生活は苦しく、未だにコンドのひとつも買えず、なぜだか皆まだ独身だけれども、「2005年もみんなで前向きに夢を追いかけて生きていこうね」と子供のように素直に言い合える女友達がいるのは幸せだなあと思った2004年の瀬であった。来年こそ、もっと良い年にしたいものである。Havea happy new year, everyone!
第25話 「割り勘の基準」
最近になって気付いたのだが、シアトルと日本では男性と女性が一緒に出掛けた際の“割り勘に対する受け止め方”が少々異なるように思う。長年アメリカに住んでいて今さら何を言っているのかと呆れられるかも知れないが、今までわざわざ考えてみなかったのだから仕方がない。
この“男女間の割り勘”という行為に対する日米間の意識の相違を考えるきっかけになったのは(と言っても、そんな大袈裟な問題ではないだろうが)、先日アメリカ人と日本人の女友達大勢でワイワイ飲んでいる時に日本人のW子(33歳)が発したひと言だった。大手日系貿易会社で事務系の仕事をしているW子は、いつも小ぎれいで可愛らしく、最近サムというボーイフレンドができたばかり。その日、W子はサムがどれだけ素敵かという近況報告をした後、「でも、今までの彼とは違ってサムはいつも割り勘なの。それが嫌なのよねー」と軽く愚痴をこぼした。すると、その直後にW子はアメリカ人の女性達から、「えっ? それじゃ、いつもは割り勘にしてないの?」「割り勘が嫌だなんて、W子は彼との関係をどういうものしたいのよ?」「あなたはプリンセスになりたいわけ?」などと一斉に突っ込まれてしまったのだ。
きっとW子は、「割り勘なんて男らしくない」「デートでは男性が女性に奢るのがマナーよ」「彼の方が高い収入を得ているのだから、会計は彼が支払うべき」というような同調発言をみんなから無意識に期待していたと思う。まさか、こんな軽いひと言によって周囲から「あなたはゴールド・ディガー(玉の輿狙い)」的な指摘を受けるとは思ってもいなかったようで、「でも、私は割り勘には慣れてないから……」などとモソモソ言いながら、目で私に助けを求めてきた。でも、私も誕生日などの特別な日や相手が私に借りがある場合以外、基本的に男性とふたりだけで出掛ける時は会計を割り勘にしている。
しかし、本音を吐くなら私も男性が「払ってあげる」と言っているのにもかかわらず、クールに割り勘を押し通すなんてことは全然したくない(笑)。「男性に払ってもらうのは当然」だとは思わないが、「奢ってくれるならラッキー!」という浅はかな気持ちが自分の中に存在することは恥ずかしながら認めざるを得ない。でも、ここアメリカにおいて、それがポリティカリー・コレクトかどうかという問題や、「いつも奢っているのだから……」ということを理由にされて相手の要求を断りにくくなるという利害関係さえ生まれないならば、基本的には女性なら誰でも「男性に奢ってもらったらうれしい」という気持ちが少しはあると思う。だから、私はW子の気持ちもよくわかった。
私がこんなことを考えている間に、隣に座っていた日本人のM美(35歳)が、「私はお金を掛けてネイルやスパに通い、いつも素敵な洋服を着てきれいにしているのだから、食事やお酒くらいは男性に奢ってもらいたいと思っている。だから男性とふたりだけで会って割り勘なんて言われたら、何なのコイツって思っちゃう」と、きっぱりと言い切った。M美の実に堂々とした若いOL的な発言に私は大爆笑したのだが、残念ながらアメリカ人の女性軍は全然笑っていなかった(笑)。
まず、グラフィック・デザイナーのケリー(37歳)が、M美に向かって反論した。
「奢る・奢られるという行為が日常になると、奢られる側は必ずいつか奢る側に頼るようになるわ。そうなると相手に言いたいことを控えたり、相手の意見を自分より優先しやすくなって正当なバランスが保てなくなる。男と健全な関係を保つにも、まずは割り勘を通すことは大事よ。昔はアメリカでも男性が女性に奢るのがマナーだったけど、今でもその行為を常にしているのは、相手と寝ることを期待している男達か、仕事やプライドを持たない女性達か、パーティー・ボーイズ&ガールズだけよ」
少々フェミニスト的な発言に聞こえなくもないが、コンテンポラリー・アメリカンな意見である。
続いて広告代理店勤務のクレア(34歳)が、「男女の付き合いは対等なのだから、男性だから女性に奢る必要なんてないし、仕事を持つ女性が自分で支払えるにもかかわらず、相手に支払ってもらうことを期待するのはオカシイわ。W子もM美も立派な仕事を持っているのに、なぜ男性が支払うべきだと思っているのか、その理由をよく考えてみるべきよ」と言った。ごもっともな意見である。
クレアの意見を聞いて、W子は妙に素直に「私は今まで、そんな風に考えてみたこともなかった」と言い、ちょっと考え始めた。でもM美は、「クレアとケリーの言うことはわかるけど、私は男性に奢ってもらう。私がそうして欲しいのだから、そう思う自分の気持ちを全然悪いとは思わない。奢ってもらったら、私のことを大事にしてくれているって思うし、うれしいなって思うもの。それに、常に女性に奢れないような男性なんて、私は好きになれない」と、再び堂々と言い放った。アメリカ生活が長いだけあり、たとえ友人に「プリンセス」とか「ゴールド・ディガー」だとからかわれようが、いつでも自分の意見を堂々と言うM美を私は非常に立派なヤツだと思う。しかし、M美が今まで付き合ったアメリカ人男性達がみんな、彼女に“デートするには最高だけど、結婚は考えられない”と言った理由には、今の発言がまったく関係していないとは言えないかも知れない(笑)。
「ねぇ、M美はいつも相手に奢らせると言ったけど、相手から“その代償”を求められたことはないの?」と静かな口調で尋ねたのは、最近ボーイフレンドと別れたロリー(36歳)だった。ロリーは彼から“お金を出してもらうことの代償”を求められて、ヒドイ別れ方をしたばかりなのだ。
ロリーの元彼は頭脳明晰でルックスもクールなコンピューター・エンジニア。ロリーは某有名高級レストランのヘッドウエイター(日本で言うウエイトレスだがアメリカの高級レストランのヘッドウエイターは私のような地味なライターよりもずっと高給取り)で、いつも割り勘主義者。付き合い始めた頃から、ロリーはいつも「自分の分は自分で払わせて欲しい」「前回あなたが出したから今回は私が払う」と言っていたが、彼はロリーには絶対にお金を出させず、頻繁に洋服やコンピューターなど豪華なプレゼントを贈り、「早く僕の家に引っ越して来て欲しい」と彼女を急かしていたほど熱烈だった。周囲からは、彼は少々強引なところもあるが、ふたりは結構上手く言っているように見えていたのだが、彼女いわく彼は“コントロール・フリーク”だったらしい。
彼はロリーにお金は出させなかったが、ロリーの生活や行動のすべてに口を出した。彼女の仕事を下に見るような言い方をしたり、彼女のことを自立していない人のように扱い、彼女が意見をすると、「キミの面倒は僕が見てあげるから、何も心配しなくていいよ」と言って常に彼女をお姫様(というか子供)のように扱かおうとしたそうだ。そのうちロリーの友達の選び方や付き合い方にも口を出し始め、いつも明るい彼女からどんどん覇気がなくなっていった。ロリーが「彼はスイートだけれど、だんだん自分の自信やプライドが持てなくなってきたような気がする」と感じ始めた頃、彼が彼女のEメールをハッキングしていることが発覚(!)。それを機に彼女は彼と別れる決心をしたのだが、その途端に彼は豹変したのだ。「俺があれほど面倒を見てやったのに別れを切り出すとは、お前は最低な女だ。お前は俺の愛と親切と金を利用した!」と、彼女を罵倒しまくる攻撃に出たのである。
「いい歳して、まだレストランで働いているくせに、俺なしでこれからどうするつもりなんだ!」と言われた時には、ロリーは別れを決めて本当に良かったと思ったそうだが、当然である。ロリーがレストランで働いているのは、その仕事が大好きだからだ。いつか自分の店を出したいと夢見て頑張っていることを友達はみんな知っている。本当は自分自身に自信が持てない弱い男ほど、女を自分より下に置いてコントロールしたがるというが、間違いなく彼もそのひとりだったのだろう。
だからロリーはW子とM美に向かって、「対等な関係でいたかったから、奢って欲しくない、高価なプレゼントもいらないと言い続けていたのに、彼は私に一切払わせなかった。私のケースは奢ることで相手を服従させて支配しようとする最悪の例。だから相手に奢らせるなら、自分が相手とどのような力関係でいたいのか良く考えてから決めるべきだと思うわよ」と言ったのだが、実に説得力があった。それを聞いたW子は真剣な面持ちで大きくうなずいていたが、M美はまた「だけど、その男は超特別なケースだと思う。女性に奢ってくれる男がみんなコントロール・フリークだとは限らないじゃない? 私はやっぱり割り勘は嫌。男なら女に奢るという甲斐性がなきゃダメよ」と、胸を張ってきっぱりと言い切っていた。何度も言うが、実にあっぱれなヤツである。
男とは割り勘にするか、奢ってもらうか、もしくは自分が奢るべきか……。テーブルの上に請求書が置かれた時、私のように「奢ってもらいたいけど、割り勘にしておかないと……」などと、表情はクールに装っていても本心ではいろいろ考えてしまう輩もいるだろうが、きっと自分が相手とどんな関係を望んでいるかがはっきりわかっていれば悩むことなくひとつを選んでスムーズに行動に移せるのだろう。
そんなことを考えていたところに、親しい男友達から電話が掛かってきたので、「ねえ、私はあんたといつも割り勘だけど、ほかの女の子にはいつも奢っているの?」と聞いてみた。すると彼は「うーん、相手によるけど、ベッドを共にしたら俺は絶対に奢らないね」と言う。私が「何それ? どういうこと?」と驚いて尋ねると、彼は「だって、その女の子と寝ているのに俺が奢り続けたら、まるで彼女の体に対する代償を支払っているみたいじゃないか。そんなことできないよ」と言った。友人の言い分には納得はしたものの、それを聞いてアメリカでの割り勘の基準がますます不可解になったのは私だけだろうか?
第26話 「意志の強い女」
アメリカ人の独身女友達ジェシカは、フリーランスのプロデューサー。勤めていた制作会社から独立して既に10年という立派なキャリアを持つ彼女は、とても仕事ができるスマートで美しい女性だ。物怖じせずに自分の考えをはっきりと発言し、反論にもきちんと耳を傾け、物事を冷静沈着に素早く解決できる女性で、いつも堂々としている。
彼女と知り合ったのは今から4年ほど前。某企業が日本向けのプロモーションを行うことになり、私にPRビデオの台本執筆の仕事が回ってきた。早速、打ち合わせに行ったら、そのプロジェクトを取りまとめるプロデューサーがジェシカだったのだ。軽い冗談も交えながら、テキパキと場を仕切る彼女を見て、「わあ、かっこいいなあ、この人……」と、感動したことを覚えている。打ち合わせとは異なり、毎回意向が変わるクライアントの要求に対して何度も泣きが入りそうになる私を、ジェシカが激励しつつ的確にリードしてくれたので何とか無事にプロジェクトを終えることができた。それが縁で友達になったのだが、今でも私は弱気になる度に彼女に励ましてもらっている。私にとってジェシカは、優しい年上の独身女友達であると共に憧れの女性的存在なのだ。
独身とはいっても、ジェシカには一緒に暮らして6年になる、デイブという素敵なボーイフレンドがいる。いつ会ってもふたりはとても仲が良く、お互いがそれぞれの仕事や活動を応援し合いながら、プライベートな時間はベッタリ一緒に過ごすというスイートな生活を送っている。ジェシカのように仕事ができる女性が40歳近くなっても結婚していないと、「きっとキャリアのためにプライベートを犠牲にしてひとりで生きてきたのね……」と思われがちだが、彼女のプライベート・ライフはとても充実しているように見える。仕事以外ではデイブと過ごす時間を最優先にしているので、彼女を飲みに誘っても結構頻繁に「今夜はデイブとパーティーに出掛けるから、別の日にして」とか「今夜はデイブとDVDを見ながらリラックスする予定だから、飲みには行けないわ」などと言われてしまう。私のように、仕事以外には女友達と会うことしか予定がない生活を送っている人には、仕事とプライベートのバランスが取れているジェシカの生活はかなり羨ましいものである。
しかし、私のような凡人は、ジェシカとデイブの幸せそうな様子を見るたびに、「こんなに仲が良く、一緒に住んでいる期間も長いのに、なぜ結婚しないのかしら?」と、疑問に思ってしまう。実際、何年か前に私は自分より年上の彼女に向かって、「ねえ、ジェシカは結婚する気はないの?」と、素直に聞いてみたことがある。するとジェシカは、「私は結婚っていうものを信じていないの。だから一生、結婚はしないわ」と、きっぱり言い切った。私はかなり驚いて、なぜそう思うのかと突っ込んで尋ねると、彼女はこう説明してくれた。
「結婚して何年か経つと、“結婚した”という安心感からもともと他人同士だという事実を忘れて適度な緊張感を失ってしまう。結婚前までは平等に生活していたのに、結婚したら相手に頼るようになる人も多いわ。ほとんどの人達が、そういうことに対してさまざまな理由をつけて正当化するけれど、結局は相手を以前のようには愛せなくなって離婚したカップルが周囲に数え切れないほどいるでしょ。それに私は子供が欲しいと思わないから、子供のために籍を入れる必要もない。デイブはとても素敵な人で、彼のことを心から愛しているから今の状態が最高なの。彼も私のことをとても愛しているけれど、私と同じ理由で結婚はしたくないと思っているわ。だから、私たちは結婚しないのよ」
確かにアメリカには、たとえ一軒家まで一緒に購入しても結婚はしないというカップルや、宗教が異なるので結婚できないというカップル、何十年連れ添っていてもずっと籍は入れていない年配のカップルなど、とにかくいろんな人達がいる。だから、ジェシカとデイブのケースもそれほど珍しくはないと思うし、ジェシカ本人の説明も非常に明快でわかりやすい。もし、ほかの女性が同じセリフを言ったら、強がって格好をつけているだけだと思うかも知れないが、誰もが憧れるジェシカが言うとそうは聞こえない。
でも、私はジェシカのようには割り切れないと思う。彼女の考え自体は理解できるが、私なら人生を一緒に過ごしたいと思うほど相手を愛していたら、やっぱり結婚したいと思うだろう。だから、その気持ちをジェシカに伝えたら、彼女は笑顔で私に逆にこう尋ねてきた。
「そう思うのは、籍を入れないと愛が永遠に続かないような気がして不安だから?」
“結婚”という他人との約束をそういう風には考えたことがなかったので、それは私にとってなんだか衝撃的な質問だった。何と答えるべきか考えていると、ジェシカはいつもの優しい口調で、「人は人、私達は私達。あなたが結婚したいと思うなら、その気持ちを信じればいいのよ。私とデイブにとっては今の状態が一番幸せだと言っているだけなんだから」と、微笑んだ。
その後、相変わらずジェシカとデイブは一緒に暮らし続けて更に何年かが経ち、その間に私達の共通の友人が何人も結婚した。ジェシカとデイブと一緒に友人の結婚式に参列するたびに、私は凝りもせず、「ねえ、こんなにラブラブなのに本当に結婚しないの?」と尋ねたが(私もしつこいな)、その都度、彼女に「しないわ。結婚なんて全然意味がないもの」と、返され続けた。
そのジェシカが、先月とうとう40歳の誕生日を迎えた。私だったら超落ち込むだろうと予想される「独身にして40歳の誕生日」だが、ジェシカは数週間前からこの日をすごく楽しみにしていて、「ビッグ・フォーティーだもの。今年はめちゃめちゃ盛大に祝うわよ」と気合いを入れ、わざわざ友人達に自宅で開催するバースデー・パーティーの招待状まで郵送してきた。招待状には、「ジェシカの40歳の誕生日なので、みんなこの日はドレスアップして来てね! 楽しく過ごしましょう!」と書かれていた。いつもさっそうとしてかっこいい女は、40歳ごときではビビらないのだろう。私はますます彼女の強さに感心させられ、自分が40歳になる時には彼女のように振る舞えるよう、もっと自分に自信を持ちたいものだと、ひとりで気合いを入れ直した。
というわけで誕生日当日、ドレスアップしてジェシカとデイブの家に到着すると、かなり大勢の人が集っていた。ジェシカのご両親まで招待されていたので、久しぶりにお母様とご挨拶などをしているうちにパーティーが始まり、みんなでワインを飲みながら団らんしていると、誰かがグラスをカンカン!と鳴らし、場が一瞬静かになった。グラスを鳴らしたのは、ワインで既にいい感じにでき上がっていたジェシカのお父さんだった。そして、お父さんはいきなり大声でこうアナウンスしたのである。「みなさん、今日はジェシカのビッグ・フォーティーの誕生日に来てくれてどうもありがとう! そして、ジェシカとデイブの婚約パーティーにようこそ!」
言うまでもないが、それを聞いた私達は各自の耳を疑った。「オーマイガーッ!!」と、ほぼ全員が驚愕の声を発したほどのサプライズであった。だから、パーティーの参加者達が次々とカップルに駆け寄って祝福しているのに、私を含む女友達軍団だけは「ひえーっ!」「ちょっと、どうなってんのよ?」「予定外妊娠とか?」などと、かなり混乱していた。これまでジェシカが結婚に対してどう思っているのか嫌というほど聞かされてきたし、誰ひとり彼女から婚約の「こ」の字も聞いていなかったからだ。でも、「とにかく、よくわからないけど、おめでたいことだから」と体勢をたて直し、みんなでジェシカに祝福を言いに行った。
私達、女友達軍団が近づくと、ジェシカは頬を赤らめながら「サプラーイズ!」と、おどけてみせた。みんなから「本当にサプライズだよ」「何で隠してたわけ、まったく」などと言われながらも、愛情のこもった祝福の言葉とハグを受け取ると、ジェシカは「結婚式は5月なの。みんな招待するから絶対に来てね」と嬉しそうに言った。すると友人のベスが、「もちろん行くわよ。絶対結婚しない、結婚なんて人生の墓場だとまで言っていたあなたの結婚式だもの。見逃すわけないじゃない!」と、痛烈な一撃でサプライズのお返しをしてから、「で、なんで突然結婚することに決めたの?」と、単刀直入に尋ねた。
するとジェシカは「You can hate me(私のこと大嫌いになっていいわよ)」と、笑いながら前振りしてから、こう続けたのだ。「私、ずっと嘘をついていたの。デイブは私との結婚をずっと迷っていたのよ。だから私の方も結婚に全然興味がない振りをしていたわけ。だって情けないじゃない、私はこんなにイイ女なのにパートナーから何年も結婚を迷われているなんて(笑)。彼の気持ちが固まるのをバカみたいに6年も待ったのよ。だから突然結婚する気になったんじゃなくて、ようやく結婚するの(笑)」
婚約して初めて結婚に対する正直な気持ちを吐露した彼女を見て、私は驚きと共に「すごく可愛い人なんだなあ」と思って、ちょっと涙腺がゆるみそうになった。彼女のように素敵な独身女でも、友人にも言えないほど高いプライドや悩みを抱え、それを何とか乗り越えようと自分なりの方法でがんばり続けてきたのだ。みんなも同じように何かを感じたようで、ジェシカの話を聞いた瞬間に全員で彼女を囲んで“グループ・ハグ”をして(笑)、彼女の婚約をシャンパンで乾杯した。
それにしても、私も含めて誰ひとりジェシカの本心に何年も気付かなかったとは驚きだ。彼女の演技が完璧だったともいえるが、どんなに弱気になっても人前では一切泣きを入れず、自分が信じるポーズを貫き通したジェシカは本当に意志の強い女である。彼女の結婚を心から祝福したい。
第27話 「運転しなくてもいい女達」
シアトルには市内を走る電車や地下鉄がない。そのため短期間しか滞在しない留学生などを別にすれば、シアトルで生活する独身女に自家用車は必需品である。
日本と同様、アメリカでも車を所有するのはお金が掛かる。中古車を格安で購入するのは非常に手間の掛かる作業だし(普通の独身女にはディーラーから新車を購入する予算などない)、維持をするのも大変だ。法律で定められた保険や車両登録代なども毎年支払わなければならないし、定期的なガソリン代、駐車場代、オイル交換代に加えて修理費も掛かる。私は先日、走っている最中にあまりにも車体が揺れるので4年振りにタイヤを交換したのだが、セール品を選んだのに400ドルも請求されたので泣きそうになった。そのうえ、こうしてメンテナンスをしていても突然のアクシデント(鍵穴を壊されたり、車をぶつけられたり、レッカーされたり)が起これば、さらなる出費も掛かる。
しかも私は、車の運転をするのが大嫌いである。私に限らず、車の運転が嫌いでも自分のボロ車を所有している独身女性は私の周囲だけでもかなり大勢いる。みんな「嫌いだからと言って一生運転しなくて済むなら、どれほど気持ちがラクになるだろう」と嘆いているが、嘆いたところで車は自動的に走ってくれないので文句を言わずに自分で運転しているようだ。
「そんなに大変なら車なんて持たないで、いつも誰かに運転してもらえばいいじゃない?」と思うなら、あなたはきっと非常に恵まれた独身女性なのだろう。これほど無理してでも私達が中古車を所有している理由は、「できるだけ他人に迷惑を掛けずにこの街で暮らしたい」と思っているからだ。もし車がなければ、毎日の通勤や繁華街でのショッピングには市バスを利用し、お洒落して夜遊びに出掛ける時は、その都度タクシーを利用すればいいだろう。普段の食料品の買い物も数日ごとに持てる分だけ少しずつ買えばいい。でも、米や瓶詰めの調味料など重い食料品の買い出しや、中古家具や電化製品など配達してもらえない大きな品物の売買、バスが走っていないような不便で遠い場所へ行く時などには、どうしても車が必要になる。つまり、車がないとちょっとしたことで他人に助けを求める機会が山のように出てしまうので、その都度レンタカーを借りるよりは安いはずだと信じて、嫌々ながらも車を所有しているのである。
車を所有していなくても、何でも面倒を見てくれる優しいボーイフレンドか伴侶がいれば、「お願いね!」というひと言で車を出してくれるだろう。しかし、パートナーがいない独身女は、何でも自分で何とかしなければならない。自分の用事なのに、いつも友人に車を出してもらう訳にはいかないのだ。友人の車はタダではない。車を出せばガソリン代も掛かるし、マイレージも増えるし、何と言っても友人の時間を頂戴することになる。だから、私達のような独身女がシアトルで車を所有している理由は決して“趣味や娯楽やステイタス”ではなく、極端な言い方をすれば“大切な友達を失わずに自分で自分の世話をするためのサバイバル用具”なのだ。
でも、シアトルには「自分の出費は気になるが、他人の出費は全然気にならない」という独身女性もたくさんいる。しかも、なぜかそういう輩の多くが日本人だったりする(笑)。彼女達は大概の場合、車が必要になっても不思議なことに「決してレンタカー屋には電話しない」。今どきのレンタカー屋は電話1本で自宅まで車を持って来てくれるサービスもあるのに、“レンタカー”という選択肢は彼女達の頭の中には最初からないらしい。車が必要な時に、まず彼女達が電話を掛ける相手はレンタカー屋でもタクシー会社でもなく親切な男友達。そして運悪くその男達が捕まらない時の次なる選択肢が“親切な同胞の独身女”なのだ。
さらに不思議なのは、こういう輩に限って決して自分から積極的に相手にガソリン代をオファーしたり、手間と時間とお金を掛けさせた御礼として食事をご馳走したりしない。一度、私の女友達のひとりが、ライド(車に同乗させて欲しいという意)を頼んで来た日本人の女の子に対して「私はちょっと都合が悪いから、○○レンタカーに電話してみたら? 他社よりも安いはずだから」と言ったら、その子はとても憤慨して「レンタカーなんて高くて借りられないわ! 友達の車ならタダだからお願いしているのに、そんなこと言うなんてヒドくない?」と言われたそうだが、とんでもない話だ。ヒドイのはそっちである。私達の車はタダではない。私達が自分でガソリン代や税金や車両保険などを払っているから「あんたにはタダのように見えるだけ」なのだ。
“彼女達”が往々にして同様のトリックを使用する点も見逃せない。車を出してもらいたい相手に電話を掛ける際、大抵の場合、まずは「久しぶり! 今、何してるのぉ?」とか「突然ごめ~ん、今ちょっと大丈夫?」と極端に明るい声で聞いてくる。自分が電話を掛けて来た理由を相手に話す前に、相手が今自宅にいてくつろいでいるのか、暇そうなのかを先にチェックするのだ。こう聞かれた際、素直に「別に、大丈夫よ」と相手の気持ちを気遣って本当は忙しいのに忙しくないと言ったり、「暇だからDVDを見てるんだ」などと“今、本当にしていること”を言ったらおしまいだ。それを言ってしまったら、「えっ、そうなのぉ? じゃあ、今から○○に行かない?」「それなら、ちょっとお願いしてもいいかなぁ?」と不意をつかれて、とっさには断れない状況に追い込まれてしまうからである。
こういう状況下に置かれると、私の場合、ほとんど断れない。もし断ったら、自分が意地悪な女のような気がするので無理してでも車を出してしまうのだ。基本的にいざというところで結構気が弱いので、だからこそ頻繁に頼まれてしまうのだと思う(笑)。そして自分の貴重な時間とお金を浪費した後、自分のバカさ加減に対して落ち込むのである。
でも、「断ったら自分が意地悪な女のような気がするから断れない」と思う女は私だけではないらしい。先日、日本人の女友達を大勢呼んで鍋パーティーをした時にこの話題を振ったら、全員同感だと言っていた。なかには「やりたくないのに断れない自分が嫌で、フラストレーションがたまって仕方がない!」と言い、そのため大型バイクの免許を取って車を処分しようかということを本気で考えているという女までいた。バイクなら自分と荷物しか乗れないからという理由らしいが、それも一案である(でも雨が降ったら危険だし、バイクで家具は運べない)。
基本的に、車を所有しない独身女達は、どうも車を所有する独身女性達の金銭的な負担や気持ちがなかなか理解できないらしい。彼女達は、まるで私達車所有組を「自分のボーイフレンドか夫と間違えているのではないか?」というような行動をしばしば取る。前述した鍋パーティーの際に、みんなから「今までの不愉快な経験談」をたくさん聞いたので少し紹介しよう。
まず、弁護士秘書の恵子によると、恵子の近所に住んでいる車を持たないA子は、恵子に車を頼む際、必ず「何時ごろ迎えに来てくれる?」と聞くそうだ。恵子が車で家まで迎えに来てくれるのが当然だと思っているわけだが、A子の家は恵子のアパートから5ブロックしか離れていない一方通行の突き当たりにある。つまり迎えに行くと車をバックで走らせなければならず、すごく手間取る立地らしい。恵子は毎回A子のそのセリフを聞くたびに、「自分が人に用事をお願いしてるんだから、5ブロックくらい歩いて私の駐車場まで来いよ、ボケッ!」と言いたいたくなるのだが、「大人だからとてもそんなことは正直には言えない」らしい。それにしても、頼んでいるA子の方はなぜこんな簡単な気が回せないのだろうか?
また、某企業の広報部で働く絵美の友人B子の場合は、いつも絵美と約束する際に「じゃあ、家の前に着いたら下から呼んでね。すぐ降りていくから」と言うそうだ。絵美は、彼女のこのB子の行為が「小さなことだけれど、何だかアッシー(古い!)のように扱われているみたいでムカつく」という。自分なら相手がわざわざ時間とお金を掛けて迎えに来てくれるのだから、「相手を待たせる失礼がないように、せめて車が到着するよりも先に家の前で待っていよう」という気遣いをするからだ。私達も交代で仲間に車を出してもらう時は、「近くに来たら携帯から電話して。外に出て待っているから」というのが普通だ。でもB子のような女性達は、そうは言わないのである。私も同様の経験が数限りなくあるが、私達は彼女らの旦那でも運転手でもないのだから、女友達に迎えに来てもらうなら、このくらいの気配りは見せるべきだと思う。
某社事務職の朋子の話はもっと具体的だ。以前、朋子が友人C子の提案で、カナダに近い遠くのアウトレット・モールまで一緒に出掛けた時、「申し訳ないけれど、ガス代の一部を少し払ってもらってもいいかな?」と言ったら、C子にものすごく驚かれたそうだ。朋子にすればC子が自分の方から「いつも車を出してもらっているから、今日は私が満タンにするわ」ぐらいは言ってくれると期待したらしいが、結局10ドル支払ってくれただけだったらしい。しかし後日になってC子が「朋子は一緒に出掛けたのに私にガス代を請求してきたので驚いたわ」と周囲に言っていたことが判明し、超落ち込んだという。
車所有者側から見ると、C子こそ「一緒に出掛けたのだから」ガス代の一部を積極的に払うべきだと思うのだが、なぜか朋子のように自分から一部負担をお願いした人の方が「セコい奴」と思われる傾向が世間にはあると思う。なぜ頼まれる側の私達の方が、正直にガス代を少し負担して欲しいと言って不愉快な思いをしなければならないのだろうか? 親切でまともな人間の方が損をする仕組みなのだろうか? それとも、相手の負担額や運転する側の気持ちになど、「気付かない振りをする方が賢い」のだろうか?
日本と異なり、シアトルでは車の免許は2日で取れる(教習所が必須でないから)。10ドル出して簡単な○×式の学科テストと路上テスト(近所をひと回りするだけ)を受け、25ドルの免許代を払いさえすれば、即免許がもらえるのだ。しかし前述のC子は免許を持っていない。朋子より稼いでいるにもかかわらず、「車を所有するとお金と手間が掛かるし、環境にも悪いから」という理由で車を持たない主義らしい。素晴らしい理由だし個人の意思を尊重もしたい。だが、そんなことを言っていながらC子はとても頻繁に他人の車を当てにするので、これは主義ではなく便宜上の理由だと私達は見ている。
そういうわけで私は、電車や地下鉄が網羅されている土地以外のアメリカに住むならば、誰もが一度は人生経験として中古車を所有してみるべきだと思うのだ。そうすれば少なくても相手の状況を気遣えるようになるだろう。例えば、ちょっと車を出してもらったなら運転手のコーヒー代を奢るとか、食事をしたらチップだけでも運転手には払わせないとか、迎えに来てもらうなら家の前で待っているとか、そういう小さな配慮ひとつでも運転手側は「車を出してあげてよかった」と嬉しくなるものなのだ。
それとも、私達も車を処分して“車を運転しなくてもいい女”になった方がもっと幸せになれるかも知れない。不愉快な思いをすることもないだろうし、少なくても、こんなことをいちいち考えなくても済むだろう。
第28話 「ヘザーが泣いたプロポーズ」
“天はニ物を与えず”とはよく言ったもので、このことわざはほとんどの人に当てはまる。しかし残念ながら世の中はそれほど公平ではないので(笑)、たまに一生懸命考えてみても“持っていないものが見当たらない人”というのがいたりする。私の女友達のヘザーは、まさにそういう女だ。
ヘザーは“美人なのに性格も良くてバカでもない”という、かなり稀なタイプの独身女である。シアトルの某有名企業に勤務し、ベルタウンの高級コンドに住み、愛車は新車のミニ・クーパー。お金持ちのお嬢様なので、独身のひとり暮らしでもお金には全然困っていない。性格はいつも明るく、落ち込んでいる友人がいたらすぐ飛んでいくような姉御肌。また、頭の回転が速く話題も豊富なうえ、流行にも敏感で洋服やインテリアの趣味も良い。さらに道ですれ違った男性が思わず振り返るほど美しい顔立ちと抜群のスタイルを持ち、胸のサイズなんてEカップもある。フー(溜息)。
1年ほど前、共通の男友達から初めてヘザーを紹介された瞬間、私は彼女の美しさと溢れ出るオーラの強さに圧倒されてしまい、「きっと欲しい物をすべて難なく手に入れてきた女なのだろう」と少々引き気味だったが、一緒に飲んだら超面白い人だったので初日からすっかり意気投合してしまった。人は見かけによらないとは良く言ったものだ。私が初日の感触から想像した通り、ヘザーは内陸地方都市出身で非常に宗教色の強い白人上流家庭に生まれ、周囲の誰からも愛されて育ち、成績優秀で通した有名私立校ではチア・リーダー、プロムではプロム・クイーン、大学時代は白人フラタニティーの代表を務めたという、まさにハリウッド映画が描く“オール・アメリカン・ガール”を地で行く経歴を持っている。もし友人ではなければ、自分が卑屈になるのを防ぐためにも、できれば近くに寄りたくない経歴である(笑)。
そんなヘザーは、言うまでもないが“超”がつくほどズバ抜けて男にモテる。ちゃんとしたホテルのバー(ミート・マーケット※ではない)やレストランでも、たった数時間の間に何人もの男達がヘザーに電話番号を尋ねてくる。ヘザーと一緒に出掛け始めた頃はおもしろがって男の数をカウントしていた私も、途中から数えるのがバカらしくなってしまったほどだ。
一般的に“ものすごく男にモテる美しい女”というのは、男性には愛想が良くても同性の前では性格が悪く、周囲の女性達から嫌われている場合が多い。中には女友達と大事な話をするために一緒に出掛けているのに、男性からのアプローチがあると連れの女友達をそっちのけで男性に対応してしまう女もいる。通常こういう女には“まともな女友達”がほとんどいない(ちなみに、モテる女と一緒に行動しておこぼれを授かろうと考えるような最低の女のことを“まともな女”とは言わない)。これに反してヘザーは女友達と出掛けている時に男性から誘われても思わせぶりな態度など一切出さずに“きっぱり”と断り、連れの女性に対して失礼な態度を見せない。これだけが理由だとは言わないが(でも、きっと大きな理由のひとつ)、ヘザーは驚くほど大勢の女友達を持ち、みんなから好かれている。きっと見えないところで人並み以上に努力しているのだろうが、私のような疑い深い人間ですら魅了してしまうのだから本当にスーパーな女である。
でも、これほどスーパーな彼女でも「喉から手が出るほど欲しいものがある」ということを知ったのは、先日開催されたヘザーの30歳のバースデー・パーティーでのことだった。それは「愛するボーイフレンドとの結婚」である。何もかも手に入れているように見えるヘザーが、こんな月並みな願望を抱いていると知り私は少し驚いたが、ヘザーは基本的に“オール・アメリカン・ガール”だ。彼女にとって結婚式とは人生最大のイベントであり、主婦になって子育てに専念し、地域や教会のボランティア活動に精を出す美しい母になるのが夢なのだ。しかも30歳になっても独身だとは、彼女が少女の頃に描いた夢には入っていなかった。
こんなにモテるヘザーがまだ独身なのは、ものすごく愛しているボーイフレンドがいるからだ。つまり、彼女が喉から手が出るほど欲しいものとは、その彼からのプロポーズである。彼女が4年前から付き合っているインド人のボーイフレンド、スレーシュはとてもハンサムな男性で、アメリカの有名大学を首席で卒業後、シアトル在住のエリート・インド人の例に漏れず超有名IT企業M社のエンジニアとして採用され、現在も同社の正社員として働いている。頭が良く経済的にも安定していて、優しくて思いやりがあり、いつも物静かながら笑顔を絶やさないスレーシュをヘザーは心から愛しており、彼も同様に心からヘザーを愛している。だが、スレーシュは一向にヘザーにプロポーズする気配を見せないというのだ。
なぜスレーシュは、とうとう30歳の大台を迎えた美しいヘザーにいつまでもプロポーズしないのだろうか? それはふたりの宗教が異なるからである。ヒンズー教のスレーシュと、敬虔なプロテスタントであるヘザーの両親が共にふたりの結婚の可能性に対して非常に難色を示しており、真剣に話を聞いてくれない状態だそうだ。ヘザーは彼が双方の両親を説得してくれることを期待して、彼からのプロポーズを毎日待ち続けているそうだが、スレーシュの態度がまだはっきりしないらしい。ヘザーの気持ちは「何があってもスレーシュを取る」と既に決まっているのだが、スレーシュの方は両親への忠誠心や宗教の大切さと、ヘザーとの新しい未来への可能性の狭間で悩んでいるように見えるという。
アメリカのように多種の宗教が入り交じった国で暮らしていると異宗教間のトラブルを抱える人たちの話をよく聞くが、こればかりは当人でないと本当の意味での問題の深さは理解できないように思う。ヘザーのバースデー・パーティーは誕生日前夜に開催されたのだが、彼女は「30歳を迎えたからといって、彼が両親を説得できる可能性が高くなるとは思えない。こんなに愛しているのに、このまま一生彼とは結婚できなかいかもしれない」と言って、珍しく少し落ち込み気味だった。何でも手に入れているように見えるヘザーても、他人では助けてあげられないような大問題を抱えていることを知って私はとても気の毒になった(人の心配をしていられる立場ではないのだが)。もしかしたら世の中は私が思っている以上にみんなに公平なのかも知れない。
ヘザーとスレーシュはパーティーの翌日、30歳の誕生日をふたりだけで祝うためにラスベガスへ旅出った。このラスベガス旅行はスレーシュからの誕生日のプレゼントだった。彼が企画した3泊4日の旅は、宿泊するホテルも予約してある高級レストランもすべてヘザーには“サプライズ”。彼女が事前に伝えられたことは「飛び切り素敵なドレスと靴をいくつか持って来てね」ということだけだったそうだ。これをヘザーから聞いた友人一同がホッとしたことは言うまでもない。こんな映画のような完璧なお膳立てが“プロポーズのための旅”でなかったら、一体何の旅だと言うのだろうか。スレーシュは間違いなくこの旅行中に彼女にプロポーズするはずだ。女友達はみんな期待に胸を膨らませてヘザーをラスベガスへ送り出した。
数日後、シアトルに戻って来たヘザーを見た瞬間、「この女のことを少しでも心配して損した!」と思ったのは私だけではなかったはずだ。キラキラと輝くような満面の笑顔で私達の前に現れたヘザーの左薬指には、目がくらむほど大きなダイヤモンドが輝いていた。その指輪をはめた左手を胸に当てながら、ヘザーが私達に語ってくれたスレーシュからのプロポーズはこうである。
ラスベガスに到着すると予想通り高級ホテルのスイート・ルームが用意されていて、スレーシュはヘザーを毎日素敵な高級レストランへ連れて行ってくれたそうだ。ギャンブルはしないし、いつも物静かな彼がこんなゴージャスな旅をプランしてくれたのは初めてだったのでヘザーはとても嬉しかった。でも、スレーシュは誕生日の直前に彼の両親と話し合いをしたはずなのにヘザーには結果を教えてくれなかったので、不安と期待の両方で終始落ち着かなかったそうだ。そして誕生日の当日、もちろんヘザーはプレゼントに婚約指輪がもらえることを期待していた。でも1日中、彼のポケットから小さな箱が出て来ることはなかった。そして翌日もふたりでロマンティックな1日を過ごした。スレーシュがどこか落ち着かない様子だったので「今日こそプロポーズか」と1日中期待し続けたそうだが、またしても何も起こらなかった。
そしてその翌日、ラスベガスでの最後のディナーの席でのこと。この時点でヘザーは「ここまで彼が言い出さないということは、やはり親が反対する女性とは結婚できないことを私に伝えるつもりかも知れない」と半分諦めかけていた。スレーシュが終始そわそわしているのも、それをヘザーに伝えるタイミングを待っているだけかも知れない。ふたりは何とも言えないテンションを抱えながら食事を始めたが、スレーシュはいつもより妙にゆっくり食べている。なんとかメインディッシュを食べ終わると、デザート・メニューが運ばれてきた。体重を気にしているヘザーは、ウエイターが何度も勧める本日のデザートを断り、代わりに食後酒のメニューを持ってこさせた。スレーシュにもわかるようにヘザーが食後酒のスペシャルの銘柄を読み上げていると、最後の銘柄のところで彼女の目が止まった。そこには「ヘザー、僕と結婚してください」と書かれていたのである。ヘザーの目に思わず涙が溢れ、この部分を声を出して読み上げることができなかったのは言うまでもない。ヘザーが泣きながらスレーシュの顔を見ると、彼も緊張で額に汗をかきながら少し震えていたそうだ。ヘザーが「イエス、イエス、イエス!」と言って彼に抱きつくと、彼は感動して目に涙をためながら「ありがとう。絶対に幸せにするから」と言い、彼の給料の3ヵ月分以上もする高価なダイヤモンドの婚約指輪をヘザーにプレゼントしてくれた。事情を知っていたレストランの従業員達から祝福の拍手を受けながら、ヘザーは心から神様に感謝したとういう。
スレーシュがヘザーが絶対にデザートを断って食後酒を頼むことや、メニューを自分のために読み上げる癖をすべて把握していたのも可愛いが、一番いいニュースは宗教が異なる双方の両親がようやくふたりの結婚を納得してくれたことである。ふたりは来年の春、伝統的なヒンズー教の結婚式を彼の実家のそばで行い、その直後に伝統的なプロテスタントの結婚式を彼女の実家のそばで行うことが決まった。伝統的な結婚式に憧れていたヘザーは結果的に結婚式を2回も挙げられることになったのだから、めでたしめでたしである。でも、このヘザーの話を最後まで聞いた後、私はこう思った。やっぱり世の中にはすべてを手に入れられる女とそうでない女が存在し、残念ながら世の中はそれほど公平ではないのだと(笑)。
※meat marketと書き、肉体関係のみが目当てのナンパ・スポットを指す俗語。
特別企画:独身女座談会
「男と女がくっつくには何が必要?」

秋野未知は多忙につき、執筆をお休み中。
今回は特別企画として、シアトルの独身女を集めた座談会をお送りします。
座談会メンバー紹介
A子:シアトル在住の会社員。30過ぎても占い好きで夢見がち。
B美:同じくシアトル在住の30代会社員。酒とタバコは欠かせない毎日。
C江:大学を卒業したばかりの20代。彼氏はいるが、遠距離恋愛中。
友達→恋人の可能性
| A子: | どうしたら、彼氏ができるんだろう。 | |
| B美: | それは……永遠のテーマだね。 | |
| A子: | 出会いが全くないわけでもないんだよね、男の友達だって結構いるし。 | |
| C江: | 友達から恋人の関係になるのが難しいんだよね。 | |
| B美: | そう言われると、そうかも。 | |
| A子: | やっぱり、何かきっかけがないとダメなんじゃない? | |
| B美: | 例えば? | |
| A子: | どちらかが告白するとか。 | |
| C江: | まず、告白するほどの情熱が生まれないとね。 | |
| B美: | 友達ってことは、「一緒に過ごして楽しい」というような好意はお互い持ってるわけだけど、告白するほどではない、と。 | |
| C江: | コクって友達ですらなくなるのも怖くない? | |
| A子: | 相手に好きな人がいるのかを聞くところから始まって、自分に対する気持ちがどの程度かも知らないといけないし。 | |
| B美: | それを探るのって、またビミョー。直接的な言い方だと、まるで自分が相手に気があると思われそうじゃない? 実際はまだそこまでじゃないのに。 | |
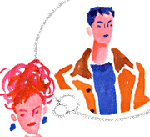
出会いはどこに?
| A子: | C江はどうやって今の彼と知り合ったの? | |
| C江: | 向こうからナンパされたの。 | |
| B美: | えー、そうなの。 | |
| A子: | でも、それで長く続いてるんだから、人生わからないよね。D子だって、そうじゃない。 | |
| B美: | そっか、そういうケースは多いのかな。 | |
| A子: | 向こうに好意があることが前提だから、ある意味わかりやすいよね。 | |
| C江: | 誘いに乗るか、乗らないか。“探り合う”必要がない(笑) | |
| B美: | うーん、私はナンパはダメ。かと言って、今の仕事では出会いがないし、ネットはもうこりごりだし……。 | |
| A子: | 私もネットはイヤだ~! ろくな男いないよ。 | |
| C江: | みんな、実はネットを利用してるんだね。無料サイトだったからじゃない? 有料なところだったら、もっと違うのかも。それなりに本気の人達が利用してるわけだし。 | |
| B美: | やっぱ、自然な出会いって無理? | |
| A子: | この前『an・an』の特集で「“運命の恋”の手に入れ方」っていうのがあって、思わず買っちゃった。 | |
| B美: | そういうの読んでも、いつもピンと来ないなー。 | |
| A子: | 2005年下半期の恋愛占いもあったよ。 | |
| C江: | そうだ、『an・an』の上半期占いで、B美は4月に出会いがあるんじゃなかった? | |
| B美: | 全く、ナシ! っていうか忘れてた。 | |
| A子: | そんなもんだよね。でも、なんだかんだ言って占いは読んじゃう。部屋に風水も取り入れたし。 | |
| B美: | 恋愛運を上げる色は、ピンクでしょ? 私もマニキュア塗ってるよ、ホラ。 | |
| C江: | それにしては、ふたりともあんまり効果ないね(笑)。 | |

結婚を避ける男達
| B美: | なんで私の周りには、結婚に興味ない男しかいないわけ? | |
| A子: | 将来が全く見えない男だと、30過ぎてつき合うにはキツいよね。 | |
| B美: | 毎日のように遊んだり、飲んだりしてる友達はいるけど、シモネタばっか。バーで引っ掛けた女との一夜を細かく描写されてもねえ。 | |
| C江: | 単にB美がおっさん過ぎるんじゃないの? | |
| A子: | 言えてる(笑)。そこまで“男友達”になっちゃうと、恋愛に進むのは難しいかもね。 | |
| B美: | 彼、一生結婚しないって豪語してるけど、今のうちだけ。50過ぎたら絶対後悔するって! | |
| A子: | 特にアメリカではそういう人多いのかな。 | |
| C江: | 人によるとは思うけど。日本にいる人に比べたら、多そうな気はする。離婚も結構多い社会だから、結婚に対する思い入れも弱くなってるのかもね。 | |
| A子: | 結婚を考えていない人とは、もしつき合うことになっても、全然彼女扱いしてくれないとか、都合のいい女になってしまうとか、そういうダラダラの関係になってしまいそう。 | |
| B美: | 私はそういうのがイヤだから、前の彼と別れたのよ! | |
| C江: | まあ、そういう関係でも結局は結婚してる人もいるけどね。 | |
| A子: | 逆に20代の輝かしい青春時代をフイにしてる人もいるんじゃない? 男はいいけど、女は出産を考えればタイム・リミットがあるから、いつまでも待てないよ。 | |
| B美: | 1年以上つき合って、結婚したらしばらくふたりで新婚生活を楽しみたいから……。逆算したら、今年中に誰か見つけないといけないじゃん! | |
| A子: | もう、2005年も半分過ぎたしね。 | |
| C江: | 来年の今ごろも同じこと言ってそうでコワい……。 | |
第29話 「愛をとるか、金をとるか?」
私達の年齢(30歳代)の独身女になると、20代のころから毎日仕事を続けているので、ブランドもので全身を固められるほど裕福ではなくても、翌月の家賃を払えないほど貧乏でもないという人が多いと思う。もちろん一軒家の購入とか、ゴージャスな海外旅行とか、素敵な伴侶など、簡単には手に入らないものは山のようにあるが、“自分ひとり”の生活費に関しては他人に迷惑を掛けずに自分の経済力でテイクケアできている人がほとんどではないだろうか。
そんな30代の独身女友達と集っておしゃべりをする際、このところよく話題に上るのが「今月のダメ男くん」の話である。仕事を中心とした近況報告が終わり、だんだん場が盛り上がってくると、たいてい誰かが「そういえば先日、結構いいかなって思った出会いがあったんだけど……」と切り出す。「あったんだけど……」と聞いた時点で過去形だとわかるので、「でも、またダメ男くんだったの?」とすかさず誰かが切り返すのがお決まりになっているほどだ。
ダメ男くんの定義は非常に多岐に及ぶので「○○ならダメ男くん」とは言い切り難い。たとえば今まで私を含めた周囲の女友達が出会ったダメ男くん達には、ものすごくスイートな人だと思ったのに実は長年連れ添っている妻がいたとか、優しくて誠実な人だと思ったのに“母違い”の子供が5人もいたとか、会社には通わずフリーランスで仕事をしていると思ったらシュガー・ママがいたとか、トレンディーで夜遊び好きな人だと思ったらアルコール中毒だったとか、超明るくパワフルな弁護士だと思ったら万年コカイン中毒だったなど、驚くほどいろんな人がいた。結婚を前提にお付き合いしたいと思っている女性にとっては、不倫の事実を隠されていたとか(アメリカ人にも多いんだな、これが)、何かの中毒(これは意外にもエリートに多い)というケースは基本的に最初からお話にならないので「それは早く別れておいて良かった」ということになる。でもたとえば、好きになった相手に現在養育義務のある子供が大勢いる場合や、今日現在安定した収入がない男性の場合は、一概に「即、ダメ男くん」とは決定し難い。子供の有無に関しては、現在の彼女と出会う前に起きたことだし、現時点で安定した収入がなくても来月には状況が変わるかも知れないからだ。だから、こういうケースに関しては当事者を含めた周囲が「この相手はダメ男くんか否か?」ということ、つまり「関係をコミットメントまで進めても大丈夫な相手なのか?」ということに関して熱い意見を戦わせることになる。
最近、周囲が熱くなったのはN子のケースである。N子はシアトルのダウンタウンにある某社にてフルタイムで働きながら、仕事の後に週3回ほどアメリカ人にダンスを教えている非常にアクティブな37歳だ。「どうしようもないほど好き」という気持ちになれる相手を求めて自分の感情に妥協せず、自然に“時”がくるのを待ち続けたN子に数年ぶりにようやく彼ができて(ワンダフル!)、半年ほど前からその彼と一緒に暮らし始めた。男と暮らし始めた当初というのは誰でもそうだと思うが、何だかんだと毎日忙しくて“完璧にフリー”だった時とまったく同じようには行動できなくなる。だから、N子が久しぶりに飲み会に参加したので、みんなとても盛り上がった。
N子のアメリカ人の彼、レイはアーティスト(画家)で、N子とは毎月シアトルで開催されている「ギャラリー・ウォーク」で偶然知り合い、ほぼ電撃的に恋に落ちた。当時N子はレイのことを、とても素敵な絵を描くセンシティブで優しい人で、自分の作品を描く以外に絵画教室のようなところで教えていると誇らし気に話していた。その事実は半年以上一緒に暮らしていた今でも変わっておらず、レイは相変わらず毎日N子に対してとてもスイートらしい。でも、その日のN子は「どうしようもなく女友達と話したい!」と、ちょっと悩んでいる様子だった。
N子は、「毎日、心から愛する人と生活できて幸せだが、信じられないほど彼が貧乏なので、結婚を前提に付き合っても大丈夫だろうか」と悩んでいた。レイは個展を開催して自分の作品が売れない限り教室からの収入に頼るしかないのだが、教室の収入は画材代くらいしかまかなえないことが一緒に生活して初めてわかった。一緒に住み始めてからというもの、家賃も光熱費も食費も電話代もガソリン代も駐車場代も洋服代も全部N子が支払っており、甘いふたりの生活と引き換えに出て行くお金が今までの2倍以上になったという現実と、元来描いていた理想とのギャップでフラストレーションがたまっているらしいのだ。
N子は、「40歳目前という年齢で貯金が一銭もなく収入も学生バイト並みの彼が、今までどうやって生活してきたのかわからない……」と言って苦笑いをしていたが、きっと過去に作品が売れ続けた時期があったか、以前はいいスポンサーがついていたのだろう。アーティストには収入のアップ&ダウンがつきものだ。売れる時もあれば、売れない時もある。だからN子も「もう少し待てばまた売れるかも知れない。でも、いつまで待てばいいのか。自分ひとりだったら何とかなるという今の収入で、貯金を食いつぶしながらいつまで彼を支えていけるのだろうか……」と悩んでいるのである。
これを聞いた周囲は一瞬にして熱くなった。女友達たちは各々瞬間的に「残念! それはダメ男くんの典型かもしれない」「自分の生活で精一杯なのに、どうやってもうひとり養うのよ?」「かなり厳しいね。だってこの年齢で貯金なし、収入なし、保険なしだと、今から事態が急に好転するとは思えないよ」「さらなるお金を使う前に早く別れた方がいいかもよ」などと、好き勝手にバンバン発言した。しかし、N子のさらなる話を聞いて、そんな短絡的にN子に対してアドバイスなどできないことに全員が気付いたのだ。
N子は今まで弁護士やITデベロッパーや医者など“俗にいうエリート”と言われる男性と数々付き合いながら、結局すべて自分から別れている。そのN子が、「レイは確かにお金はないけど、今まで付き合った誰よりも優しくて思いやりがあって、私のことを毎日ものすごく愛してくれるのよね。たとえば、絵画教室でお金が入った日は必ず花束やラブリーなカードをくれるし、家事はいつも全部一緒にやってくれたり、毎晩長い時間を掛けて私の肩をもんでくれたりするわけ。つまりね、経済的な問題さえなければ私の方から今すぐプロポーズしたいくらい彼のことが好きなのよ……」と言うのだ。
確かに“多くの男性”は女性と付き合い始めた当初はそういうことをしても、一緒に暮らし始めてしばらく経つと徐々にそういう回数が減っていき、しまいには記念日とか誕生日とか以外は特別なことをしてくれなくなる。でもレイは常にそういう配慮してくれる上に、「N子が世界中で一番きれいだよ」と毎日15回くらい言ってくれるらしい。「花やカードをくれるなら貸している金を先に返してよ、と思うんだけど(笑)。やっぱりうれしいじゃない? こんなにスイートなことをし続けてくれる人と付き合ったことがないからかも知れないけど、正直言ってメチャメチャ幸せなのよ……。だから悩んでいるんだけどさ」と何だかとても幸せそうに話すN子を見た周囲は、一斉にため息をつきながらこう言った。「Gosh, I wish I had a guy like him!(もしそんな男がいるならば、私もそういう男と付き合いたい!)」。
つまり、N子のケースは「レイはダメ男くんなのか」という問題ではなく、「愛をとるべきか、経済的な安定を求めるべきなのか?」という問題なのだ。その場にいた独身女達が揃って、N子に「きちんと考えた方がいい」的な意見はしつつも「やっぱり情熱的な恋愛ってとっても素敵」と思ったのは、この歳になるまでこれだけ相手を選んできたのだから、「できることなら情熱的な恋愛をして、その相手と結婚したい」と、みんなが心のどこかでそう望んでいるからだと思う。
「愛をとるか、金をとるか?」という問題は、そういう条件下にある彼との結婚を考える独身女性にとっては究極に難しい選択であろう。なぜなら、きっと誰もが「できることなら両方欲しい!」と思っているはずだからだ(笑)。
第30話 「私の夏」
取材ライターという私の仕事は、自分が取材させていただく相手や場所へ自分から出向くのが基本である。そして、なぜか私の仕事は冬は妙に暇なのに、夏になるといきなり忙しくなり、ほとんどシアトル以外の土地に出掛けている状態が続く。今年も5月くらいから週に1日休むことが難しくなり、もう8月末だというのに休みなしで働く日が続いている。夏の間に冬の穴を埋めているわけだから、“アリとキリギリス状態”と言えばいいのだろうか。
以前にも書いたが、私は基本的に「売れっ子のライターさんが行きたがらない取材先」に行くことが多い。「こんなに良い季節にへんぴな場所なんて行きたくない」と、夏は特にみんなが仕事内容を選ぶから、来るものはすべて引き受ける私に仕事が回ってくるのかも知れないと考えたこともあるが、真相は不明である。シアトルは夏が短いので、美しい夏の間はみんなとてもアクティブに行動する(恋の季節とも言える)が、私はほとんどシアトルにいないので、少ないチャンスをさらに遠ざけてしまうという非常に残念な生活パターンに陥っている。
出張が続くことで一番辛いのは、女友達と全く遊べないことだ。Eメールくらいはするが、いつものように一緒に食事をしたり、飲みに行ったり、ショッピングやパーティーに行ったりという楽しいことが全然できない。夏だというのに大好きなBBQパーティーにも参加できない。よって、みんなの近況をネタに原稿を書くことができず、今月は私の仕事事情を紹介することになったわけだ(泣)。
仕事の話になると、よく「秋野さんはいいわねえ。仕事でいろんなところへ行けて」と言われる。しかし私の場合は「仕事で数ヵ月ほとんどシアトルにいなかった」と言っても、「編集者が全部お膳立てをしてくれて、ニューヨークやロサンゼルスに行って昼間から優雅にカクテルを飲みながら取材」ができる身分ではない。高級スパやレストラン取材のような「おいしい仕事」も非常に少ない(誰かください、そういう仕事!)。大抵、私が取材に行かされる場所は、例えばユタ州の某飛行場から自分でレンタカーを5時間も運転しなければ到着しない牧場とか、普通なら行く用事がないと思われるセントルイスのギャング街とか、12人くらいしか乗れない小型プロペラ機に乗り換えた上に車で数時間走ったところにある鬱病になりそうな街とか、「何だ、ここは~!?」と思うような場所ばかりである。そんなところで、都会に住む独身女がうっとりするような素敵な出会いがあるわけがない。
田舎の安ホテルのロビーですれ違う人達と言えば、腕に女の名前のタトゥーを入れた長距離トラック・ドライバーのおっさん、椅子からはみ出すほど太った老夫婦、誰とも挨拶さえ交わさない“訳あり気な”旅行者、行儀の悪い子供達を大勢連れた大家族などばかり。アメリカの田舎を舞台にしたロード・ムービーの脚本を書くしかないような、シュールな設定の安ホテルに長期滞在をする私の実情など知らないから「秋野さんはいいわね~」と言う人が多いのだろうが、この切ない程の実情を知ったら、きっと誰ひとり、うらやましがらないと思う(笑)。
しかも、早朝から日没まで取材や撮影をして、夜にはその日の取材をまとめなければならず、同行のカメラマンさんはフィルムの整理をしなければならないので、カメラマンさんと一緒に飲みに繰り出すような時間もない。1日の仕事がすべて終わるのはほとんど夜中だし、たとえ時間があったとしても、自分ひとりでバーに行くのは苦手なので(結構小心者なのだ)、取材以外で夜に出歩くことは皆無である。安ホテルの部屋で女がひとり寝る前に安ワインを飲む図なんて想像しただけで悲しいが、私はそれを現実にやっているのだから(しかも最近はそれにも慣れてきた)、もう笑い飛ばすほかないのである。
「秋野はいろんな人を取材する仕事だから、普通の人より出会いの数が多いでしょ?」とも、よく言われる。確かにオフィスにこもって仕事をする人よりは、知らない人と出会う可能性は多いだろう。でも、取材先で自分の個人的なことを話すことはほとんどないし、取材時間は細かく決められているため、そんなことを話す時間も全然ない。しかも、私自身の好みや世界観とは全く異なる人と話すことが多い。たとえば、先日の取材先は性犯罪者専用の刑務所だった。取材内容は非常に興味深く、大勢の人に知ってもらいたい内容だったので気合を入れて取り組んだ仕事だったが、少なくとも私はその取材に関係した誰とも個人的に電話番号を交換したいとは思わなかった。いろんな人と会って話す仕事をしているからといって、自分の伴侶になるかもしれない素敵な人と出会う可能性が高くなるとは限らないのだ。
世の中には親切な人がいるので、こんな私に出会いのチャンスを作ってあげようという人はたまにはいる。某田舎の取材先で、インタビューさせていただいた老婦人(“グランマのクッキー”のイラストのような可愛いおばあちゃん)に、彼女の孫とのブラインド・デートをセットアップされそうになったことがある。老婦人は孫の写真を私に見せながら、「あなたは頑張り屋さんね。でも早く結婚して家庭を持ちなさいな。女性は20代のうちに結婚したほうが幸せよ。そうね、今夜、家に食事に来たらいいわ。孫のウィルも呼ぶから。いい子なのよ、まだ独身だし」と微笑み、近所に住む26歳の孫に電話を掛けようとした。ウィルはシカゴに近いその田舎街で育った後に農協で働いており、「生まれてから一度もシカゴより遠くに行ったことがない」らしい(アメリカの田舎にはそういう人が大勢いる)。そんな見ず知らずの若者とセットアップされても困ると慌てた私が、「私はアジア人なので若く見えるでしょうが、もう30代半ばを過ぎているんですよ」と言うと、老婦人はショックで腰を抜かしそうになったので、何だか自分が30歳代なのに独身でいることが申し訳ない気持ちになってしまった。私の年齢がわかった老婦人が、それ以上は無理強いしなかったことは言うまでもない(笑)。日本でもそうかも知れないが、アメリカでも田舎に行けば行くほど、“30歳代で離婚経験のない健康な独身女性”の存在を不思議がる度数が高くなるような気がする。
アメリカの田舎街で長期取材をしていて、もうひとつ困ることが食事である。この年になると数週間もの間、朝昼晩、毎日外食を続けるのは非常に不健康だし、外食はカロリーが高いので自然と体重も増える。シアトルならば、和食や中華はもちろん、タイやインド料理などのエスニック料理や新鮮なシーフードなどおいしいレストランが揃っているが、アメリカの田舎街の外食事情は驚くほど悪い。ファストフードのことを真面目な顔で「レストラン」と呼んでしまうし、チャイニース・レストランへ行けば真っ赤な甘いソースのアメリカ風中華料理しか出てこないし、サラダを頼めば葉が変色しているし、スープはキャンベルの缶スープだし……。これがたとえばロシアのアメリカン・レストランとか、アフリカの中華料理店ならば許せるのだが、シアトルと同じアメリカ国内だからショックが大きいのだと思う。とは言っても状況は変えられないので、私は「どんなにまずくても、出された食事は楽しんで食べよう」と前向きに取り組むようにしている。知らない土地で、そんなことにひとりでトライしている自分がとても健気に思える時もあるが仕方がない(笑)。
だからこそ、シアトルの空港に戻ると、まず女友達に電話して速攻でおいしいものを食べに行くようにしている。そして、久しぶりに自分のアパートに帰る。私が出張に出るたびに、部屋の鍵を預けている仲良しの女友達が植物と郵便物の世話をしてくれるので、ドアを開けるとテーブルの上に必ず彼女からの「Welcome home! I miss you」というメモが置かれている。私の帰りを楽しみに待ってくれる彼がいなくても、そのメモを見るたびに「いい女友達がいる私は幸せ者だなあ」と実感する。
でも、もし首を長くして私の帰宅を待っている彼が部屋にいたら、出張から家に帰って来るたびに今よりもっと幸せな気持ちになるのだろう。その日の到来を心待ちにしながら、私はすぐ次の出張に出るために帰宅そうそう洗濯を始める……これが私の夏である。改めてこうやって書いてみると、私の夏って結構きついなあ(笑)。でも、それでもこの仕事を続けているのは、結局私は何だかんだいっても自分の仕事が好きなのだと思う。毎日頑張っていれば、いつかはニューヨークに出張に行ける日も来るかもしれない。願いはきっと叶うはず(と信じたい)、みんなも頑張ろうね!
第31話 「褒めなきゃならないアメリカ人」
アメリカで暮らして何年経っても、未だに慣れないことのひとつに「相手を褒める」という行為がある。別に褒めるという行為自体は難しいことではないが、褒めなければならないポイントやタイミングが日本と微妙に異なるからだ。
日本でも相手を褒めることはよくある。中でもビジネスや近所付き合いにおいては格別である。上司や取引先など明らかな利害関係が存在する相手などに対しては、褒めまくると言ってもいい。私も日本でお勤めをしていた頃は、「いや~、社長のゴルフの腕前はタイガー・ウッズも真っ青ですな。いや、恐れ入りました。ハッハッハッー!」と車海老のように体を前傾させながらお愛想笑いをする親父達の姿をよく目にしたものだ。また、PTAや近所付き合いでも「お宅の息子さんは優秀で羨ましいわ。うちの子にもお宅の爪の垢を煎じて飲ませたいほど」とか、「あら奥様。そのスカーフ、とてもお似合いですわね~」などというやり取りは常に存在する。「ごまをする」という言葉もあるほど日本社会に根付いた行為である。でも、これは「この商談を何がなんでも決めたい」とか「隣近所から悪く言われて、住み難くなったら困る」など、基本的に何らかの利害関係が存在する場合に多く見られる行為であって、親しい女友達とか伴侶とか自分の親兄弟に対して日常生活の中で「ここで相手を褒めなければマズい」と感じることはほとんどないように思う。そう考えると、日本における相手を褒めるポイントは案外つかみやすいと言えるのではないだろうか。
それに比べて、アメリカにおける「ここでは相手を褒めるべき」というポイントは少々わかりにくい。アメリカ人は基本的に褒められ続けて育っている上に、「相手を褒める」のは慣習なので、ちょっとした挨拶の際でも妙に大袈裟に褒め合う。でも、この挨拶時の流れは誰が見てもわかりやすい。とりあえず何かを褒めればいいのだ。これは日本のPTAの集まりにも非常に似ている。褒めるのも褒められるのも苦手な私でさえ、別にその相手に何も目新しい変化が見られなくとも、"Wow,you look great!"くらいは言うように心掛けている。いちいち面倒臭いなと思うことは多々あるが、“郷に入っては郷に従え”である。
私が「わかりにくいなあ」と思うのは、アメリカ人の彼や旦那や親友など「超身近な人達」に対する褒め方である。私は私なりに意識的に褒めているつもりだが、それでもアメリカ的には「褒め足りない」ことが最近よくわかってきた。私もほかの外国人の類に漏れず、渡米してからの数年間は会話の中での微妙な駆け引きが読めるほど英語も文化も理解できなかったので、こういうことをそれほど重要視していなかった。でも日本語と同様、英語にも“含み”がある。その含みやダブル・ミーニング(まったく別のふたつの意味)を持つ単語のボキャブラリーなどが増えてくると、今まで見えなかったものが多少見えてくるし、ちょっと皮肉を含んだジョークにも周囲と一緒に笑える回数が増えてくる。こうなると会話の中で「あっ、今のはAさんを褒めるところだったんだな」と何気に周囲から知らされることもあるし、メチャクチャ面白いけれども手痛いジョークを返されたことで、自分の発言が相手を少々ディフェンシブな気持ちにさせてしまったことに気付かされたりする。たまに、こういう微妙なラインに何も気づかなかった渡米当初の方が、アメリカ生活が楽だったなあと思うことさえある。
また、自分では相手に対する愛情で言ったこと、つまり相手を褒めたつもりでいても、それが必ずしも自分の意思と同様には受け取られないことも難しい点だ。例えば私がアメリカ人の男性と付き合う時、「あなたって本当に頭が良くて、素晴らしいわ」というような台詞を頻繁に言うべきなのはわかっていても、何だか嘘っぽく聞こえる気がして抵抗を感じてしまう。だから、何かを手伝ってもらったり、助けてもらった時に大袈裟にその功績を褒めまくるなど、自分なりの方法で相手をできるだけ褒めてきた。それでも、直接的な台詞を私が頻繁に言わないことでもめた経験は数え切れないほどあるのだ。
くだらない例で恐縮だが、私はアメリカ人の男性と初めて付き合った時、「なんで君は僕のことを全然褒めてくれないのか? 僕のことを本当に好きなのか?」と真剣に尋ねられて、「口に出して褒めないから愛情が少ないと思うなんて、この男、バカじゃないの?」と思った記憶がある。「言葉じゃなくて相手の心を読めよ。浅い奴だな」と、非常にがっかりしたのだが、その後に付き合ったアメリカ人の男性達も、言い方は多少異なるがみんな私に同じことを何度も尋ねたので、さすがに参ってしまった(笑)。とにかく私は褒め下手らしい。簡単に言えば、まず相手を褒める回数がアメリカ人に比べて断然少ないのだ。私としては、心のどこかで「言葉に出さなくても信頼があれば気持ちを汲んでもらえる」と思っている上に、大切なことを何度も口に出したら価値が薄れる気がするのだが、アメリカ人はなかなか他人の気持ちを「聞いてくれるけれど、読んではくれない」。友人から聞いたのだが、私の元カレの中には、あまりに私が相手を褒めなかったので(本人は褒めているつもりなのに)、今でも私を“愛情の薄い女”だと思っている奴もいるそうである。
「相手を少し落とすことで、自分が相手に対する愛情を周囲に表現する」という日本的なテクニックが「アメリカでは全然通じない」ことが、国際間の誤解を生む原因となる場合もある。これは日本の芸人やTVタレントがよく使っているが、一般人の私達は、これを照れ隠しとして使用することが多いように思う。ちょっとした相手の「笑っちゃう部分」や「おかしかった失敗」を友達の前で楽しく話してしまうのだ。言っている本人からすると「こんなことしちゃう彼って可愛いでしょ?」と結構ノロケているつもりでも、自分のことを話されたアメリカ人の中には火がついたように怒る人もいる。「なんで僕の恥ずかしい失敗を人前で言うんだ」とか「そんなプライベートなことを他人に言うなんて信じられない」などと、アメリカ人の彼や旦那を怒らせた日本人の女友達は私が知っているだけでも山ほどいる。私自身、アメリカ人の彼を怒らすたびに、「人の前では褒めることしか言っちゃいけないんだな」と毎回学ぶのだが、ほとぼりが冷めた頃にまた同じようなことを言ってしまったことが何度もある。
友人のK子から聞いた話だが、K子がアメリカ人の友達と複数で話している時に、ある「褒めミス事件」を起こしてしまったそうだ。アメリカ人のAさんが抱えている問題の本質が、誰がどう見ても明らかにAさん自身の行動に起因していた。でもほかの友人は「あなたは一生懸命やっているじゃない。偉いと思うわ。時間が経てばきっと何とかなるから大丈夫よ」と、解決策にならないことばかり言うので、K子が「その問題を本当に解決したいなら、あなた自身も現在の行動パターンを変えて、もう少し努力するべきだと思うわ」と真摯にアドバイスしたら、すっかりAさんを怒らせてしまったそうだ。Aさんは「それ、どういうこと? 私に問題があるって言ってるの?」と、ディフェンシブになり、K子の誠意よりも“指摘された”という行為ばかりが問題になった。後日、その場にいたほかのアメリカ人の友人から、K子は「友人でもパブリックで、その人の悪いところを指摘しちゃだめよ。あなたは良くやっているとか、偉いわとか褒めてあげないと……」とアドバイスをされたそうだ。K子は私達日本人の友達の前で「知らない人ならともかく、友達なのに褒めとかなきゃいけないなんて、納得いかないわ! 褒めてばかりじゃ問題が解決しないじゃない」と落ち込んでいたが、私もK子と同様の失敗をしたことがあるので気持ちは良くわかった。ちなみに、私はアメリカ人の友人のアドバイスを受けて、それ以後、そういう話題は相手と2人で話す時だけにするようになった。今、ふと思ったのだが、アメリカでは「指摘してはいけないこと」がパーソナル・レベルでたくさんあるから、「どんなに相手に問題があっても、とりあえず褒める」という文化が発達したのだろうか?
とにかく、この「相手を褒めるべきポイント」は、私のような正直者にとっては把握することがかなり難しい(笑)。きっと基本的には何でも褒めておけば安全なのだろう。でも、それでは真の友情や信頼、愛情が育ちにくいように思えてしまうのは、私だけだろうか。(な~んて言っても、どの国も同じかな?)
第32話 「アメリカと肥満」
先日の『シアトル・タイムズ』紙に、シアトルを含むワシントン州キング郡の肥満率が人口の18パーセントに達したという記事が掲載されていた。同郡の中でもアーバン市などは人口の28パーセントが肥満らしい。これは大変な数字である。
身長と体重のバランスを測定するBMI指数では、25以上ならば「太り過ぎ」、30以上が「肥満」だと分類される。例えば身長160センチメートルならば体重47.5~63.8キログラムが「標準体重」(BMI18.5~24.9)、それ以下は「アンダーウエイト」(痩せ過ぎ)。アメリカで肥満と診断されるには身長160センチメートルの場合、少なくとも体重が76.8キログラム以上なければならない。
日本の場合、身長160センチメートルで体重76.8キログラムだとかなり目立つだろうが、アメリカだとこの程度ではそれほど目立たない。アメリカでも日本と同じBMI指数を使用しているが、日本ではBMI25以上で「肥満」と分類し、30以上になると「高度肥満」と呼んでいるらしい。この違いからも価値観の相違が少し見えるが、アメリカなら「健康的なナイス・プロポーション」だと褒められる体型の女の子が、日本では「あのラーメン屋で働いている、ちょっと太っている子でしょ?」と表現されるのも基準の違いである。私は日本人としては自分が「ちょっとデブ範囲」に入ることを明確に認識しているので、この記事を読んで速攻で自分のBMI指数を確かめたが、あと5キロ落とせばベスト体重だけれども何とか「標準体重」の範囲内であることがわかり、かなりホッとした。しかし、BMI指数上は標準に入る私でも、日本に帰国するたびに両親から「アメリカに行って、こんなに太ってしまった」と心配され、健康な生活を送るように毎回厳しく指摘されるのも、国の標準が異なるひとつの例であろう。
日本にも肥満の問題はあるだろうし、アメリカだけが問題を抱えている国ではないだろうが、アメリカの肥満は日本に比べて全然スケールが違う。BMI指数の「30以上が肥満」という最高値設定では、“普通に肥満な人”と“スーパーサイズに肥満な人”の区別が付かないので、少なくともアメリカではBMIの数字を50とか80まで増やした方がいいと思うほどである。
それにしてもアメリカで肥満と認識される人達は本当に大きい。私は仕事柄、飛行機に乗ることが非常に多く、しかもいつもエコノミー・クラスなので、毎回「今日は細めの人が隣に座りますように……」と祈ってしまうほど、太った人と隣り合わせになることが多い。自分も痩せているわけではないので、太っている人に対してはシンパシーがある方だと思うが、残念ながら機内ではシンパシーが消える。みんな同じ料金を払って乗っているのに、太っている人は各座席を隔てる肘掛けを“最初からまるで当たり前のように”自分だけが占領して、それを“当然の行為だと主張するような態度”を取るからだ。きっと各自のプライドがそういう強い態度を取らせるのだろうが、私はそういう態度に対してカリスマ司会者のオプラ・ウィンフリーのように「それこそBBWの心意気よ。そうでなくちゃ!」とはポジティブに言い切れない。BBWとは“BigBeautiful Women”の意で、太っている女は美しいと自信を持つことの定義らしいが、SSBBWなる言葉もあることを知って、「それは、どうなんだろうか……」と思ってしまった。ちなみにSSBBWとは“Super-SizeBig Beautiful Women”のことだそうだ。
アメリカでは特に、どんな発言をするのも常に誰かに対して何らかの差別的な要素を含むことがないように細心の注意を払わねばならない。そのため、ほんの少しでも何か他人とは違う様子を感じている表情を見せたり、太っている人に向かって「本当に大きいですね」とか、「もう少し気をつけた方が体に良くありませんか?」などとは親切心からでも絶対に言ってはいけない。だからこそ、前夜ほぼ徹夜状態だったので機上で少しでも睡眠を取ろうと思っている時に、肘掛けを占領されたうえに私のスペースにまで体をはみ出し、そのうえ挨拶のひとつもないとなると、どうしてもムカついてしまう。「私も同じ金額を払って搭乗しているのに、なぜ私だけが100%全面的に相手に気を遣わなければならないのか?」という気持ちを文句にも態度にも出せないのは不公平だと思うのだ。でも、この国ではそんな気持ちを他人に面と向かって言うことはできない。そんなことを言ったら名誉毀損で訴えられてしまうかもしれない。だから、肘掛けだけでなくスペースまで取られても黙っているしかないのだ。“先に取ったもん勝ち”のアメリカを象徴するような問題である。
「私が太っているものだから、まったく面識のないあなたの座席の半分近くを占領してしまって本当にごめんなさいね」という態度や笑顔を見せるか、ひと言でも「すみませんね」と声を掛けてくれれば私も許す。「まあ、何を言っているんですか。困った時はお互い様ですよ」なんて言いながら、感じの良い笑顔のひとつも返すかもしれない。私がムカつくのは彼らが「いばっている」ように見えるからだ。そういう態度は、太っていてもプライドを持とうというBBWの本来の意図ではないように思う。挨拶や気遣いを見せる態度は他人に対する思慮や配慮である。他人への気遣いと自分へのプライドは異なるものなので、たとえ他人を気遣ったとしても自分を尊む“プライド”は失われないはずだ。とにかく私の運が飛び抜けて悪いのかもしれないが、これほど多くの割合で体が非常に大きい人と飛行機で隣り合わせになるということは、それだけ多くのアメリカ人が肥満だということなのだろう。
この国で発表されているさまざまな肥満原因調査によると、一番の問題は、アメリカでは野菜や果物などのヘルシーな食材は、ファストフードや炭酸飲料よりずっと値段が高いので、低所得層に肥満が多いことだという。正しい食生活を教える教育が浸透していないことと、誰でも安価で利用できるように各地域の公民館などにジムを設置しても、ジムに行くためのバス代がないことが理由で利用者が少ないことも問題らしい。前述した記事の中には、研究者が肥満率の高い地域を調査したところ、通りにはファストフード店が建ち並び、公園が少なく、スーパーマーケットでは10個で$1の揚げドーナツ・パック(だったと思う)など信じられないほどの安値で簡易スナックが売られていたそうだ。また、その地域の歩道を調べたら一部の整備状態が悪いことがわかったので、「だから肥満の人が外を歩かない→歩道を税金でただちに直すことにした→これで人々が外を歩く→肥満率の低下に繋げる」という動きをしていることも書かれていた。
環境を整えれば肥満が低下するという記事の視点はよく理解できるが、この記事を読んで、まず「えっ?」と思った人は、きっと私だけではないだろう。確かにアメリカ政府が高度肥満者に毎月生活保護を支給したり、肥満者が余分な脂肪を切り取る手術費を税金から負担したりするのはすごいことだと思うが、私には「本人の意思と努力」というとても大切なことが根本的に見失われているような気がする。外を歩かないのは本人の怠惰による可能性があるかもしれないことよりも、じゃあ歩道を整備してあげようという発想に、私は「えっ?」と思ってしまうのだ。念のためスーパーマーケットに行って確認してみたが、やはりドーナツよりもキャベツ1個の方が安いし、器に盛るだけで食べられる袋入りのサラダや工場で既に食べやすく切られた果物は高くても、普通のレタスやリンゴやオレンジは、ポテトチップス1袋よりもずっと安い。ポテトチップスが買えるなら、野菜も買えるはずである。
私は自費でアメリカの大学に留学したので、大学時代の私の食生活はカツカツだった。トマトやレタスは値段が高くて、しかもお腹にたまらないので、「米・キャベツ・ジャガイモ・ニンジン・玉ネギ」という基本食材の中で精一杯工夫する食生活を送り、水を飲んでいた。当時の私にはファストフードやスナック類はご馳走だった。政府から支給されるフードスタンプを使って買い物している人が、ドーナツやスナックや炭酸飲料を買う様子をレジで見るたびに、うらやましいなと思いながらも、「どうして今日はキャベツが特売なのに買わないのかしら」「どうして食べなくても困らないコーラやアイスクリームをフードスタンプで買うのかなあ」などと、よく疑問に感じたものだ。だから私は「健康な食材が高いから買えないので太る」という理由には簡単には納得できない。
また、ジムに通うバス代がなければ、家の周囲を30分間グルグル歩くとか、部屋で腹筋や腕立ふせをしてはどうだろうか? 運動するよりも、テレビを見ながらスナックを食べる方が誰にとってもラクなはずだ。その結果、気が付いたら高度な肥満になっていた人には税金から補助金が出る。でも自分でお金を払ってジムに通い、太らないようにものすごく毎日努力している人は、肥満から派生する医療費を使わず国に貢献しているのにもかかわらず、税金からご褒美がいただけないのはなぜだろう?
私は出張で1週間近くホテル滞在が続くと、朝昼晩すべてが外食になるうえに運動する時間がないので確実に太ってしまう。先日、出張から戻った翌日に女友達と久しぶりに集った席で、私が「あー、もうこんなに太っちゃってどうしよう。最近ダメだなあ」と言ったら、日本人の友達が「うん、秋野、最近太ったね。急にオバサンぽくなったから気を付けなよ」と心配してくれた。だから普通に「ねえ、何をしたら一番効果的かな?」「まずは食事の量を減らすこと。そして運動。あんた最近ジムに全然行ってないでしょ? 体の線に出てるよ」などと真剣に話していたら、日本人の私達の会話を聞いていたアメリカ人達が「Ican’t believe you said it!」と言って、ものすごく驚いていた。でも、その後いろいろ話しているうちに、アメリカ人達から「相手にはっきり思っていることを言いたいと毎日にように思うわ。でも、それを言ったら私の方が常識や教養がないと思われてしまうから言えない」「ポリティカリー・コレクトかどうかを気にしてばかりいるから、この国にどんどん問題が増えていくのよ」などという発言まで飛び出した。しまいには「私にも変なところがあったら言って欲しい」とお願いしながら、私達日本人の正直な友人関係をとても羨ましがっていた。
日本人の女友達や母親の発言はキツイものがある。でも、それはとても大切なバロメーターでもある。「ちょっと太ったかな」と思っても、周囲にはっきり言われて初めて「ああ、本当に人にわかるほど太ってしまったのだ」ということが確実に認識でき、非常に焦る。認識できなければ状況は変わらないので、この認識は手痛いけれども非常に大切なバロメーターだ。アメリカ人に比べて日本人に肥満が少ないのは、単に食べ物や運動量の違いだけではなく、歯に衣着せぬ「鋭い指摘」をする女友達の存在かもしれない。
第33話 「エル・ワード」
某原稿の締め切りを直前に控えていた先週末、パーティーのお誘いも断って仕事をしていたら携帯が鳴った。クライアントからではなく、男友達のトニーからの電話だとわかったので「暇だから電話して来たのだろう」と無視して仕事を続けていたのだが、しつこく何度も掛かってくる。仕方がないので電話に出ると、トニーは「お前、今、何してる? ちょっと出て来れないか?」と妙に緊迫した声で尋ねてきた。「締め切り前で忙しいから今日は出掛けられないよ。ほかの人と遊びな」と答えると、彼は「お前じゃなきゃダメな用事なんだよ。1時間でもいいから何とかならないか?」と珍しく困っている様子である。「先に言っとくけど、お金なら貸さないよ」と言うと、「そんな冗談を言ってる場合じゃないんだ。何とか出てきてくれよ。理由は後で話すから」と懇願するので、「なら、あんたのオゴリだよ」と念を押して近所のバーへ出向いた。トニーは相手が友達なら女でも絶対におごったりしない。その彼が「何でもオゴってやる」というのだから、何かややこしい問題でも起こったのだろう。
トニーは明るくて面白い奴だが、あまり知らない人に対しては異様なほど外面が良く、やたら調子のいいところがある男である。しかし、親しい友人には自分の財布の中身から、前夜を共にした女性の話まで、こちらが聞きたくなくても詳しく話すオープンな奴だ。だから彼と友達になって5年以上経つ私は、彼が抱えているたいていの問題は知らされている。そんな彼が電話では簡単に話せないことがあるなんて、何だか面倒なことに巻き込まれそうな予感がした。
約束の店でトニーを探すと、彼はすぐに見つかった。そして彼の隣には、私が会ったことのない日本人らしき女性が座っていた。その見慣れない構図を目にした瞬間、私は自分の予感が的中したのを確信した。トニーはいつもベラベラとくだらないことを話しまくる騒がしい男だが、その日は妙に大人しく、私に向かって「やあ、来てくれてありがとう」とまで言うので、かなり妙なことになっているのがわかった。でも、その女性がとても礼儀正しく上品な人だったので私は少し安心した。彼女はH子さんといい、東京の会社で働いているキャリア・ウーマンで、半年ほど前にトニーが出張で初めて日本に行った際、仕事関係のパーティーで知り合って友達になったらしい。トニーは自分が気に入った女の話は何でも私にするのにH子さんの話はまったく聞いていなかったので、トニーがH子さんと特別な関係ではないことは想像できた。しかも、H子さんはトニーの好みとはかけ離れた地味な雰囲気を持つ、繊細でナイーブな女性だった。もっと良く言うならば、H子さんはトニーには出来過ぎた人に見えた。
トニーが特に何も説明しないので、私はなぜ自分がその場に急きょ呼び出されたのかわからないままに、とりあえずカクテルをオーダーし、その日の朝にシアトルに到着したばかりで、シアトルに来たのは初めてだと言うH子さんと「シアトルはどうですか? 結構寒いでしょう?」、などと明るい調子で世間話を始めた。私はなぜ自分が場を盛り上げなければならないのだろうと思いながらも、つい人に気を遣ってしまうタイプである。トニーは自分ひとりでは場を持たせきれないから、出張でシアトルを訪れたH子さんと同じ日本人である私を呼び出したのだろう。だから、私はまったく罪のないH子さんに気を遣って、つまらない質問だとは思いながらも「シアトルへはどんなお仕事でご出張されたんですか?」と、一般的な振りを入れてみた。
するとH子さんは、とても素敵な笑顔を浮べながら「いいえ、出張ではないんです。休暇を取ってトニーさんに会いに来たんですよ」と当たり前のように答えたのである。それを聞いた私は、飲んでいた水のグラスを口につけたまま一瞬固まってしまった。そしてバツが悪そうに大人しく座っているトニーの表情を横目で見ながらも、笑顔を作って「まあ、そうなんですか? わざわざ休暇を取って?」と何気ない口調で会話を続けた。H子さんは「日本で出会って以来、トニーさんとはEメールでたまにやり取りしていたんですけど、彼がシアトルに遊びにおいでと何度も言うので、いろいろ迷った末に思い切って来たんです」と、少し照れながらもとても嬉しそうに話した。しかもH子さんはトニーの家に滞在するらしい。彼女の幸せそうな様子を見ながら、私は「あーあ、トニー、またやっちゃったな。自分で責任取れよ」と心の中で毒づきながらカクテルを飲むしかなかった。
H子さんが化粧室に行くために席を立つと、私はいきなり口調を変えて早口でトニーに「あんたは彼女を単なる友達のひとりだと思っているようだけれど、明らかに彼女はあんたのことを単なる友達だとは思ってないよ。ナイーブそうな女性だから、そこんとこ、ちゃんとしときなよ」と冷たく言い放った。トニーはオロオロしながら「俺も彼女が今朝ここに来て始めて、お互いの理解が違うことに気付いたんだよ。俺どうすればいい? お前、何とかしてくれよ。友達だろ?」と焦りまくっている。とにかく、滞在中にトニーは彼女と友達であり、彼にはなれないことをわかってもらい、彼女がシアトルで楽しく過ごせるようにベストを尽くすしかないという結論を出した。そして彼女が席に戻ってきてからはトニーも通常の口調に戻って、自分が本来はバカな男であることをガンガンとアピールし始めたので、私もそれに少し付き合ってから家に帰った。
H子さんの滞在中、何度かトニーと一緒に彼女に会ったが、H子さんは本当に良い人だった。彼女がそれほど良い人でもナイーブな人でもなければ、トニーも適当によろしくしたかも知れないが、そういうタイプの人と一線を超えると割り切れなくなる場合が多く、友達ではいられなくなる可能性が高い。だからトニーは遠くから訪ねてきた友人をケアするホストに徹底していたが、自分が理想とする友人関係を気にするあまりに度が過ぎて、何だか必要以上に親切にしているように見えた。「ものすごく親切にされることと愛情は、場合によっては見分けがつきにくいから気を付けなよ」と私はトニーに何度か忠告したが、「俺は誤解が生まれないように一切、彼女に手を出していないから大丈夫だ」と言って態度を変えることなくH子さんの良きホストを続け、数日後にH子さんは無事日本に帰国した。
ちょっと心配したけれど、みんなが楽しく過ごせて良かったなと思っていると、またトニーから電話が掛かってきて「落ち込んでるから、ちょっと付き合え」と言われた。今度は何だろうと思って出掛けて行くと、トニーはすべてうまく行って楽しく終わったと思っていたのに、最終日にH子さんからエル・ワードを出されてしまったと言うのだ。「オーマイガーッ!」と叫ぶと同時に、私は「あんた彼女にそんなこと言わせるなんていったい何をしたのよ!? あれだけちゃんとしろって言ったでしょ!?」とものすごく怒った。トニーは「俺は何もしてない! 本当にしてないんだよ!」と大声で反論し、「だから落ち込んでいるんだ」と言ってガックリと肩を落とした。
言うまでもないかも知れないが、エル・ワードとは特定の相手に面と向かって「I love you」と告白することである。日本に住んでいる日本人にとっては、アメリカ人は誰かれかまわずエル・ワードを口にしているように見えるだろうが、実際はそうではない。家族や親しい友達に向かって言う「I love you」と、特定の相手に向かって始めて口に出す「I love you」はまったく異なるものである。エル・ワードの意味は非常に重い。デートを重ねているカップルでも、いつ相手がエル・ワードを言うのかとやきもきしたり、いつまでも相手がそれだけは言われないので、その関係を続けていくことを諦めてしまったりと、さまざまなドラマを生む重要な言葉である。そしてエル・ワードを持ち出された以上、「聞こえなかった振り」をしてそれを無視する訳にはいかないのだ。H子さんとは友達でいたいと願ったトニーが落ち込んでいたのは、そのせいだった。彼はそれに対して何か答えなければならない状況に追い込まれてしまったからだ。もしかしたら、H子さんはそのセリフが彼をそこまで追い込むことになるとは思ってもいなかったかも知れないが、自分が彼女と同じように感じているというサインをはっきりと見せていないアメリカ人であるトニーに対して言うには、タイミングが性急過ぎたことには間違いない。
結局トニーがどう答えるのかは本人の問題なので、私は「あんたの態度がはっきりしないから彼女にそんなことを言わせてしまったんだろうから、私はもう何も聞かないよ」と、きっぱりとラインを引いたが、二人が共に多少なりとも傷付いてしまうことには変わりないだろう。本当にエル・ワードを言ったり、言われたりするタイミングは難しい。でも、相手とベッドを共にしたいという理由だけで、会ったばかりの相手にエル・ワードを言う奴もいるので、その使い分けや意味の違いも理解できる能力も持たなければならない。あー、英語って本当に難しい!
第34話 「オフィシャルな相手」
アメリカでは感謝祭やクリスマス、ニュー・イヤーズ・イブなど、大きなイベントが目白押しとなる11月後半から元旦までの期間を全部ひっくるめてホリデー・シーズンと呼び、この時期にはさまざまなパーティーが催される。感謝祭やクリスマス当日は家族単位の集りがほとんどだが、クリスマス前までの12月中は会社や仕事関係のパーティーが集中する。まあ、簡単に言えば日本の忘年会シーズンのようなものである。
とは言っても、日本における会社の忘年会と、アメリカの会社が主催するクリスマス・パーティーには、いくつか異なる点がある。たとえば日本だと、会社の忘年会でも2次会、3次会へと続き、記憶がなくなるほど飲んで盛り上がってもご愛嬌だが、アメリカでは会社のパーティーで記憶がなくなるほど飲んでしまったら、翌日にはオフィスから自分の机が消えている可能性が高い。パーティーで飲んでも良いとされるお酒の量や、その飲み方と勧め方は2国間でかなり異なるように思う。
でも何よりも異なるのは、アメリカでは会社や仕事関係者のパーティーに自分のパートナーを同伴して出席する習慣であろう。なかでも年末に開かれる仕事関係のパーティーでは「ホリデー・シーズンだから!」という妙な理由で、いつもよりさらに同伴での参加を即されることが多い。もちろん主催者はよかれと思って「同伴で」と誘ってくれているのだろうが、これは独身者にとっては非常に面倒な習慣でもある。
しかも、この習慣は招待された独身者を「ひとりで行くか、同伴するべきか」と悩ますだけでなく、その招待客が「誰かとお付き合いをしている」場合にはちょっとしたドラマを生んでしまうこともある。仕事関係のパーティーのような「オフィシャルな集り」の場合、友人は連れて行かない。そのような集りにわざわざ誰かを同伴するということは、「この人は自分にとってオフィシャルな相手である」という意味になってしまうからだ。逆に言えば、そういう場に同伴する(または同伴される)ということは、その相手が正式なパートナーであると認める(認められる)ことでもある。相手にとっての自分の位置付けを確認するには、これほどわかりやすいバロメーターはないだろう。だからこそ、ホリデー・シーズンには、各所でちょっとしたドラマが生まれるのである。
たとえば私の某女友達(日本人)は、「彼女はパーティーにどんな人を連れてくるのだろう」という周囲の期待(本人からすると)をわずらわしく感じたので、仲良しの女友達を連れて出席して以来、会社ではずっとレズビアンだと思われていたことが最近になって判明した。同性ならばいいだろうという考えは、アメリカでは通じない。私もこの習慣の本来の意味を認識せず過去に一度、オフィシャルな集りに友人の男友達を連れて行って大失敗をした経験があるが(第14話参照)、その事件後に周囲のアメリカ人達から、「同伴するような相手がいない、または相手がいても同伴するにはまだ早いと思う場合は、ひとりで出席するものだ」と教えられて大恥をかいた。まだ学生だったり、友人主催のカジュアルなパーティーだったりしたら何でもありだが、仕事関係の集りには「せっかくの豪華タダ飯だから、誰かを誘ってあげよう」などと貧乏臭いことを考えてはいけないようである。
つい先日も女友達のA子が、現在お付き合いしているアメリカ人男性が彼の会社のクリスマス・パーティーに彼女を誘ってくれなかったと言って落ち込んでいた。それを聞いて、その場にいた日本人の女性陣は「えっ、どうして? もう半年も付き合っているのに!」とか、「もしかしたら雰囲気的に同伴者を連れて行きにくい会社なのかもよ」と彼女に同調したが、複数の男友達(アメリカ人)は「何言ってんだ、そんなことは良くあることだよ。だから深く考えるな」と言って彼女を慰めていた。その折に、これまた独身のスコット(36歳)が「俺だって今まで誰も会社のパーティーに連れて行ったことがない。そんなことしたら後が大変だ」と言ったので、私が、「あれ? じゃあ以前2年近くも付き合っていたリンダ(仮名)も連れて行ったことがないわけ?」とちょっと彼女をかばうような口調で聞き返すと、彼は「あるわけないだろ。We were just dating」と答えた。
私はその女性とは友達ではなかったし、スコットとも頻繁に会うわけではないので事情を知らず、ずっとその女性のことを彼の“ガールフレンド”だと思っていた。だから「あ、デートしていただけなんだ。失礼しました」と言って、さっさとその話題を終わらせた。すると、A子が「え? ちょっと待って。デートしていただけってどういうこと? なんでデートしているのにパーティーに連れて行かないの?」と聞き返したので、みんなが一瞬「はあ?」と止まった。A子の発言の意味がわからなかったからである。A子は英語が上手いがアメリカに来てまだ日が浅いので、アメリカと日本では「デート」の解釈が多少異なることを知らなかったらしい。
日本では通常“ふたりは付き合っているからデートしている”と解釈するが、アメリカでは多くの場合、“デート”というのは彼女とか彼という「オフィシャルな相手」になれるかどうかを探り合う、お互いにとってのお試し期間だ。デートしている期間中は、週に1度か2度ほどふたりで会って食事に行ったり、映画を見たりという「それほどスペシャルではないこと」は定期的にするが、親に会わせたり、前もってバレンタインズ・デーや誕生日など意味を持たせてしまうイベントを一緒に過ごす約束はしない。たまたまそういう特別な日に予定が空いていた場合は誕生日を一緒に過ごす結果になることもあるだろうが、基本的には単に定期的に会っている関係を「デートしている」という。それゆえにオフィシャルな相手を連れて行く会社のパーティーに、「まだデートを重ねているだけの相手」を連れて行くことは「あるわけない」のである(スコット談)。
個人的には“We were just dating”というフレーズに、“just”という単語が入るのは非常に気になるのだが、アメリカにおける“Just dating”は単にその言葉そのものであり、それ以上でもそれ以下でもないのだ。だから、ある女性と“デート”をしている男性が、複数の女性とも定期的に会っていても基本的にはそれに対して文句は言えないのである。デートしているだけの彼は、日本的な認識における「彼」ではないからだ。もちろん、自分がデートをしている男性が複数の女性みんなと寝ているとなれば道徳観の問題になるので話は別だが、相手が本当に自分に合っているかどうかを見極める目的で複数の女性とデートをしているならば、アメリカ的には相手の行動には口出しできないのである。それが嫌ならば、複数とデートをしている相手とは最初から付き合わないか、デート期間というプロセスをすっ飛ばしていきなり「私とだけ付き合って欲しい」と頼んで「いいですよ」と言ってくれた相手としか付き合わない(そんな人がいたら、ちょっと怖いけど)という方法しかないだろう。
このことをスコットがA子に説明したのだが、彼の話を聞いたA子はボソッと、こうつぶやいた。
「もしかしたら、私はまだ彼女ではないのかもしれない……」
それを受けてスコットが、“Maybe you’re right”と真剣に答えていたのが、とても印象的だった。
ホリデー・シーズンには、このようにちょっとしたドラマが各所で起きるものである。でも、笑い飛ばせるものはできる限りすべて年内に笑い飛ばして、みんなで良い新年を迎えよう!
第35話 「オンラインに躊躇する理由」
女友達のクリスが「アメリカでは4,000万人の人がオンライン・デーティングを利用している」という記事をメールして来た。4,000万人といえば、ニューヨーク州の人口、あるいはオーストラリアの人口の約2倍である。ここシアトルが位置するワシントン州の人口で比較するなら、州人口の約7倍の独身者がオンライン・デーティングを利用していることになる。これは、ものすごい数である。
そのうえ、その記事には「アメリカでは18歳以上の人口の44パーセントが独身。つまり独身者は1億人以上いる」とも書かれていた。1億人、である。1億なんて聞くと、まるで街中の至るところに途方もなく大勢のシングルがさまよっているような気がしてしまうではないか。でも国勢調査だから、きっとじいさんやばあさんも数えているだろうし、入籍していなくてもパートナーと暮らしている人も多いだろうから、その分は減らして数えたほうがいいのだろう。とにかく、たとえ紙の上だけの話にしても独身者がアメリカに1億人もいるなら、独身者の40パーセントがオンライン・デーティングを利用しているということになる。10人のうち4人という利用者の多さに、思わず「えーっ! 嘘でしょー?」と若者のような高音を発してしまったほど驚いた私だが、送り主であるクリスのメールは、「そういうわけで、ネットでの出会いに対してネガティブなことを散々言ってきた私ですが、これを機にオンライン・デーティングにトライすることにしました」という、妙に淡々とした告知で終わっていた。そのアナウンスメントは、4,000万人というユーザー数の報告よりも私には大きく響いた。
クリスは「オンラインで選んだ男とのデートなんて“出会い”とは呼ばない」、「オンラインをやるほどデスパレート(絶望的)な女にはなりたくない」などと胸を張って言い切る、オンライン強硬反対派の筆頭だった。友人Aがデートしていた相手が妻子持ちだとわかった時も「だからオンラインはダメなのよ」と言って関係を止めさせたし、友人Bが寝た男が性病持ちだったことがわかった時も、「やっぱりオンラインだったから……」とわけのわからないことを言っていた女である。バーやクラブで出会った男でも妻子持ちや病気持ちは大勢いるだろうし、イベントやボランティア活動で出会った男でも職業や学歴詐称をする嘘つきヤローはいるはずなのに、彼女はオンラインを利用してデートしている誰かの関係が消滅するたびに、その原因を何でも「オンライン・デーティング」のせいにしていた。
クリスが頑なな態度を取っていたのは、彼女の持論が、「運命の人との出会いは、必ず誰にでもある。そして、その相手とは必ず自然に出会うはず」だったからだ。彼女は、「オンラインのように学歴や職業や写真から選んだ相手と片っ端からデートしていたら、いつの日かきっと自分もそういう方法でしか人間の価値が見えなくなり、出会うはずだった運命の人とは出会えなくなるかも知れない」と、よく言っていた。
私もクリスのように考えるほうなので、彼女のメールを読んで、「とうとう彼女も……」と、何となくさびしいというか、置いてきぼりをくらったような気持ちになった。自分だけが大きな流れに逆らって進んでいるような感じ、と言えばわかってもらえるだろうか。もしくは、みんなが対岸にどんどん渡っているのに、自分だけが岸辺に迎えに来ている最新型のボートに乗ることをなぜか躊躇している、という感じが近いかもしれない。それは、私がオンライン・デーティングに対して未だにある種の抵抗を感じていながらも、自分の将来を現実的に考えるならば、そんな悠長なことを言っている場合ではないかも知れないという焦燥感を感じているからだろう。
クリスが言うように、美しい持論を信じて毎日をポジティブに過ごそうとしても独身である現状はなかなか変わらないし、運命の時を待っているうちに、あっという間に40歳になってしまうかも知れない。だったら、自分の持論とか信念とか子供のころからの夢なんてものは横に置いて、「もう、あんまり時間がないんだから、なるべく早いうちに、多少冴えなくても高収入で優しくて、変態ではない人を見つけなきゃ」という気になるのが普通だろう。「ただ何かを信じて待つ」ということほど苦しいことはない。しかも、最近はオンラインを利用して結婚したカップルも増えてきた。だから、運命の出会いを信じている人も待っていることがどんどん不安になってきて「周囲がみんな利用しているし、ちょっとトライしてみようと思って……」という、何となく「本当はやりたくないんだけど、もう一般常識だから」的なニュアンスを含む言い訳をしながら登録しているのかも知れない。
こんな簡単なことに、なぜ私は抵抗を感じるのだろうか? そう自分に問いかけてみて初めて気付いたのだが、「オンライン・デーティング」が問題というより、私はきっと日本にも古くから続く「お見合い」というコンセプトが個人的に嫌いなのだと思う。30歳代以上の人にとっての真剣なオンライン・デーティングは、近所の世話好きなおばさんが持って来る見合い話と基本的には同じだ。どちらも学歴や収入など条件の合う人を先に選んでから、結婚を前提にお付き合いする。違うのは紹介者であるおばさんの有無だけだ。おばさんがいれば相手の素性や評判を先に調べてくれるので、相手が嘘をついているかなどはオンラインより確実にわかるし、お見合いならおばさんが代行してくれる相手の吟味や、おばさんが装飾して相手側に伝えてくれる自分のPRを、オンラインの場合はすべて自分で行い、おばさんの付き添いなしで相手とご対面する。細かいディテールは異なるが、両者のコンセプトは同じである。決定的な違いは、お見合いは昔からあった習慣なので、「世間に対して言い訳する必要が全くない」ことくらいだろう。オンラインに登録する以前にクリスが「もしオンラインで出会った相手と万が一結婚した場合、どこで出会ったのかと他人に聞かれるたびに、答えを躊躇するかもしれない自分を想像してしまうことが悲しくない?」と言ったことがあるが、日本の見合いにそういう感が少ないのは、歴史に裏付けられた世間体の違いなのだろう。
まあ、それはともかく、大人気のMySpace.comといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に参加することすら躊躇してしまう私には、デーティング・サービスに自分を登録して、まったく知らない人達を文字と顔写真だけで選考した後に、その相手とふたりきりで会う……、というコンセプト自体がどうしても受け入れられない。「私はコレコレこういう人なので」、と文字で自分のキャラを説明することによって最初から自分にレッテルを貼ることも嫌だし、適当に書いたことに対して「それならば、ぜひ会いたい」と言ってくる男とデートしたいとも思わない。もっと単純に言うなら、「4,000万もの人々のように素直にその行為を楽しむこと」が、私には「できない」のである。
結局のところ私は、そこまで自分の好みをわかっているくせに、「時間を無駄にしている」とか、「そんなことをしている間に40歳になって、子供も産めなくなるよ」などと言われると「そうなのかなあ……」と簡単に迷ってしまう自分の弱さが情けないのだと思う。自然に訪れるべき運命の出会いを信じたいなら、迷わず信じろよというだけの話なのに、まったく人間とは意思の弱い生き物である(笑)。
前述した記事の中には小さかったけれども、アメリカでは既婚者の63パーセントが「友人、知人を通じて何らかの形で相手と知り合った」ということも書かれていた。どんなにデーティング・サービスが流行っていても、未だに大勢の人達がオンライン以外の方法で出会って結婚しているのだ。私のようなオールド・ファッションな人にも希望はまだある、ということではないか。だから、「待っているだけでは乗り遅れてしまう」と周囲に心配されながらも、私はまだ当分の間、待ってみようかと思っている。少なくとも、週末に予定されているパーティーが終わるまでは待つつもりである(笑)。
第36話 「無防備な出会い」
「素敵な人との出会い」を期待している時には、どんなに努力しても誰とも出会えないが、「今は誰とも付き合いたくない」と思っている時や、「それどころじゃない」というほど忙しい時に限って劇的な出会いがある……、という話を独身女性ならば一度くらいは聞いたことがあるだろう。私も人からそれを言われるたびに、「チッ、何言ってんのよ。私なんていつも貧乏暇なしなのに、出会いなんて全然ないわよ!」と思っていたのだが、今はこの説は正しい、と思う。なんと、私にも同じ状況でようやく出会いが訪れたのだ。祝!
それは私が極寒のアラスカへの1週間の取材旅行からクタクタになってシアトルに戻って来た夜のことだった。自然環境に関する取材だったので、ほとんどが寒い屋外での仕事という過酷な状態だったが、取材の内容は満足できるものだったので体の疲れに反比例して気分は良かった。だから、空港から自分のアパートへ着いてすぐに熱いお風呂に入り、茹でダコのように温まったところでキューっと冷たいビールを飲んで、「いやー極楽、極楽。自然もいいけど、やっぱり私は都会がいいな」などと、ひとりごちながら上機嫌でソファに寝転んでテレビを見ていた。すると、タイミングを見計らったように女友達のEちゃんが電話を掛けてきた。
「秋野、帰ってきたの? 久しぶりにYちゃんがシアトルに来ているから、今からみんなで友達のパーティーに行こうよ」と言う。今からと言っても既に夜9時を回っていたし、アラスカから帰って来たばかりの私はソファーから起き上がれないくらい疲れていたので、「Yちゃんには会いたいけど、今は疲れていて出掛けられないよ。もう寝ちゃおうかと思っていたところだもん」と言って誘いを断った。するとEちゃんは、「そんなオバサンみたいなこと言ってたら何もできないし、誰にも会えないよ。Yちゃんも明日にはヨーロッパに帰っちゃうし、とにかく今からすぐ迎えにいくから出掛ける用意しといてね」と言って強引に電話を切ると、Yちゃんと一緒に私のアパートまで本当にすぐに迎えに来た。迎えに来た以上は友人を待たすわけにはいかないので、私はお風呂とビールで赤くなった顔にさっと超適当な化粧をして、普段着のまま急いでEちゃんの車に乗り込んだ。普段なら「そんな格好でベルタウンには絶対行かない」という組み合わせだったが、思考回路が既にストップしていた状態だったので、仕方なくそのまま出掛けたのだ。
パーティー会場はベルタウンにある某バーだったので、店に入っていくとEちゃんの友人達がすでに大勢で盛り上がっていた。Eちゃんは、私とYちゃんを自分の友達に簡単に紹介すると、そのまま友達と話し始め、Yちゃんは飲み物を買いに行ったので、私は3人分の席を確保するためにキョロキョロと探し始めた。すると数分前に紹介されたばかりのEちゃんの男友達であるポールが、私に代わって3人分の席とテーブルを確保してくれたのでお礼を言うと、自然にその場で会話が始まった。ポールはEちゃんの友達だとわかっている安心感からなのか、それとも自分が極度に疲れていたので普段よりも知らない男性に対する警戒心がなかったからか理由は定かではないが、初めて会ったというのに昔から知っていたような気がするほどポールとは妙に話が合った。笑いのツボと物事に対するシニカルな見方が私と同じで、ファッション・センスも好きなことも自分と趣味が似ているのだ。なんだか、まるで学生時代の同級生にばったり再会したような不思議な感覚だった。会話の途中でふと自分の普段着と、マスカラさえ付けていない状態の顔に気付き、「こんな時に限って話が合う素敵な人と会っちゃうんだよなあ」と少々情けなくなったが、今さら家に帰って着替えるわけにもいかない。
そこにYちゃんが戻って来たので、私はポールに失礼してYちゃんとふたりで話し始めた。それ以上、彼と話し続けるのも、初めて会ったにしては長過ぎて不自然な気がしたし、Yちゃんとは普段めったに会えないので話したいことが山ほどあったからだ。おまけに私は普段着で、ほぼスッピンである。でも、Yちゃんと私が夢中で話していると、ポールが10分毎くらいに私達のテーブルにやって来ては、ちょっと何かを話して自分のテーブルに戻って行くのだ。何回か彼がそれを繰り返しているうちに気が付いたのだが、ポールが5回目くらいに私達のテーブルに来た後に、なんだか気が散って仕方がないので私はYちゃんに「なんか、ポールってすごく話は合うんだけど、ちょっとウザくない? 私達がふたりで会話を楽しんでいるのがわからないのかしら?」と言ってみた。すると彼女が「彼、わかっていても止められないのよ、きっと。だから、もう少し優しくしてあげたら? 秋野って、そういうところ素直じゃないからさ。どう見てもふたりとも、クリックしちゃった感じだよね」といって笑うので、そこで初めて私は「彼は私と話したいのだ」ということに気付き、突然ものすごく恥ずかしくなってしまった。いい歳をして「恥ずかしくなる」ということ自体が恥ずかしいくらいだが、その時は本当に顔から火が出るほど、自分の鈍感さとYちゃんに指摘された事実がとんでもなく恥ずかしく感じたのだ。「私としたことが……」という感じと言えばいいだろうか。
でもYちゃんのおかげで、帰り掛けにポールが私を出口まで追い掛けて来て、自分の電話番号とEメールを書いた紙切れを渡し、「どうしても、もう一度会いたいのでお願いだから連絡して欲しい」と言った時には、「なんだこいつ、変なヤツだな」とか「みんなに電話番号を渡してるんだろうな」と思うこともなく、とても素直に「OK」と言うことができた。今時、私の電話番号やメルアドを聞かずに(聞かれても普段の私なら教えないが)、自分のものだけを渡す方法も、私にはポイントが高かったように思う。
そして2日間、「そうは言ったが、実際にメールを送るべきか、送らないべきか」を女友達に相談しまくった。すると相談した全員が「初対面でそんなに気になる男と会うことは滅多にないから、グリーティング・メールくらいは送ってみろ」と言うので、私は彼に超短いEメールを送った(会えて楽しかったというグリーティングのみ)。すると、すぐに私にとっては超理想的な返事が届き、何度かメールと電話で話した後に初デートをし、セカンド・デート、サード・デート……と続き、いつの間にか、仕事以外はほとんど毎日一緒にいるという信じられないような状況に。自分でも「私のような人にも、こんなことが起きるんだなあ」と不思議に思うが、周囲の女友達はみんな「秋野にさえ強烈な出会いがあるんだから、私らにも必ず訪れるはず」だと妙に勇気づけられたと言っている(笑)。
他人から何かを得ようと期待していない人の方が、期待している人よりもずっと美しく見えるというのは至極単純な事実だと思う。男女の性別に関係なく、自分の相手を必死に探そうとしている状態の人は、たとえ無意識でも、その場にいる人をつい品定めしてしまう傾向がある。男性陣に聞くところによると、「その場にいる男性を片っ端から無意識に品定めをしている女性」ほど他人の目に醜く映るものはないそうだ。だから、洋服にも髪型にも気合を入れて出掛けた時よりも、それほど気張らないで普通に出掛けた時のほうが、なぜか良い男に声を掛けられる確率が高いことがあるのだろう。そういう気合の入っていない時には、自分が今現在フリーだということを必要以上に公共の場で口に出したり、他の女性に対して妙に殺気立つこともないはずなので、多くの人とスムーズに出会えるのではないだろうか。
最近、周囲の女友達の間でよく出る話題は、「いかにして気合を抜いて出掛け、素敵な出会いに結び付けるか」である。この場合、一番難しいのは、「いかにして極自然に充実した多忙状態を作り、いい感じに気合を抜くか」ということだと思うが、それが最初から簡単にできるならば誰も苦労はしない。だから、とりあえずは私に偶然起きたケースのように、自分の仕事に今以上に精魂込めて気合を入れ、他のことには「気合を抜かざるを得ない状態」にまで持っていけば状況が変わる人もいるかもしれない……。
第37話 「習慣というもの」
今、出張で1年振りに東京に来ている。
私が言うまでもないが、東京は忙しい街だ。東京に来ると何だかやたらと焦ってしまう。出張の間だけレンタルしている携帯電話がひっきりなしに鳴り、次から次へと打ち合わせが入り、上ったり下ったり走ったりしながら急いで地下鉄を乗り換え、まさに息をつく暇もない。毎朝7時半に起きて仕事をしているのに、ハッと気付くと夜の7時になっている。東京ではシアトルの10倍くらい時間が速く流れているように感じてしまう。ペースが速いだけでなく、飲み屋が朝4時や5時まで開いているのも困ったものである。これでは疲労困憊しないほうがおかしい。
帰国するたびに「売れっ子ライターでもないのに、東京に帰って来ると何でこんなに忙しいのだろう?」と疑問に思う。でも、たまに帰って来る私だけが特別忙しいのではなく、東京で働いている人はみんな忙しいように見える。それが、3分間隔で時間通りに走る電車のせいなのか、いろんな機能が付いた高性能な携帯電話のせいなのか、私の業界に限ったことなのかはわからないが、大勢の人達が文字通り分刻みに予定を立て、しかも異様なほど長時間働いている。たとえば昨夜あった仕事絡みの食事&飲み会は、開始時間が夜8時半で、全員が揃ったのは夜11時を回ってからだった。最後に到着した人は別の会に出席して遅れたのではなく、大急ぎで仕事を終わらせて駆け付けたのだが11時を過ぎてしまったと言って謝っていた。日本人は本当によく働く。シアトルだったら、こんな遅い時間に仕事絡みの集まりなどあり得ないし、たとえあったとしても、たぶん誰も来ないだろう。
そんなわけで、シアトルでは周囲から働き過ぎだと頻繁に注意される私でも、東京に来ると自分が全然一生懸命働いていないような気がしてくる。東京のパワーはすごい。きっと人々がこんなに働くからこそ、流行にも敏感でエキサイティングな街であり続けられるのだろう。
基本的に私は、そんな東京が大好きだ。でも、アメリカ暮らしの長さに比例して、帰国するたびに“驚くこと”がどんどん増えてきたような気がする。中には東京で毎日通勤していたころは当たり前のように受け止めていた事柄も含まれていて、そのひとつが通勤ラッシュ時の電車内の状況だ。痴漢や変態でもない限り、「ラッシュ時の車内が大好き!」なんていう人間はいないとは思うが、公共の乗り物が発達していない車社会アメリカから東京に戻って来ると、朝の通勤ラッシュの車内の状況にうまく対応できない。人と人との距離が近過ぎるのだ。他人の顔と身体が自分にぴったりくっついてくるので、どんなに晴れた美しい朝でも非常に不愉快な気分にさせられる。男性にも女性にも意地悪な態度や非常識な行為(肘で他人を押したり、髪を引っぱっても謝らないなど)をする人が車内に多いことが納得できるほど劣悪な状況だ。日本における1年間の自殺者数が異様に多い理由は、朝のラッシュ時の車内状況にもあるかもしれない。
長年のアメリカ暮らしで日本人としての忍耐力が弱まったのか、根性に対する美徳感が消えかけてしまったのか、今の私にはこの車内の状況が受け入れられない。以前は我慢できたことが我慢できなくなったのは、加齢も影響しているだろうが、やっぱり“慣れ”が一番大きいと思う。本当に我慢ができなくて、近距離なのにもかかわらず、このケチな私が750円も余計に払ってグリーン車に乗ってしまったほどだ(笑)。アメリカ移住後は、東京で働いていたころよりも年収がさらに低いのでグリーン車代はとても痛かったが、気分が悪くなるほど物事を我慢するのは健康に悪いと判断し、“座れないのにグリーン車代を払う”という非常に納得いかない行為を決行した(空席があってもなくても750円なのだ。超不満)。とは言っても、私は帰国している間だけだからまだ良いが、みんなは一体どうやって毎日我慢しているのだろう? 自分が我慢していた当時の理由を忘れてしまったので、単純にラッシュ時の劣悪な車内状況に驚いた私だが、習慣というものの強さにも驚かされた。
習慣の違いといえば、帰国するたびに「やたらと他人から太ったねと言われる」というのがある(笑)。日本の女性達の美しさのスタンダードが相変わらず「小さくて非常に細い」ので、アメリカでは普通サイズか小さい私でも、東京に戻ると毎日「私はとても太っているのだ」と嫌なほど認識させられる。帰国初日に家族に再会したら、まず「あら、また太ったね」と言われ、久しぶりに会った女友達には「ちょっと太った?」とか「雰囲気がすごく丸くなったね」と言われる。実際に昨年よりも少し太ったので、その辺りまでは別にそれほど気にならないが、大して仲が良いわけでもないクライアントに「あれっ、太りました?」と言われたりするのは、かなり不愉快である。
数日前なんて打ち合わせに出掛けた先で、「ご無沙汰しております」とか「お久しぶりです」とか「お元気ですか」と挨拶する前に、男性のクライアントからいきなり「太りましたよね?」と言われて、とても悲しくなった(笑)。それほど「私は太った」という事実に確信を込めた「ましたよね?」という日本語をわざわざ使用してまで、私という他人の体型に関してコメントする必要があるのだろうか? 以前にもこのコラムで書いたが、アメリカでそんなことを他人にコメントしたら社会的に問題になるので誰も他人の容姿に関して自分の意見を言わない。その状態にすっかり慣れてしまった私には、おじさん達からの「太りましたよね攻撃」は決して“私に対する親近感”とか“私の健康を気遣う余りの心配”から出た言葉だとは受け取れなかった。だいたい赤の他人の容姿を、なぜそこまで気に掛けるのだろうか? まあ、この他人からのしつこいほどの「体型に関する指摘」が日本人の百貫デブ化を防いでいる可能性が高いので(アメリカの巨大人間化に比較して)、それを悪くは言えないが、何よりも先に「太ったね」と言われてしまうご挨拶を久しぶりに連続して受けて、いちいちショックを受けている自分に驚いたのだと思う。東京で働いていたころにも言われたことはあるし、言われている人を頻繁に見ていたのに、そのころは別にムカつくことはなかったのだから、習慣とは恐ろしいものである。
驚いたことやギョッとしたことを挙げていったら切りがないのでこの辺にするが、習慣や感覚の違いは諸所に生じても、東京はやっぱりおもしろい。これだけ刺激のある街で仕事をすると触発される機会が多いし、今回の出張では仕事を通じて30歳代や40歳代でいい仕事をしている超カッコイイ独身女性達とたくさん出会えたので、それぞれの女性から元気をもらっている。だからシアトルに戻るのを躊躇する気持ちもあるのだが、そろそろ疲労とストレスが溜まってきたので、通勤ラッシュがなく、他人から太ったと言われることもなく、朝から夜中まで連続して働かなくてもいいシアトルに帰りたくなってきた。東京は今週から桜が咲き始めたけれど、シアトルの桜はもう咲いているのだろうか。穏やかな春のシアトルが楽しみだ。
第38話 「友達の気遣いと私の気遣い」
「ちょっと、ポールとはどうなのよー? ちゃんとうまく行ってるの?」
という質問が最近、私の周囲では「やあ」とか「元気?」という挨拶代わりになっている。
この質問をされるたびに、私はどんな些細なディテールももらさず、ポールと私が今どれほど上手く行っているかをきちんとみんなに説明している……わけがない。基本的に独身の女友達の誰ひとり、「うまく行っているカップルの話」なんて事細く聞きたくないからだ。そんな話を聞いても、ちっともおもしろくもうれしくもないことを、つい最近まで彼がいなかった私自身が一番よく知っている。
だいたい、自分の女友達とその彼が、「具体的にどのくらい上手く行っているか」という話を本気で聞きたいと思う独身女なんているのだろうか? 私がポールと付き合い始める前までは、誰か身近なカップルの話になると、いつもみんなで「あー、そんな楽しい話、聞きたくないよー」などと言っていたし、一緒に飲むと必ず「私よりもあんたに先に彼ができたら殺す」と言っていた女友達までいたのだ。だから、上手く行っているカップルの話を聞きたい独身女なんて、多めにみても全体の約20パーセントというところではないだろうか。自分の女友達が「ひとりの人間として毎日を幸せに生きているか」ということを気に掛けるのは大切だが、「女友達が今どれほどラブラブか?」というディテールを聞いて楽しいかどうかは、まったく別問題である。
だから私は冒頭のように尋ねられるたびに、できるだけその話題が長くなり過ぎないように心掛けている。でも、そうは言っても、どのくらいの量なら短くて、どのくらいなら長いのかは個人の感覚により異なるので、実際のところ私の努力がどれだけ実っているのかは全然わからない。もしかしたら友人達からは、私がポールの話をし過ぎてウザいと思われているかも知れないし、あまり話さないから水臭いと思われているかも知れない。こういうことって、とても微妙だ。
たとえば先日、某女友達と久しぶりに一緒に飲んだ時にも、「ポールとどうなっているの? 今回はうまく行きそうなの?」と聞かれた。だから、「うん、まあ上手く行ってるよ。毎日楽しいし」と、あっさりめに答えた。それを受けて彼女は、アメリカ人の常識にもれず、満面に笑顔を浮かべながら「I’m soooooo glad to know you’re damn happy」(あなたがメチャクチャ幸せだと知って、とてもうれしいわ)と言い、そのセンテンスの最後に笑顔のまま「, you bxxch!」(まったく嫌な女!)と付け加えたので、私は正直でいい女友達を持っていることを改めて認識し、それに対して感謝した(笑)。でも真面目な話、それが実際のところ親しい友達の本音だと思う。「仲良しのあんたが幸せなのはすごくうれしいけど、ちょっとムカつく」という感じが一番近いのかも知れない。
こういう風にはっきりと言ってくれる友達がいないと、「誰も聞きたくねーよ、そんな話」っていう雰囲気が読み取れなかった場合などに非常に困ることになる。この前、友人のパーティーにてヨーロッパ系の彼と現れた女性が「彼がいつも“ハニーは何もしなくていいんだよ”って言うから、家では何もさせてもらえないのよお」と甘ったるい声で発言し、私を含めた周囲の女性陣が一斉に早送りの引き潮のごとく彼女のそばを離れたという出来事があったが(笑)、幸せ過ぎて場の雰囲気が読めないというのは恐ろしいことだと実感した。その女性には「そういうことをそんな口調で話すのは止めなさいよ」と注意してくれる友達がいないのかもしれない。
そういえば、日米親善関係のパーティーなどで「うちのがね、いつも気を遣ってくれるから、うちでは全部……」などと、周囲の女性達がしらけきっているのに夫の自慢話を延々と続けているイーストサイド駐在系マダム(仮称)※を目にすることがあるが、あれもどうかと思う。余談だが、なぜ彼女達が夫の功績を“まるで自分の手柄”のように鼻高々と自慢するのかも謎である(笑)。イーストサイドには、シアトル在住者にはわからないルールがあるのかもしれない。そんなことはともかく、周囲に引かれてしまわないように、話題選びには気を付けなければと思う今日このごろである。
さて、ポールと付き合うようになってから、私の生活の中で何が一番変わったかといえば、それは「独身の友達からの電話の数が極端に減ったこと」だ。しかも、男女問わず。これは私にとっては一大事である。私の独身女友達は、みんな美しくてスマートで常識があるので(持ち上げ過ぎか?)、付き合い始めて数ヵ月のラブラブなカップルが「今なんどき何をしているかわからない」という状況下において、大して急用もないのに夜に電話なんて掛けて来ない。また、独身の男友達は「俺がお前にしょっちゅう電話を掛けて飲みに誘ったらポールが変に思うだろ?」と言い、全くと言っていいほど電話を掛けて来なくなった。私と彼がふたりだけで過ごす時間を気遣ってくれるのはうれしいが、正直言ってこれは私にとって“ものすごく辛い”変化である。
私はこう見えても案外寂しがりなので(笑)、友達と一緒に過ごすことが何よりも大好きだ。今までの人生も友達に支えられて生きてきたと思っている。アメリカ人の友達は、未だに文法や言い回しを間違えながら変な発音で生意気に英語を話す私でも、全然気持ち悪がらずにそばにいてくれるし、日本人の友達は言葉の壁や外国人としての不安、孤独感をシェアできるだけでなく、私がへこんでいれば励ましてくれる。どうしてもひとりで夕食を食べたくない夜には、いつも女友達が「いいよ、一緒に食べよう。どこ行く?」と言ってくれるし、死にたくなるほど寂しい気分の夜に電話すれば、たとえ忙しくても長電話に付き合ってくれる。家族や親戚、同じ中学や高校を卒業した気の置けない友人が誰ひとりいないアメリカにて、自分ひとりで生活する日々の中、もしアメリカで出会った今の友達がいなかったら、乗り越えられなかった壁は数え切れないほどあると思う。だから、彼ができたがゆえに「友達からの電話が極端に減る」とか「友達との距離が少し遠くなる」とかいうことは、私にとって大事件なのである。
ポールと付き合う前までは、私に男がいても、私の生活は全然変わらなかった。ポールと出会う前に私がしばらく会っていた男の時は、友人達の誰ひとり、そいつのことを“目に入らない”または“気にも留めていない”様子だった。その男のさらに前に付き合っていた男(私本人は大熱愛だと思って盛り上がっていた10歳以上年上の男性)の時なんて、周囲の独身友達は揃って私のことを「じじいキラー」と呼び、「ねえ、じい様と会うより一緒にパーティーに行こうよ」とか、「お前、今日もじいさんと会うのかよ。やめとけ、年寄りは」とか、そんな感じで、とにかく男がいてもいなくても、全然私の生活環境は何も変わらなかったのだ。それなのに今回は違う。なぜか、みんなが静かなのだ。この友人達の対応が変化した理由は何だろう? どこか「今度の男は今までとは違うぞ」ということを、私よりも周囲の友人達のほうが敏感に嗅ぎ取っているのだろうか。
理由が何であれ、とにかくあまりに電話が鳴らないので、すっかり寂しくなった私は、片っ端から友達に電話を掛けてみた。誰も掛けて来ないなら、自分が掛ければいいのだ。そんなわけで、私は何人かの友達を誘って久しぶりに飲みに繰り出し、みんなが電話を掛けてこない理由を探ってみた。結果は思った通り、みんな「今回は何だかちょっと違う」と思っていて、「だから邪魔をしないように」しているらしい。ありがたい心遣いだが、「特に週末は彼との予定があるだろうから、誘わないようにしている」というのを聞いた時は、ちょっとショックを受け、「えーっ? 最初から決め付けないで、いつもみたいに私も誘ってよー。寂しいよー」と私は思いっきり不満を述べた。すると友達のひとりが「私だって淋しいよ。でも、もし彼と出掛けるからって言われて断られたら、もっと悲しくなるじゃない? 自分だって嫌だったでしょ?」と言われて、もっともだと納得した。シングルの友達が私を誘った時に、もし私が「ごめん、ポールと約束してるの」と答えたら、「ごめん、取材が入っているから無理」と言われるのとは違って、グンと寂しく感じてしまう。そんな思いをするのはできる限り避けたいから、「最初から誘わないほうがいい」というわけである。
全く、こんな基本的かつ大事なことに気付かなくなるなんて、私は一体どれほどのぼせていたのだろうか? 自分の状況の変化に舞い上がって、みんなの気遣いにも気付かず、相手の気持ちを汲み取ることも忘れていたなんて、とんでもないことだと深く反省した。冗談ではなく本物の「Bixxh」にならないためにも、今後はあまりのぼせないように気を付けようと思う。でも、誰も意図的にのぼせるわけではないから、これって結構難しいかもしれない……。
※シアトルから湖を挟んで東側、ベルビューを中心とするイーストサイド地域は、家族持ちの日本人(特に日本企業の駐在員)が多く住むことで知られている。
第39話 「35歳から死ぬまでに必要な金額」
昨夜、近所に住む女友達のA子が「なんだか、ものすごく落ち込んだ……」と言って、ワインを持って家に遊びに来た。フリーランスの私にとっては平日と週末の夜にそれほど違いはないが、彼女はきちんとした会社にお勤めしている会計士なので、平日に私の家に遊びに来ることはほとんどない。ということは、昨夜は相当へこんでいたわけだ。
オリーブをつまみながらワインを飲み、最初は「今日は仕事でこんなことがあった」とか、「早く週末にならないかなあ」とか、そんな取り留めのない話をしていたのだが、A子がフッと、「ねえ、秋野はフリーランスだけど、来年の収入とか10年後の収入とかを今よりも多く稼げるどうか、心配になることない?」と聞いてきた。なんという愚問だろう。そんなもの、“ものすごく心配している”に決まっているじゃないか。私は、「もちろん心配してるよ。ひどい時は1週間に1度くらい自分の将来が不安になって、人生の選択を最初から全部やり直したい気分になるほど」と、別に威張ることではないが思いっきり胸を張って答えた。
伴侶や両親からの金銭的サポートがまったくなく、自分ひとりだけの収入で生活している私達のような独身者で、“来年の年収”を本気で心配しない人なんているのだろうか? 「来年はこの仕事がないかもしれない」とか、フリーランスならば初めてお仕事するクライアントが「約束通り入金してくれず、家賃が払えなかったらどうしよう……」とかいう不安は常につきまとうはずだ。私なんて、たまにどうしようもなく不安になって、思わずツーッと涙がこぼれてしまうことさえある。
とは言っても、来年の年収を不安に感じる“不安量”のようなものは、人それぞれ生活環境によって全く異なると思う。以前、私が業界女性達の親睦会でポロッと経済的に不安定な生活に対する不安を口に出した時、同様にフリーランスとして働く女性達が、「そんな心配しなくても絶対何とかなるわ! あなたは心配し過ぎよ」とか、「私もちゃんと生活しているんだから、あなただって大丈夫!」とか言って大いに励ましてくれたことがある。でも、私が「じゃあ、あなたもこれこれこういう状況なの?」と具体的に自分の例を出して質問してみると、強く励ましてくれたひとりは親に全額援助してもらった頭金でシアトル市内に一軒家を所有しており、いざとなれば銀行から借金できるだけの資産を持っていたし、もうひとりは祖母の遺産で買ったコンドミニアムをベルタウンに所有していたし、最後のひとりは毎月$1,500の家賃と毎月$250の医療保険は旦那が全額払っているというケースだったので、ここでいう「私達のような」というカテゴリーからは除外したいと思う(笑)。
とにかく、私が胸を張って「もちろん心配だ」と答えるのを聞いた友人A子は、ゆっくりと首を振りながら大きくため息をついて、「やっぱり、ひとりって不安だよね……。パートナーがいれば、ここまで心配しなくてもいいんじゃないかって思わない?」と、言った。「……うん。そう思うこともよくある……」と正直に答える私。どんなに独身という自由を謳歌していても、経済的に先が見えない不安から、自分が選択してきた人生に対して弱気になることは多々ある。結婚すれば経済的にラクになる保障はないのに、結婚している人達は全員、自分よりも経済的に安定しているように見えたり、「あの時細かいことを気にせずに、あの男と結婚していたら、今ごろどうなっていただろう?」などと、過去に自分が選択した結論を後悔することすらある。こういうことを考え出したら最悪だ。
“自分が選択したことを後悔する”という行為は、私を含めた30歳を過ぎた独身女達が“妙に弱気に気になった時”にやってしまうことが多いが、これだけはしてはいけない。これをやってしまうと、そこから先に進めなくなるからだ。だから、どうしても後悔してしまう時は、その相手との別れを決心した理由を必死になって思い出そう。これだけは言えるが、弱気になった時に昔の男と寝たり、うっかり寄りを戻したりしないほうが懸命だ。そんな気分の時は、すぐ女友達に電話して「あの男に電話を掛けてしまいそうだから、私を止めてくれ」と頼むか、無駄話をして気を紛らわすに限る。私の周囲にもそれを重ねて難を逃れた女友達がたくさんいるが、頑張って無事に切り抜けた女達には自然に次の彼ができ、今でも昔の男との関係をきっぱり切れない複数の女友達には何年経ってもステディーな彼ができない。たぶん、付き合い始めた男性が昔の彼女と「今は友達なんだから問題ないだろ?」と言って頻繁に会っていたら、それに対して心から良い気持ちはしないように、昔の男とすっぱり切れない女性も相手にそう感じさせるからだろう。だから、時間つぶしで付き合う相手ならともかく、本気で付き合いたい男が現れたら、とりあえず昔の男とふたりで会うのは止めたほうがいいだろう。
話題が完全に本題の“経済的不安”からそれてしまったが(笑)、自分の周囲にある不安材料を心配し始めると現状がさらに不安に見えてくるので、私もできるだけ気にしないように毎日をポジティブに生きようと努力している。でも、やはり“年収”とか“安定”に関する話題を正面から投げられたら無視はできない。ああ、なんて重い話題だろう。だいたいA子が、独身女にとって「認めたくないけれど、認めざるを得ない超現実的な不安材料」を話題にしたのが悪いのだ。A子は在米歴が長く、アメリカの会社で働いているが、普段から『日経ウーマン』とか『日本経済新聞』などもこまめにチェックしている数字に強い女だ。彼女が落ち込んでいた原因は、偶然に目にした「35歳からの残りの人生に、いくら必要か?」という見出しの記事を最後まで読んでしまったからだという。その見出しを聞いただけで私もかなりひるんだが、その記事によると日本の平均的な35歳の独身者が85歳までの50年間に必要な金額は、なんと1億5,000万円だそうである。
「えっーーーーーー!? そんなに掛かるのぉぉぉぉぉぉー? 冗談じゃないわよおぉぉぉぉぉぉ!」と、思わずアパート中に響き渡るような大声を出してしまったほど私は狼狽した。1億5,000万円! い・ち・お・く・ご・せ・ん・ま・ん・え・ん・である。しかも、これは自分ひとりが85歳までに必要な金額であって、子供の養育費とか伴侶や年老いた両親に対して手助けをする金額等は全く入っていないという。その場合はもっと掛かるのだ。1億5,000万円という金額は単純に“独身者ひとり”が生き抜く金額の平均値らしい。全く、なんてことだろう! 私の今の年収では、こんな気が遠くなるような数字に達するわけがない。
だから私は、「この金額ってさ、きっと東京の六本木とか南青山に住んでる、めちゃくちゃエリートな独身者の年収に基づいているんだよ。私達のような平民の年収で計算してるんじゃないと思うよ」と、明るく現実を払拭する戦法に出た。するとA子は静かな微笑みを浮かべながらバッグから小さな手帳を取り出し、それを開いてから、「まず、日本の平均的な35歳の独身者は手取り年収400万円、年間支出315万円、年間貯蓄額85万円、現在の貯蓄額350万円とのことです」と、アナウンサーのような口調でメモを淡々と読み上げた。「えっーーーーー……」という情けない声と共に私はリビングの床に崩れ落ち、床にひっくり返ったまま「税金も年金も医療保険も差し引かれた後の手取りが400万円……、年平均貯蓄額が350万円……」と、壊れた機械仕掛け人形のようにブツブツと同じことを繰り返した。そんな私を見ながらA子はとどめを刺すように「手取り400万円の内訳は、家賃・共益費8万円×1年で96万円、生活費(外食を含む食費、光熱費、電話代、交通費、雑費、交際費、医療費等)12万円×1年で144万円、その他レジャー(服飾費、美容院代、旅行代等)5.5万円×1年で66万円、貯金約7.8万円×1年で93.6万円。そして30年間で使う生活費とは別に、貯金は35~65歳の30年間で約3,000万円になるから、66歳~85歳の20年間で国から支給される年金とその3,000万円を使い切って生活するって流れらしい」と言った。私はA子から内訳を聞いてショックが緩和されるどころか、「平均的な35歳は1年間に100万円近く貯金をしている」と知り、貯金や資産のない自己状況と比べてガーンと落ち込んだ。
A子は、「ねっ、落ち込むでしょ? これを聞いたら貯金ができる仕事に変えなきゃまずいと思うよね? それとも日本に帰ったほうがいいのかなあ。日本のほうが同じ仕事でも年収は絶対に高いし。でも、35歳を過ぎたアメリカ帰りの独身女を雇ってくれる会社なんてないよね……。とにかくお金を貯めなきゃ……」と、なんだか何かに取付かれたような勢いで話していたが、私はショックのせいかA子の話を聞きながら、だんだん笑いがこみ上げてきた。人間はどうにもならない危機に直面すると恐怖心や不安がなくなると聞いたことがあるが、それに似た心境だったのかもしれない。ふと我に返って、「お金が出て行くことばかり心配して、友人達に変な気を遣わせたり、人生を存分に楽しめないのは嫌だ」と思ったからだ。人生は1回きりだし、運が悪ければ明日車にひかれて死んでしまうかも知れない。だからこそ、将来のお金のことばかり心配し過ぎて、親しい友人が死ぬほど落ち込んでいる時に迷わず彼女の飲み代をおごってあげられなかったり、いつもとても世話になっている友人への誕生日プレゼントに少しでも安い品物を選んだり、友人に招いてもらったハウス・パーティーに手ぶらで参上するような感謝の気持ちを表せない人、つまり男性にも女性にもリスペクトされない人には絶対なりたくないと思った。たまに、そういうことをする独身女性を目にしてしまうことがあるが、それは悲しいだけでなく、女性の私が見ても引くのだから、男性が見てしまったら最後だろう。A子とは、かなり夜更けまで飲んでこの件について話したが、彼女も「お金は貯めたいけど、そういう困った独身女にならないように気を付けよう」という案に同意し、そのころにはすっかりふたりとも立ち直っていた。とりあえず良かった、良かった。
これは人から聞いた話だが、中国の風水ではお金はいいことのためにたくさん使わないと単になくなるだけだが、本当に大切な人のためにたくさん使えば、それと同額かそれ以上が自分に戻ってくるものだと言われているらしい。だから私も、たとえ85歳まで生き延びられる貯金がなかったとしても、人の道だけはそれずに、これからも日々を楽しみながら前向きに生きたいと思う。
第40話 「仕事で“女”を出す女達」
久しぶりに「最近これほど怒ったことはない」というような出来事が起きた。
私の仕事は通常、編集者と打ち合わせをした後は基本的に自分ひとりで取材のアポを取って、ひとりで取材に出掛け、原稿を執筆して提出するという流れだが、雑誌やムック本などでプロのカメラマンによる写真が入る場合は撮影にも立ち会う。アメリカ人のモデルが入るとか、日本から有名人が来て撮影する時とか、場合によっては現場に立ち会うだけでなく、私が撮影自体をコーディネートすることもある。
とんでもない出来事は、先日行われたある写真撮影の現場で起きた。その撮影は、「ちょっと、その辺を歩いている女の子に入ってもらいましょうよ」という低予算なガイドブック調の撮影ではなく、「このページには、このロケーションでこの衣装を着たモデルが2名入って、こういう小道具が必要で、天候はこうでなきゃいけなくて……」と詳細に明記された指示書に基づいた“きちんとした撮影”だった。しかも、日程も超タイトなうえに、その特集ページは15ページ以上あったので、「いくらメイクさんや日本からの現場スタッフがいても、特集の原稿執筆と撮影コーディネートの両方はとてもひとりではできない」と言って断ろうとしたら、日本の出版社が「ロサンゼルスの日系制作会社から私専用のアシスタントとして日英バイリンガル・スタッフをふたり送り込む」というので、それならばできるだろうと判断して仕事を引き受けたのだ。
撮影前々日にロサンゼルスから到着した日本人スタッフは、ふたりとも若い女性で、とてもかわいかった。たぶん20代前半だろう。声が高く、どこかベタベタ話すというか、甘ったるい感じが耳についたが、私が雇ったスタッフではないのでその点は諦めることにした。格好はロスに在住する今どきの日本の若者という感じで、片方は太めのショーツを太いベルトでファッショナブルに着こなし、もう片方はピチピチのローライズ・パンツを履いていて、失敗したのかわざとなのかは不明だが、パンツに下着のラインが見事にくっきり透けていた。「よろしくお願いしまーす!」と言って私に挨拶する仕方も、“腰から体を前に倒して頭を下げる本来の挨拶”ではなく、“ヨロシクと言いながらアゴを前に出すことによって一瞬だけ頭の位置が少し下がる”という上目づかいの挨拶だ。
今どきの若者はこんな挨拶でも制作会社に雇ってもらえて、シアトルまで出張させてもらえるのだ。時代はすっかり変わったんだなと、うらましく思った。私の時代は、本当に一人前になるまで先輩抜きで出張なんて行かせてもらえなかったし、こんな挨拶をした途端に、その後一切無視されるか、その場で足に蹴りを入れられたものだ(ホントに)。とにかく、数日間とはいえ私のアシスタントになる人達なので、「過去にどれだけ撮影を経験しているのか」とか「どんな内容の仕事をしてきたか」、「今回の仕事への自信はどれくらいあるのか」とか軽く聞いてみると、ふたりとも今まで何度も撮影を経験しているから、「どんな撮影でも全然、大丈夫です!」と自信を持って答えていた。ちなみに「全然、大丈夫」とは正しい日本語ではない(笑)。まあ、それはともかく、そんなに自信満々に言うのだから(私が同じことを聞かれても絶対に彼女達のようには答えられない)、挨拶が変でも、答え方が変でも、きっと仕事はできるのだろうと信じて、早々に役割分担を割り当て仕事に入ってもらった。
すると、どうだろう? 全然、仕事ができないじゃないか! 私よりもずっと若いはずなのにすぐ疲れてしまうし、すべての作業がまるで老いた亀のように遅いのだ。たとえば「XXXに関しては今すぐこうしてくださいね」と頼むと、「私、すごくお腹がすいてるんで、その前にお昼を食べて来ていいですか?」と言うし(ふざけんな! 仕事してから食え!)、「XXXの手配は何時にコンファームできるのかしら?」と聞けば、「そんなのわかりません。まだ相手から電話来ないんで」と言う。おいおい頼むよと思った私は、少々厳しい口調で「予定の時間までに電話が来ないなら、こちらからもう一度電話して! 明後日の撮影なんだから急いで対応してくれないと間に合わないわよ」と注意すると、「私だって急いでやってますよぅ! 相手が悪いのに私にそんな言い方しないでください」と口答えする。こちらがお願いしている事項に対して相手のせいにするとは最悪だし、急いでやっているように見えたら、こんな注意を受けないはずだ、とは考えないのだろう。ああ、バカは困る。
中でもヒドすぎて笑ってしまったのが、ひとりの女の子(A子)に「撮影スタジオBにこれを急いで運んで来て」と頼んだら、「はーい。でも外はものすごく暑いので、冷たいものとか買いたいんですけど」と言う。「じゃあ、買ってください」と言っても黙って立っているので「何なの?」と聞くと、「ジュース代とかぁ、そういう細かいお金は私が自分で立て替えなきゃいけないんですか?」と言うではないか。私はロサンゼルスから来た彼女達の雇い主ではないのに、私がお金を渡すのを待っているのだ。心の中では「お前、それは自分が飲むジュースだろう? そのくらい自分で出せよな」と思ったが、ランチとかジュースとか、小さなことでひとりのスタッフが機嫌を悪くすると全体の雰囲気が悪くなるかもしれないと思ったので「じゃあ、私が預かっている経費を少し渡しておくわね。$200でいいかしら? これでみんなの分も適当に買って来て。でも急いでね」と言って現金を渡した。
ここまで読んで読者のみなさんはすでに想像がつくだろうが、やはりA子は1時間以上経ってから自分だけランチを食べて手ぶらで戻って来た。気が利かない女というのは、こういう人のことをいうのだと思う。携帯電話もあるし、スタジオの電話番号も持っているのだから、買って来る内容を忘れたならば電話1本を入れて「今から戻りますが、何か必要なものはないですか?」と確認すればいいではないか? 1日目の半分にして私は彼女達について「こいつら、よくアシスタント業で生活が成り立っているなあ……。一体どんな特技があるんだろう?」と逆の意味で感心し始めた。
また、この業界(日本の会社と仕事をしている場合に限る)は、1日の仕事時間が異常に長いことで知られている。撮影日の直前が忙しいからという理由でロサンゼルスから送り込まれた彼女達は、シアトルと時差はないくせに夜7時ごろになると疲れてしまい、「もうホテルに帰ってもいいですか?」と聞いてきた。その日に終わらせなければならない仕事がまだ終わっていないのに、である。「どうしても今日中に終わらせないと明日大変なことになるから、頑張って終わらせましょう」と私が言うと、「じゃあ、何時ごろまで働くんですか?」と、すかさず聞き返してくる。「あなたたちのペースでやっていたら、たぶん12時くらいになるかも知れないわね。だから急いで!」と言うと、途端に嫌な顔をして、A子が「本当は私だって言いたくないですけど、私達すごく早朝の飛行機で来たんですよね。朝6時前に起きて、3時間近く飛行機に乗って。だから今日はそんな遅くまでは働けません。帰らせてください」と、ものすごくきっぱりと「NO」と言った。
世の中で“根拠のない自信”と“無知”ほど恐ろしいものはない。だから私はこういう人達とは戦いたくない。自分の時間や労力が無駄になるからだ。そういうわけで、仕方なく彼女達を早く帰し(笑)、ひとりで夜中2時まで働いた。彼女達はもちろん知らないし、聞いてもくれなかったが、その日の私の労働時間は朝8時から夜中の2時まで、つまり18時間労働だった。アシスタントのふたりよりも8時間(1日分)多く働いているわけだ。「こんな使えないアシスタントが来ることがわかっていたなら、この仕事は受けなかった」と深く後悔したが、すでに受けてしまったのだから絶対に最後までやらねばならない。それがプロ、仕事というものである。こんな自分には罪がない状況になっても言いわけはできないし、受けてしまった仕事はまっとうしなければいけない。だから翌朝も8時に撮影スタジオに入り、ひとりで準備を始めた。ちなみに彼女達は朝10時までスタジオに来なかった。
翌朝は彼女達を派遣してきたロサンゼルスの制作会社に「ご挨拶」と称して、さぐりの電話を入れてみた。アシスタントの彼女達はその制作会社の社員ではなく、外注のフリーランスで、私とは雇用主が異なるためアシスタントでも私のギャラとほとんど変わらないことがわかった(それは私を恐ろしく落ち込ませた)。しかも、ふたりともこんなに若く見えるのに、なんと30歳代で、私とは数年しか異ならない年齢(ひとりはたった1歳違い)だった。これは私にとってものすごくショックな事実だった。なぜなら、20歳代なら許されることは30歳代では許されないからだ。そうかと言って1日でできるようになるわけがないので、私にできることは何もない。仕事を続けるしかないのだ。
そうこうしているうちに朝10時にスタジオに現れたお嬢様2名は、「おはようございます! わあ、秋野さんって働き者ですね。昨日は何時まで働いていたんですか?」と聞いてきたので、「うーん、夜の2時くらいまでかな」と答えると、自分達だけ早く帰ってしまったことを悪びれる様子もなく、「秋野さんって仕事が好きなんですねー。そんなに働いていたらプライベートの時間なんてないんじゃないですかあ?」と、くったくない調子で返されて、私は固まってしまった。よく、そんな調子で目上の人に話せるものだ。1日18時間働いたら、プライベートの時間なんてあるわけないだろう。ムカついたのと同時にボーイフレンドのポールの顔が一瞬浮かんだが、アメリカ人の彼は私が仕事をし過ぎて家には寝に帰るだけの状態をおもしろく思っていないので最近はまともに話もしていない。だから、この子達にこんなことを朝っぱらから言われるのも仕方ないのかもしれないと思って、ますます不愉快な気分になった。でも、私がアシスタントだったら、自分の代わりに遅くまで働いてくれたボスに、朝っぱらからこんなことは決して言わないと思った。
撮影前日は前々日よりも状況はさらにひどかった。1日$50くらいしか私とはギャラが変わらないのに、彼女たちは何か自分に都合が悪いことが起きると「秋野さんからの指示です」と言って全部私のせいにする。「お前が指示を聞き間違えたんだろう!?」と心の中で怒ってみても、すでに終わってしまったことなので、どうにもならない。私が「いい加減にしなさい、このバカ!」と、はっきり怒れば良かったのだろうが、忙し過ぎてバカに構っている暇がなかったので流してしまい(笑)、自分でやれることを全部やって、そのまま撮影になだれ込んだ。
そして撮影日。1日に撮影する予定のロケーションが複数あったので、時間刻みでモデルやカメラマン達と民族大移動をし続けなければならなかった。私は撮影隊と一緒に行動するので、アシスタントのひとりがひとつ先の撮影現場へ先回りして入り、そこで準備をして撮影隊が到着するのを待つ。そして、もうひとりが撮影終了後の現場に残って後片付けをしてから、その次の次の現場へ先回りして準備をする、というローテーションになっていた。だが、彼女達はそれが予定通りにできなかったのだ。信じられないことだが、何度注意してもA子もB子も私の担当である撮影隊と一緒に行動したかったのか、いつまで経っても次の現場に先回りせず、撮影現場にある車の横に立ってモデルやドライバーさんと一緒にサンドイッチを食べたり、おしゃべりをしたり、名刺を渡したり、携帯番号を交換したりしていたからである。私のアシスタントとして仕事をするために現場にいるのではなく、現場に居合わせた「ただの“女”」(または関係者の家族、ゲスト、はたまたセックス目当てのグルーピー)のような行動に出てしまったのだ。この彼女達の行動は明らかに私の計算外だった。仕事ができないだけでなく、グルーピーのように自分のケータイとかメルアドとかをモデルやクライアントや関係者に渡してしまうなんて考えられない。
そんなわけで私の怒りは昼前には頂点に達していたが、実際にキレたのはふたつの出来事が連続して起こったからだった。ひとつはA子が先回りせずにまだ撮影中の現場に残っていたので「A子ちゃん、早く次の場所へ行って準備をしてちょうだい」と、3回叫んだ。それでも無視して聞いてくれないので、「どうするつもりなのかな」と思ってそのまま撮影を続行していたら、カメラマンが「大至急、ガムテープを持って来てくれ」と言うので、私は30メートルほど先に停めてあった機材車の横で出番待ちの男性モデルとおしゃべりをしていたA子に向かってメガホンを使って「A子ちゃん、今すぐガムテープを持って来て!」と英語で怒鳴った。現場にいた関係者全員に一発で私の指示が聞こえて全員がA子を見たが、彼女ひとりだけが男性モデルの腕に手を掛けて話し続けていて何も聞こえない様子だ(それだけ撮影に集中していないという証拠)。だから私はその後2度も同じことをメガホンで連呼すると、A子の近くにいたほかのスタッフがA子の元まで走って行って彼女の腕を取り、何が起こっているのか伝えてくれた。スタッフ全員が自分に注目していることに気付いたA子はあわててガムテープをつかむと、信じられないことに彼女は「私は何も悪くないの」というジェスチャーをするために大袈裟に首を横に振りながら、なんと“歩いて”私のほうへ向かって来たのである。
それを見て私はキレた。私は「A子ちゃん、走って!」とメガホンで叫んだが、彼女の足は競歩に近い“早歩き”になっただけだった。そして私は、アメリカの撮影現場でこれを言われたらスタッフ生命が終わりだという台詞である「A-ko, Run! Run means run, damn it!」(走れと言われたんだから、歩いてないで走れ、バカ!)と怒鳴った。A子は意味がわからなかったようだが、現場は拍手喝さいとなった。ほかのみんなもいい加減、彼女の仕事態度にムカついていたことがその拍手で証明されたわけである。彼女が撮影現場に再び雇われることは、少なくてもシアトルでは今後二度とないであろう。
もうひとつ、私がキレたのはB子の言動である。撮影現場を移動する時は基本的に車を連ねたキャラバン隊式で移動するのだが、一応、全ドライバーに地図のコピーを渡したうえで、「こんな感じでいきますので、よろしくお願いします」と出発直前に私が説明をする。その時は数ブロックしか離れていないビルの駐車場への移動だったので、全員がすんなり到着し、早速準備を開始した。でも、私の説明を聞いたうえでキャラバン隊よりも先に出たB子だけが来ていないので、どこかで迷ってしまったのだろう。10分ほど経って、私がそのビルの男性担当者とふたりで段取りの最終確認をしていると、その担当者の携帯電話にB子から電話が掛かってきた。私達のスタッフの携帯電話に掛けるのが常識なのだが、スタッフではなく、場所をお借りしているビルの担当者に電話をしてくるところ自体がすでに信じられないが、とにかく担当者が外に出てB子の車を探しつつ誘導して、無事にB子が到着した。まさか私が担当者の真後ろにいるとは思わなかったのか、たまたま私の姿が全く見えなかったのだろう。B子は車から降りたと同時に真っ先に担当者にこう訴えたのだ。
「ああ、XXさん! うちの秋野が私に全然違う道順を伝えたので、私はおかしいなと思ったんですけど、秋野が言った道順を信じたせいで道を間違えて遅れちゃったんです。ごめんなさい。私は悪くないんです」
これを聞いた私は、プツッという音がはっきりと聞こえた気がしたほどキレた。誰ひとり彼女が遅れたことを責めてはいなかったのに、それにもかかわらず彼女はこう言ったのだ。しかも私はB子だけでなく、スタッフ全員に全く同じ道順を教えて全員無事に現場に到着しているうえに、直前にいた現場とたった数ブロックしか離れていなかったのだ。その後、私がこの女と一切話さず、何もアシスタントには頼まずに全部自分ひとりで仕事をしたのは言うまでもない。信頼できないスタッフに大事な仕事は任せられないし、自分のミスによって立場が悪くなるたびに女の一番汚い部分を持ち出すような女とは絶対に一緒に仕事をしたくないからだ。ただひとつの救いは、そのビルの担当者が撮影終了後に私のそばに来て、「君の仕事は、自分の仕事のほかに若いスタッフの面倒も見なければいけないようで大変だね」と言って肩をたたいてくれたことだ。私が「気を遣ってくれてありがとう。でも、彼女は私のひとつ下だから、もう35歳なのよ」と本当のことを教えてあげたら、その担当者は「嘘だろう! 20歳そこそこだと思って面倒見てあげたけど、あれで35歳ならヤバいだろう……」と言って超驚いていた。
問題は山のようにあったが撮影は無事終わり、私のギャラよりも1日$50安いだけのギャラをもらったお嬢様ふたりは無事にロサンゼルスへ帰った。私は二度とこんな思いをするような仕事は請けないと心に誓いながら、今この原稿を書いている。あー、でも全部書いてすっきりした! 仕事の場で“女”を出してしまうために、女性の同僚や上司や部下とコラボレートして働けないA子やB子のような女はダメだよ。だから、そんな女達は放っておいて、“仕事の時は男になる女達”は、これからも最高の仕事を続けるべく体力をつけて精一杯頑張ろうね。あー、でも、まだちょっとムカついてるかも……(笑)。
第41話 「独身女が不動産を入手する条件」
この数日間のシアトルの暑さは尋常ではない。
通常のシアトルの夏は、軽井沢や北海道の夏のように適度に涼しいので、アパートや普通の家にはエアコンが付いていない。だから30度近くの猛暑で、まったく風が吹かないと家の中の人間は茹でタコ状態になってしまう。これでは、もう暑過ぎて当然仕事どころではない。確実に地球の温暖化が非常に早いスピードで進行しているのが、ひしひしと感じられる暑さだ。
どこか涼しい場所に避難したくても、近所のジムも、コーヒー・ショップも、バーにもクーラーがないし、車にもクーラーが付いていないので逃げ場がない。ダウンタウンの図書館は現地へ到着する前に暑さで溶けてしまいそうなので行く気もしない。だから、買い物もないのに冷房が効いた近所のスーパーマーケットの中をうろついたり、ショッピング・モールに行って涼んでいたら、ふと「なぜ普段から身を粉にして一生懸命働いているのに、アメリカではクーラーのある家に住めないのだろうか?」と思い、途端に情けなくなった。東京で働いていたころは、借りていたマンションには全室クーラーが付いていたし、オフィスは北極並みに冷房が利いていたではないか。
美しいワシントン湖沿いに建つ豪華なビル・ゲイツ邸や、シアトルの長者地主であるポール・アレン邸のような家が欲しいと言っているわけではなく、平民の独身女らしい、慎ましやかなワンベッド・ルームの中古コンドミニアム(日本でいう中古マンション)か、築100年近く経っている古くて小さな家でいいのだ。そして、自分の家を手に入れたあかつきには太陽エネルギーで作動するエアコンを設置し、日本式の洗い場が付いた風呂場を造り……と、夢は膨らむ。でも、一体いつになったら自分のプロパティー(不動産)が買えるのだろうか。
30歳代も後半に近づいたからだろうが、最近、私の周囲では働いている女性で自分のコンドミニアムや家を持っていない人のほうが少数派になってきた。独身女友達のイヴなんて、ラベンナ・エリアにものすごく素敵な家(花の咲く広い裏庭、庭に面したベランダに設置されたホット・タブ、人に貸せる2部屋&バスルーム完備の地下室付き)を所持しているが、先見の命がある彼女は10年前の28歳の時にこの家を約2,000万円で購入し、月々のローンの半分は地下室を学生に月極めで貸す家賃収入で返済している。10年掛けていろいろ手も加えた彼女の家は現在約5,000万円の価値があるそうだ(ヒエーッ!)。なんて賢い女だろう。私が28歳のころなんて、まだ仕事が一人前とは言えなかったこともあって(今も一人前と言えるかどうか不明)、家を自分ひとりで購入するというオプションが自分の人生にあるという“可能性”すら考えたことがなかった。これが賢い女と、私のようなバカとの大きな差なのだろう。
シアトルに住む日本人の独身女友達(30~40歳代)で不動産を所有している人の場合、私の知っている限りでは一軒家を購入した人はひとりだけで、あとはダウンタウン周辺にコンドミニアムを所有している。だいたい30歳を過ぎて購入を考え始めたようだ。シアトルを代表するM社など、大企業に勤める女性達の中には購入時に頭金用の貯金があった人もいるようだが、ほとんどの女性達は金額の差はあっても日本の両親から頭金を借りたり、もらったりしたようである。それでもみんな月々相当なローン金額をきちんと自分で返済しているのだから立派だと思う。しかも、その毎月の支払いがこの先30年近くも続くのだ。私は数字や法律に弱いので、あと何年アメリカに住めるかどうかもわからないのに、そんな高額なローンを組んで恐ろしくないのだろうかと人事ながら不安になってしまう。
私がそんな不安を口にすると、オーナー陣達(笑)からは「不安がない人はいないでしょう。でも現在のホットなシアトル不動産事情を考慮したら、あと何年アメリカに住むかわからなくても買った方がベター。日本に永久に帰国することになったら、その時点で売却すればいいし、売却したくなければリスクは高いけれど地元の不動産屋に料金を払って賃貸する手もある。あんたもグズグズしてないで早く買ったほうがいいわよ」と言われる。簡単に「あなたも買いなさいよ」と言われても、「そうですか、じゃあ、コレとコレ」と、魚や野菜を買うようには行かないので仕方ないが、みんな本当にいろんなことをよく勉強し、考えているんだなあ、と感心してしまう。同年代なのに、不動産を所持している人達は自分よりもずっと大人に見える。
私は確かに不動産は欲しいが、それに伴う他の要因にひとりで対処するのが不安だと思うタイプだ。仕事を最後までひとりでやり遂げるとか、ひとりで旅行へ行くとか、ひとりで外国に住むとか、そういうことはちゃんとひとりでできるのだが、英語で法律をきちんと理解するとか、外国で賢くローンを組む(つまり借金を作る)というのは、自分が得意な分野ではないので気が進まない。そんな高額な買い物をして、それに保険を掛けたところで、実際に火事や地震などの災害が起きたらどうすればいいのか、想像しただけで不安になる。ひとことで言えば、私はものすごく小心者なのだろう。
いや、もっと正直に言おう。私は「できることなら結婚して、家は相手と半分ずつ支払って購入したい」とか「もし夫が65%で私が35%くらいの支払い割合で家が買えたら最高かも」なんていう、めちゃくちゃ自分にとって都合の良いことを、どこかで夢見ているのだ。自分ひとりで買うよりも、伴侶と一緒に買う方が不安も少ないし……、なんて調子の良いことを考えているから、他の独身女友達のように不動産を所有できないのだろう。つまり、女として、人間として潔くないのだ。だから不動産もないし、かといって金持ちのボーイフレンドもいないのだろう。調子の良いことを考えてばかりいる人には、バチが当たるものだ。もしかしたら、今つきあっているポールが今まで私が付き合った男の中で堂々たる1位の座に輝く金欠君なのは、私の人生にとって深い意味を持つサインなのかも知れない(笑)。
独身で外国人で女という三重苦があるのに(注:条件の良いローンを組みにくい)、アメリカで不動産を所有する日本人の独身女性達に「よくそんな高額な買い物をする決心がついたわね」と、羨望を込めて質問すると、たいてい「独身で外国人で女だからこそ、不動産を買ったのよ」という答えが返ってくる。外国人でも不動産を所有しているほうがアメリカで生きていくなら有利だし、不動産があると何かが起きたときに銀行から借り入れできるそうだ。そして、みんなが共通して言うのが、“それに、いつまでも白馬の王子様が現れるのを黙って待っていても仕方ないでしょ?”ということだ。待たないことを決心した女達、他力本願でない女達。かっこいいではないか!
そういうわけで、私は自分の力でアメリカに不動産を手に入れた独身女性達に敬意をいだいている。自分の足で1歩ずつ前に進んで行くんだ、という意志が伝わってくるような気がするからだ。私も確かに小心者ではあるが、いろいろ願望はあっても基本的には他力本願タイプではないので(笑)、自分の不動産を手に入れたいと思う。そして、そんな高額な物件を購入するならば、郊外でも小さくてもいいから絶対に一軒家を購入したいと思っている。と、友人に得意気に話したら、「マネージャーがいるコンドミニアムと違って、一軒家は修理や日曜大工が必要なので女ひとりでは維持が大変よ。男手のなさを思い知らされると思うわ」と言われ、たいていの独身女性が一軒家を購入しない理由に納得した。「それに……」と友人は続けた。
「一軒家に女ひとりで住んだら、運悪く強盗や連続殺人犯に襲われた時に誰にも知られずに簡単に殺されそうだし、そのうえ何週間も誰にも死体を見つけてもらえないかも知れないじゃない……?」
うーん、あり得る。アメリカではかなりあり得る話だ。誰か一緒でないと、やっぱりちょっと怖い。
かと言って近々、救世主が私の目の前に現れるとはとても思えないし、たとえ何年も待っても待っても、一生誰も現れないかもしれない。または、たとえ素敵な人が現れても、その人が自分よりもさらに貧乏な可能性だってある(別称ポール。笑)。だから自分の中で不安と希望の中間線を見つけて、どこかで腹をくくる決心をつけるのだ。それができなければ不動産なんて手に入れられないだろう。つまり、「どこまで潔くなれるか」が、独身女が不動産を入手できる第一条件だと思うのだ。ちなみに私は今現在はまだ、そこまで潔くなれない。だから今もこうしてアパートで茹でタコのように赤い顔をしながら原稿を書いているのである。ああ、暑い……。一刻も早く、竹を割ったような潔い女になりたいものである。
第42話 「パブリックで話す私生活」
昨日の午後、近所にある銀行へ出掛けた。アパート暮らしの私には自宅に洗濯機がないため、いつもアパートの地下室にあるランドリー・ルームを利用しているのだが、そこにある洗濯機や乾燥機はクオーター(25¢硬貨)を入れないと動かない。しかも1回の洗濯につき25¢硬貨が9枚、2台分を1度に回すなら$4.50分ものクォーターが必要なので、いつも$20ほどまとめて銀行で両替してもらうのだ。
アメリカではベランダがあっても、日本のようにシーツやタオルを両手でパンパン叩きながら外に干すことができないので、クオーターがさらに多く必要になる。まだシアトルに引っ越して来たばかりのころ、「これくらいは平気だろう」と思ってアパートの窓からこっそりバス・マットを干したら、やっぱり大家さんに注意されてしまった。晴れた日に外に洗濯物を干せないなんて環境保護に反した慣習のような気がするが、人の国の慣習にあれこれ言うと叩かれるので、私はおとなしく銀行で両替し続けている。
でも銀行という大勢の人が集まる場所で、「すみません。クオーターに両替してください」とお願いするたびに、「洗濯機もないアパートに住んでいる」という事実を周囲に並んでいる人々にわざわざ知らせているような気がしてしまう。だから、私は銀行に行く度に心の中で「次に引っ越す時は家賃が高くても洗濯機のある家に住んでやる!」と誓いを立てるのだが、そんな小さなことで“いちいち誓いを立てている”こと自体がむなしくなり、クオーターの筒を手に握り締めて、頭を振りながら帰路に就くのである。ああ、イヤだ。とにかく一刻も早く洗濯機のある家に引っ越したい。
そういうわけで、昨日も両替をしてもらうために銀行の窓口の列に並んでいた。私の隣の列には、私と同年代くらいに見える知的な雰囲気の白人女性が並んでいたので、私はその人の横顔をぼんやりと見ていた。とてもきれいな顔をした女性だったが、何だか疲れているのか、少し神経質な感じに見えたからだ。「美人の白人女性がきつい表情を浮かべていると怖いなあ……」と勝手なことを考えていたら、突然その女性の顔がバラの開花のように一瞬にして輝きを増したので、私もつられて彼女が見ている方向を振り向いた。すると彼女は私の前方に位置する窓口で、銀行員とやり取りをしていた白人男性客に向かって「デイビッド!」と声を掛け、「あら、久しぶり! どうしてるのー?」と、よく通る声で明るくあいさつをしたのだ。
声を掛けられた男性のほうも「あれーっ?! ものすごく久しぶりだねえ! いやー、どうしているんだい?」と驚きながらもさわやかな笑顔で返し、彼女との久しぶりの再会をとても喜んでいるように見えた。ふたりのうれしそうな再会の様子は、元同僚や近所の人との再会ではなく、親しかった友人との偶然の再会という感じで、周囲にいる私達も思わずほほ笑んでしまうような温かな雰囲気だった。この女性は男性の妻(もしくは彼女)とも知り合いのようで、「彼女は元気? あなた達ふたりはいつも忙しいから……」などと話していた。でも、閑静な住宅地にある地方銀行という場所柄、ロビーは驚くほど静かだったので、このふたりの会話はあえて耳を澄まさなくても、一字一句が銀行のロビーにいる全員にはっきりと聞き取れてしまう状況だった。
きっと再会がとてもうれしかったのだろう。このふたりは周囲の静まり返った状況にはお構いなしに、ロビーの隅々まで通る声で会話を続けたのである。
「ありがとう、彼女も元気だよ。きみも元気そうじゃないか。今もこの辺りに住んでいるのかい?」
「いいえ、実は私、先月ウエスト・シアトルに引っ越したのよ」
「へー、知らなかったよ。ウエスト・シアトルなんて良い場所じゃないか。大体どの辺りなの?」
「アラスカ交差点からカリフォルニア通りを右に曲がって××ブロック行って、左に曲がった×軒目にあるレンガ造りの家よ。偶然にも私が以前勤めていた××高校のすぐ近くなの」
大勢の人の前で、非常に具体的に自分の家の場所と職業を話すこの白人女性の様子に、他人事なのに私のほうが焦り始めてしまった。もしかしたら、この銀行のロビーの中には個人情報詐欺などを生業にしている人もいるかもしれないではないか。先日も、バスの中で携帯電話を掛けていた女性が電話の相手に向かって自分のソーシャル・セキュリティー番号を大声で伝えているのを目撃したが、それに匹敵するくらい危険度が高い行為に思えたのは私だけだろうか。
でも男性は、彼女がパブリックな場所で個人情報を公開していることなどお構いなしに会話を続け、「すごく良い立地じゃないか。スティーブと一緒に引っ越したんだろう? 彼も元気かい?」と、懐かしそうに尋ねた。その質問によって彼女のパートナーの名前が“スティーブ”で、男性はスティーブとも友人であることがわかった。銀行中の人達にもだんだんとふたりのシナリオが見えてきて、中には会話の流れにうなずく人までいた(笑)。しかし、男性からスティーブの様子を聞かれた女性は、ほとんど間髪を入れずに、「ノー。スティーブではなく、私は今、別の男性と住んでいるのよ」と明るく答えたのだ。それは銀行のロビーの隅々まで響き渡り、列に並んでいた人々の間に「Oops!!」(オットーッ!こりゃ、困った質問だ)と、一斉に息をのんだような緊張感が走った。
公衆の面前で、いきなり「実は全然違う男と住んでいる」と報告された男性の対応は、なかなか興味深かった。彼は明らかに動揺した様子だったが、完璧にそれを否定するかのように満面に笑みを浮かべて、「わぉ! そうかぁ。で、その人とは長く付き合っているの?」と、さらに突っ込んだ質問を投げた。まあ、彼の立場ではこう続けるしかなかったかもしれないが、どう見ても30歳代後半に見える大の大人ふたりが銀行のロビーで話す話題としては、あまりにもプライベートな内容ではないだろうか? “順番を待って並んでいる”という場所を移動したくても動けない状況下で黙って話を聞かされている人々は、きっと誰もが“ちょっと困った感じ”だったに違いない。私なんて「私のほうが恥ずかしいから、もう止めてー! それ以上はこういう場所で話しちゃだめよー!」と、その女性を止めてあげたいくらいだった。でも、そんなことをしたら“他人から注意される”という行為に慣れていないアメリカ人は、人から指摘された恥ずかしさに耐えられず、「公共の場で屈辱を受けた」などと言って私のことを訴えるかもしれないので、おとなしく黙っていることにした次第である。
しかし、このふたりは列が少しずつ動いても気にせず話を続けたので、ふたりの声は相変わらず大きなまま、話の内容は佳境に入っていった。新しい男性と付き合っている期間の長さを聞かれた女性は迷う様子も見せず、「ええ、結構長いわよ。今年の5月に出会ったから」と答えたのだ。それを聞いた私は、「ちょっと、あんた! 5月って言ったら、たった4ヵ月前じゃないの。それなのに、もう一緒に暮らしてんの?」と思ったが、ほかの誰も発言しなかったので、私も仕方なく下を向いて話の続きを聞くことにした。すると男性が「へえー、そうなんだ。どこで出会ったの?」と、またしても突っ込んだ質問をしたので、私も興味津々で顔を上げると、私の横の人も前の人もみんな一斉に顔を上げた。そして、その美しい彼女は、まるで「イチゴは赤い」とか「寿司には新鮮な魚」とか、当たり前のことを発言するように、背筋をピンと伸ばして堂々と、「彼とはマイ・スペースで出会ったのよ」と言ったのである。
これを聞いて銀行中の人が驚いた、と思う。でも、「えっー、嘘だろー? マイ・スペースで4ヵ月前に知り合った男とすでに一緒に暮らしてるわけー?」と、心配したのは私だけだったようで、会話の相手の男性は「へえー、そうなんだ。ユニークじゃないか。良かったね」と普通に相づちを打っていた。“マイ・スペース”とは日本でいうとミクシィのようなもので、友人やフリーランスのビジネスなどのコネクションを広げるための無料ウェブサイトだ。だからシングルの出会い系サイトではないのだが、そのサイトのカジュアル性を利用して知らない人に「友達になりたい」と一方的にメールを送ったり、男性からのメールが欲しくてセクシーな写真を掲載する女性やセックス・フレンド募集用に利用している人が多いという話は聞いたことがある。でも、銀行にいたこの女性のようにクラッシーな装いの美人高校教師から「マイ・スペースで出会った彼と3ヵ月後に同棲している」と聞かされ、少なくとも私は驚かされた。
この女性はこの後、「マイ・スペースで出会った彼がどれほど素敵なのか」という話を延々と続けたので、さすがに話を聞いていた男性もどうしていいのかわからない様子を見せ始めた。私も彼女の自慢が少々“too much”だったので、クオーターをゲットすると共に自分のアパートへ向かった。だから最終的にふたりの会話がどれほど温かい雰囲気で終わったのかはわからない。ただ、この日の午後、確実にわかったことは、「マイ・スペースで男を見つけた人が本当にいる」という事実と、「パブリックでは自分の名前、住所、男遍歴をなるべく話さないほうがいいだろう」ということである。みんなも気を付けようね。
※このコラムは2010年以前に執筆されています。

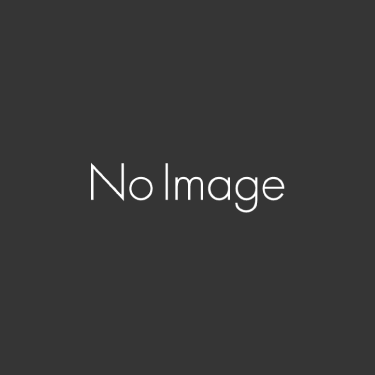


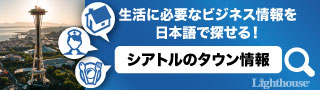


コメントを書く