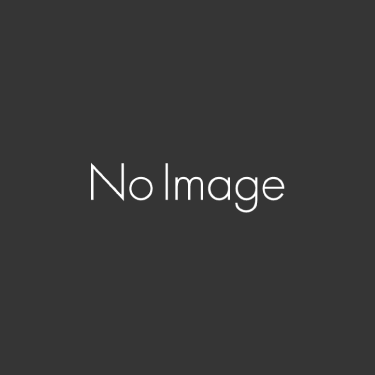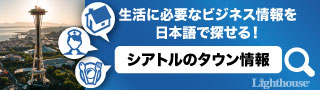アメリカ市場において大きな存在感を示している日本食のパートナーとして欠かせないのが日本酒。そして最近にわかに注目を浴びつつある日本の焼酎です。日本酒と焼酎のアメリカにおける歴史と挑戦を続けている企業の取り組みについてご紹介します。(ライトハウス 2024年11月号 特集「-日本食のこれまでとこれから- アメリカで挑戦する日本酒と焼酎」より)
アメリカの日本酒と焼酎について知る
アメリカにおける日本酒は、日本食の浸透と共に人気を拡大してきました。現在の市場における存在感や日本酒の注目度を高める取り組み、さらに日本酒を追いかける焼酎の認知度アップの仕掛けについて、ジェトロ(日本貿易振興機構)の担当者の方々に解説していただきました。
日本酒と焼酎のこれまで
まず、アメリカにおける日本酒の市場規模について聞きました。ジェトロの清水光南さんは「アメリカは日本産日本酒の輸出先としては数量が世界一の国であり、アメリカにおける日本酒の市場規模は約4億ドル(約600億円)です。ただし、2022年時点の、アメリカの酒類市場のうち、日本酒が占めるシェアはわずか0.2%に留まっており、成長の余地があると言えます。今後、2024年から2030年までは年平均成長率5.3%で成長していくことが予測されています」と、これまで市場が成長してきてはいるものの、今後もさらにシェアを伸ばす余地が残されていると回答しました。
次に、日本からの輸入金額と数量が増加してきた背景にある要因として次のようなことを挙げました。「日本酒が海外で広く受け入れられるように、商品を改良したことが一点。また、引き続く和食ブームや、訪日外国人が増加しているということも、日本酒人気の背景にあります」。
続いて、清水さんは、アメリカ国内の主な日本酒蔵として、大関、宝酒造、月桂冠、八重垣などが現地生産に取り組んでいるほか、2023年には獺祭がアメリカ産ブランドのDASSAI BLUEの販売をニューヨークで開始したことなど、日系企業の積極的な取り組みが行われていると説明しました。さらに、「輸入業者または製造業者、各州の卸売業者、そして小売業者はそれぞれ別法人でなければならないと定められているほか、原則、州を越えての商品の流通はできません。つまり、輸入業者または製造業者は、商品を販売したい州には、提携する卸売業者を持つ必要があります。」と、日本とは大きく異なるアメリカにおける独特な流通システムについての解説を加えました。
一方で焼酎について木村恒太さんは、「アメリカにおける日本食の消費増と共に、日本酒の消費も増加してきましたが、焼酎は横ばいです。日本酒には寿司というパートナーの存在がある一方、これまで焼酎のパートナーは何か?という問題がありました。現状で焼酎を主に飲んでいるのはアメリカの日本人が中心であり、日本酒と違って現地製造の話はあまり聞こえてきません。泡盛も含めて、今後、焼酎に関しては底上げをする必要があると強く感じています」と、焼酎のアメリカ市場での認知度アップのためにサポートしていく必要性を強調しました。
#Support Sake でファン獲得へ
次に、日本酒の北米のファンを増やす取り組み「#Support Sake 」について柴原友範さんに解説していただきました。「アメリカで日本のファンコミュニティーを作ろうと昨年スタートさせたのが『#Support Sake 』です。何を軸としたコミュニティーにするのか?その軸が日本酒というわけです。Instagramで展開中ですが、きれいな『ばえる』写真に共感してもらうというよりも、我々は『パーパスドリブン(Purpose Driven)』、つまり社会的意義に共感してもらうようなコミュニティーを、若者を中心に作り上げたいと思っています」。
それでは、「#Support Sake 」が持つ社会的意義とはどのようなものでしょうか。「日本酒は、アメリカでは市場を伸ばしていますが、本国、日本での市場は縮小の一途です。人口減少がその主な要因であり、若い人の酒離れもあり、酒蔵は近年厳しい状態が続いています。例えば、1985年には全国に2456軒あった酒蔵が、2021年には2264軒にまで激減してしまいました。しかも、現在、新しく酒蔵を作ろうとしても輸出目的でないと免許が発行されません。つまり、日本の一般的な酒蔵には免許が出ないという状況です。そうなると、長年続いた酒蔵であっても、今の世代で廃業に追い込まれてしまうところが多いために、酒蔵の数は減少の一途です。それを食い止めるために、アメリカを含む海外から日本酒の人気を盛り立てて、飲まれる機会を増やして、日本の酒蔵を応援して次の世代に(酒造りを)継承していかなければならないというのが、私たちが実感している社会的意義です」。
昨年スタートした「#Support Sake」は、前述の社会的意義に共感する、レストラン、酒蔵、卸業者、業界団体を中心に、一般のアメリカ人の日本酒のファンを増やしていくことを狙っており、そのためにさまざまな仕掛けを展開中です。「フォトキャンペーンやオフラインイベントを実施しており、昨年はUCLAの大学院生を対象に、日本酒のレクチャーを開催しました。『Sake Voyage』というインスタライブでは、日本の蔵元とアメリカの日本酒ファンとをつなぎ、日本酒をファンに試飲していただくというライブ中継を配信しています。さらに、レストランとのコラボ企画、『Support Sake Restauran Week』では、日本酒を扱っているレストランでペアリングのメニューを開発していただき、そのメニューを2週間提供していただくと同時に、インスタで写真を共有してもらいます。レストランに誘客すると共に、そこで日本酒と料理を味わってもらい、(日本酒の)ファンを増やすことを狙いとしています」。
また、2023年に実施したフォトキャンペーンを2024年も実施。11月15日が締め切りで、お題は「Sake Moment」。お酒を楽しんでいる写真を「@Support Sake」をタグ付けして投稿するというものです。
「さらに昨年のフォトキャンペーンの優勝者が賞品の日本行き航空券を使って日本を訪れる際に、酒蔵ツアーにも参加してもらう予定です。その模様を北米に発信することも計画中で、このように日本酒人気を盛り上げていこうと取り組んでいます」。
焼酎をスパークさせる取り組み
最後に「底上げが必要」な焼酎の認知度アップに関する戦略を、JFOODO(日本食品海外プロモーションセンター)の澤邊大輝さんが紹介してくれました。
「JFOODOでは、2021年から焼酎の消費者向けプロモーションをロサンゼルスで手掛けています。ターゲットはカクテルバーのミレニアル世代の消費者に定めています。私たちが開設した『SHOCHU Japanese Spirits』のサイトは、落ち着いたカクテルバーのイメージを前面に押し出しています。日本で焼酎を飲む時の雰囲気とはガラリと違うイメージです。このサイトでご紹介しているのは、2023年度にJFOODOで認定した9軒のアンバサダーバーです。そのバーのミクソロジストに、1軒のバーにつき2種類の焼酎を使ったハイボールとオリジナルカクテルを考案してもらいました。2024年1月~2月は『Shochu Month』と銘打って、それらのカクテルが販売されました。ただし、『Shochu Month』が終了した後もアンバサダーとして活動を継続していただき、その焼酎カクテルも販売してもらうことが私たちの狙いです。これらは、ミレニアル世代に人気があるバーで、カクテル業界の人ならば誰もが聞いたことがあるという影響力が強い店です」。
また、澤邊さんは2023年のカリフォルニア州の焼酎に関する法改正も大きな後押しになっていると付け加えました。「昨年の10月に、カリフォルニア州知事が『アルコール規制に関する法律』の改正案に署名したことで、ワインの販売ライセンスを持つバーやレストランで、アルコール度数24度以下の焼酎の販売が解禁となりました。韓国の蒸留酒のソジュは以前からアルコール度数24度以下のものに限り、ワインの販売ライセンスを持つ店で売ることができたので、日本の焼酎を販売する企業はこれまで、24度以下に調整した上で商品ラベルに『Soju』と記載、または併記するなどの工夫をしてきました。しかし、昨年の法改正で、日本の焼酎は堂々と『Shochu』として販売できることになったのです」。
これまでアメリカ市場で伸びてはきたものの、今後のさらなる快進撃に期待がかかる日本酒と、法改正を追い風に認知度向上を目指していく焼酎。共に今後の動きに要注目です。

JFOODOの焼酎公式ウェブサイト
取材協力(登場順)

JETRO(日本貿易振興機構)
米国輸出支援プラットフォームアシスタント
清水光南さん

JETRO(日本貿易振興機構)
米国輸出支援プラットフォーム事務局長
木村恒太さん
https://www.jetro.go.jp/en/

JETRO(日本貿易振興機構)
ロサンゼルス事務所次長
柴原友範さん
https://www.instagram.com/supportsake/

JETRO(日本貿易振興機構)
JFOODOディレクター
澤邊大輝さん
https://japan-food.jetro.go.jp/shochu
『シアトルの地酒』を目指す Shirafuji Sake Brewery(ワシントン州)
 伝統的な酒造りを家族中心に実践。 ▲ Shirafuji Sake Brewery |
震災後に福島からアメリカに移転『シアトルの地酒』を目指す
未曾有の大災害となった2011年の東日本大震災で、避難指示区域内にあった冨沢酒造店。同社は数百年続いたのれんを下ろすわけにはいかないと、新天地シアトルで「白冨士」の酒造りを再開し、130以上のワイナ リーが軒を連ねる中、日本酒の蔵として奮闘しています。シアトルに拠点を移した同社の冨沢 守さんと真理さんに移転の経緯と今後を伺いました。

(左)Shirafuji Sake Brewery President 冨沢 守さん、(右)Vice President 冨沢真理さん
ー アメリカ進出の経緯を教えてください。
弊社は江戸時代初期の1650年に酒造りを開始し、相馬藩醸造元として福島県相双地区で事業を続けていました。守が二十一代当主となります。しかし、2011年3月11日、大震災が発生し、原発から3キロメートル圏内にあった弊社は避難指示区域となり、酒造りを続けられなくなりました。
そこで、「白冨士」という暖簾を持ってどこか別の土地で酒造りを続けたいと日本国内を探して回ったのですが、なかなか話がまとまらず、結果的に国外に目を向けることにしました。
アメリカのシアトル、サンフランシスコ、シカゴと見て回りました。そして、このシアトル郊外でどこか東北に似た景色と雰囲気を感じ取り、ここで酒造りができたらいいなと思いました。
2012年に移転を決断し、2014年には酒造りに携わる家族がシアトルに移住しました。その後、家族の事情で数年間、物件探しは休止に追い込まれました。いざ、本格的に物件探しを始めてみると、私たちが思っていたほどには「日本酒造り」への理解を得るのが難しいことに気付きました。
ですから、2022年10月9日のテイスティングルームのオープンの日は、皆さんに受け入れられるかどうか不安でした。しかし、実際、オープンしてみると、日本酒という文化に皆さんが興味を持っていただけていることが分かりました。以降、私たちは対面式でしっかりと日本酒について説明を続けてきました。

シアトルに移転する前の福島県相双地区の「白冨士」の酒蔵。
ー 福島の白冨士と、シアトルのSHIRAFUJIとの違いとは何ですか。
全部同じです。麹菌も同じですし、麹室では(福島時代と)同じ方法で酒造りをしています。むしろ、シアトルに来たことで電気を使わないなど、伝統的な手法に立ち返ることができました。ただ、酒造りは毎日の作業から成り立っているため、2011年に休止してから10年のブランクがあり、工程や感覚を思い出しながら取り組んだようなところがあります。
また、日本では酒造に関わっている人にとっては当然の知識が、ここアメリカでは当然ではありません。蔵造りに関わる大工さんにもアルコール関係の役所の担当者にも、日本酒文化を説明するのが大変でした。一方で私たちの文化を押し付けるだけでなく、アメリカの文化も尊重することも心掛けています。つまり、相互理解の大切さをシアトルでの酒造りを通じてあらためて認識した次第です。
ー SHIRAFUJIはどこで購入できますか。
直営のテイスティングルームでの店売りとオンラインショップです。スタートして2年ですが、売上は堅調に成長しています。ただ、福島で最後に売っていた量のまだ100分の1に留まっています。それでも造ったらすぐに売り切れることが多くなったので、今後は生産量を増やすことを考えています。また、今、8種類の商品を出しているのですが、興味深いのは高級酒から売り切れるということです。純米吟醸酒を買っていかれる方が多いですね。
私たちが位置しているのは、ワイナリーが多いエリアです。色もワインのようですし、シャンパンのように気軽に楽しんでいただけるようです。
私たちはSHIRAFUJIを「シアトルの地酒」にすることを目指しています。さらに地元の料理と合う日本酒として、ローカルの人はもちろん旅行者の方々にも認知してほしいです。例えば、SHIRAFUJIはピザ、チーズ、シーフードにも合うんですよ。
それから、弊社では酒クラブを開設しています。メンバーのお客さんとは、餅つきなどのイベントを通して親睦を図っています。メンバーの皆さんは自分たちのことを「ジョーレン」と呼ぶんですよ。そう、「常連」のことです(笑)。これからもジョーレンさんを増やしていって、ここを拠点に日本酒を通して日本文化を発信していければと思っています。
ー 5年後に目指すのは、やはり「シアトルの地酒になっている」ことですか。
「シアトルの日本酒、SHIRAFUJI」という地位を確立させたいです。そのためにどうするか? 私たちは400年近く伝統的な手法にのっとって酒造りを続けてきました。ここシアトルに根を張って、今後100年、200年と続けていく覚悟ですので、まずは真面目な酒造り、ぶれない酒造りが何よりも大事だと考えています。
同特集「-日本食のこれまでとこれから- アメリカで挑戦する日本酒と焼酎」に掲載している下記の企業などについてはライトハウスの電子版をご覧ください。
◎Dassai USA Inc.:NYから全米へ、そして全世界へ 積極的に攻めていく進化型の日本酒
◎iichiko USA Inc.:アメリカ500店舗のバーで取扱中 焼酎iichikoを世界のスピリッツに
◎ この他の特集記事はこちら »
◎ シアトルの最新生活&観光情報こちら »