
2013年01月号掲載 | 文・写真/小杉礼一郎
「撮った」のでなく「撮れた」のだと思う写真がある自然の巡り合わせはまさに運。あるがままの運の姿をよく知るところから写真術が始まる

▲オレゴン・デューンを素足で歩く(歩かせる?)エコキャラバンの旅。皆が「気持ち良い! 何年ぶりだろう?」と言う。自然探訪のだいご味だ。秋の枯葉ウォークも足を喜ばせる快感がある
美しいと思う心
10年ほど前の秋、隊長はたちの悪い風邪で2、3日家でダウンしていたことがある。
熱が引いた午後、家の前のトレイルに出た。秋晴れ、空が高い。体が妙に軽くなって、まるで生まれ変わった気分だった。家のすぐ近くに深緑のモミ、深紅のメープル、黄金色のポプラが秋の陽を透かして並んで立っている。見慣れた木々も空の青さも深い輝きで、病み上がりの目から心の底まで染み通ってくる。「ああ、なんて美しい!」その、3本3色の樹の前にずっと佇み、しばらく動けなかった。
その後フワフワした足取りで家へ戻り、カメラを持ってきてその3本の樹を撮った。コンピューターのデスクトップ画像にしていたが、その後、何回かコンピューターを新しくするうちに、失くしてしまったのだろうか。今回その画像を使おうと思ったのだが、いくら探しても見つからない。ほかの人が見れば、青空を背に緑黄赤の3色の樹が並んでいるだけの写真だから、提出したとしてもおそらく編集の段階でボツになったとは思うが。
その3本の樹は毎秋同じように紅葉するので、隊長は毎秋それを眺める。が、美しさに見とれ動けなくなった、あの感動はよみがえらない。あの日あの時、最初にカメラを持たずにあの場面に行き合わせたことはありがたかった。外の自然と内の自然(体と心)の有り様が一致したその時に、美しいと思う心が動き出す。感動とは(何かに)感じて(心が)動く。「ありがたい」とは、そうあることが難しいということが改めてわかったからだ。そういう瞬間は誰もが経験していると思う。
自然探訪の場合は特に、現場での感動を写真が上回ることはまずない。なので「美しい」と心が動き出したらそれを存分に堪能させてやりたいと思う。カメラを手にするのはその後だ。デジタル・カメラの進化は、まさしく日進月歩である。手ブレ防止、多様なモード設定、笑顔検出システム。シャッター・チャンスですら、オート連写である程度カバーできるようになってきた。しかし、対象にカメラを向けシャッターを押すのは、最後まで人間側の作業。「美しいと思う心」が働き出すのを待って、それを任せよう。

▲自然探訪の先々には、晴れも曇りも雨の日もある。ひとりでこういう道を700キロも行くと、雲に心が押しつぶされそうになってくる。アラスカ北部ダルトンハイウェイでの心象・風景

▲ブライス・キャニオンで会った盲目の少女
盲目の少女が教えてくれたこと
2002年の夏の夕刻、隊長はユタ州のブライス・キャニオン国立公園の展望台で、眼下に広がる谷の景色に心を奪われていた。きめ細やかな美しい自然の造形である。谷のパインの林から、とても気持ちの良い風が吹き抜けてくる。その時、後ろから白い杖でコツコツとトレイルを叩きながらひとりの少女が登ってきた。家族がその後を続いている。彼女は展望台の手すりまで来ると、顔を上げ鼻を風に向けた。そして胸いっぱいに息を吸いこんで、心底うれしそうな顔をした。一瞬の、それだけのことだったが、さわやかな風はパインのほのかな香りを運んでいたことに、後で気付いた。なまじ目が見えるばかりに、見えていないことのほうが多かったのか……。目からウロコとはこのことだった。エコ・キャラバンで五感の旅を試みるようになったのは、それがきっかけである。写真は五感のひとつだけをかろうじて保存する5分の1の手段に過ぎないと、その時に悟った。
あなたは、ツンドラを知っているだろうか? 中学校で「永久凍土」と教えられた人は多く、その上を「素足で歩こう」と言っても、大方の人は「え?冷たくない?」と心配する。凍土の上には厚い苔のスポンジ層があり、更にその上にヤブツツジやコケモモ、ベリー類の細かく低い、潅木のメッシュの層が覆っている。だから素足でツンドラを歩くことは、素足で毛足の長い固めの分厚いじゅうたんを踏むような感じだ。実際、隊長と共に素足のツンドラ・ウォークをすると、「あ、フカフカで気持ち良い……」と皆の目が輝く。ほとんどの人はアラスカ観光に来ても、目の前のツンドラに触れることさえせず帰っていく。見るだけの旅なのだ。
「知っていること」と「見ること」と「本当に知ること」はまるで違う。目で見るだけでなく、手を触れ足裏で知り、驚き、目が輝き出す旅をしたい。旅は誰の人生にとってもその時その場、1回きりのアートなのだ。観客(見るだけ)に終始する20世紀型の旅から、自分も舞台に立って体を動かし、浸り、五感で楽しむ21世紀型の旅を隊長は提案したい。その旅の中では、写真に撮れない“もの”や“こと”の方がはるかに多い。

▲クレーター・レイクの湖面に映る雲。湖水の青さを伝える“宇宙の蒼”はこれだ、と思って撮った1枚

▲クレーター・レイクに、バック・フリップで飛び込む男性。国立公園が身近なものに感じられる
デジタル・カメラの功罪と落とし穴
年に1度、秋か冬の夜長に今年撮った写真を整理し、加工しながら自分のこの1年をじっくり見返し考える時間を持ってみよう。いろいろなものが見えてくる。
ひとつは、自分の「写真欲」。例えばハード面では、より良いカメラ、アクセサリーが欲しくなる。ソフト面では旅と撮影とのバランス。旅にカメラはじゃまだし、撮影に凝りだすと次の目的地までなかなかたどり着けない。撮影後のことも大きく、撮りためた膨大な画像の見返しと加工に少なからぬ時間を費やす。デジタルになったおかげでフィルムや現像にお金は掛からない。では時間は?手間は?その画像をどう使う?
世界は広く、自然は大きく、そしていつも変化している。写真の世界は奥が深い。だのに人の一生は短い。何を引き換えにしているか、よく考える必要がある。その年撮った写真を整理する時間は、その自分なりの折り合いを考えるのに良い機会だ。

▲雨の日には雨の景色がある。何げないシアトルの朝
隊長の場合
安いカメラ、無手勝流の隊長の写真は、引きで1枚。対象物に定規を置き、寄って1枚。そんな判で押した写真ばかりで、もうカメラに触るのも嫌になった時期があった。そして「何のために写真を撮るのか」を自問し、自分の撮っているのは「紹介写真」だということに思い至る。じゃあ「わかりやすい写真にするにはどうするか」そう割り切れてから気が楽になった。エッセンスは構図とシャッター・チャンスにあることも悟った。「撮る」ことは旅の準備段階から始まることも。その後、場数だけは踏めたし、そのつど写真の限界も知った気が
する。
隊長は時々、自分のための1枚を撮ることがある。それを「記憶の背表紙」とでも呼ぼうか? その場所の寒さ、暖かさ、さわやかさ、風や潮の香り、木々のさざめきや鳥の声、波やせせらぎの音、野生のベリーの酸っぱさ、木漏れ日のうごめきなどなど。その時、五感で美しいと思った心、それをすっと引き出してくれる1葉の写真が「記憶の背表紙」である。

▲オリンピック国立公園ラプッシュの海岸で入り日に見入るTさん。つい1年前までTさんは下肢が固まっていく病気に苛まれ、「好きな旅に出ることはもうできない」と思っていた。奇跡的に快復し、旅三昧となった今はカメラは持たない

▲ペインテッド・ヒルズに咲いたバルサム・ルーツの花。なんとぜいたくな光景だろう

▲オリンピック国立公園のハリケーン・ピークにて。誰が言い出すともなく寝っ転がって紺碧の空を見る。背中に染み入る地球の温かみは、カメラでは撮れない

▲アラスカのフェアバンクス郊外にて。雪の中で仰向けになって、頭上の天空全部で激しく乱舞する極光のページェントを眺めていると、時の経つのを本当に忘れる。オーロラを撮ることは難しくはないが、宇宙の1度きりの饗宴のほんの一部を写すことにどれほどの意味があるのかな?と思ってしまう
(2013年1月)
| Reiichiro Kosugi 1954年、富山県生まれ。学生時代から世界中の山に登り、1977年には日本山岳協会K2登山隊に参加。商社勤務を経て1988年よりオレゴン州在住。アメリカ北西部の自然を紹介する「エコ・キャラバン」を主宰。北米の国立公園や自然公園を中心とするエコ・ツアーや、トレイル・ウォーク、キャンプを基本とするネイチャー・ツアーを提唱している。 |




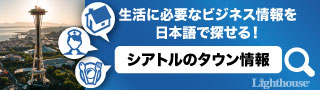


コメントを書く