
2007年01月号掲載| 文・写真/小杉礼一郎
古来、人間の敵とされてきたオオカミ
近年、このクールな野生生物を巡る論争が熱い。
オオカミと目が合う
その大きな母オオカミは、何を思ったか足を止め、隊長を見上げた。もろに目が合った。距離は2メートル、一瞬だったがそれで十分だった。灰色の目、小さな瞳孔。その姿かたちはハスキー犬に似ているが、野性のにおいを全身から放っている。今、同じ自然空間のこんなにも近くで視線を絡ませていながら、私達とこのオオカミ達の棲む世界は全く異なる。人間は偶然に、一瞬そこを垣間見ることはあっても、決して入っていけない世界。人間と自然の間に横たわる、底のない谷。それを初めて覗き込んで目が眩んだような感覚が、腹の底から頭のてっぺんまで染み渡っていった。
アラスカ州のデナリ国立公園。一般車は入れぬ園内で、ツンドラに棲む野生生物を見て回るバス(=TWTバス)の車窓からのオオカミとの出合いだった。※1インタープリター(自然解説員)がバスを運転しながら、野生の動物や鳥などを見つけては車を止め、双眼鏡を使うなどして観察する。インタープリターの解説があり、質問も出る。バスの乗客全員で四方を見ながら行くのだが、動物を見つけるのは大体、まずインタープリターである。動物のお出ましは天気にも左右されるし、動物次第だ。※2
TWTバスのツアーには、野球のグランドスラムにちなんだ「グランドスラム・デー」という言葉がある。園内の4大動物(ムース、カリブー、ドール・シープ、グリズリー・ベア)がすべて見られた大当たりの日を指すのだそうだ。が、オオカミは入っていない。めったに見られないのである。この日は偶然、子連れのオオカミが私達の車のすぐ横を通ったのだった。それも、隊長の目の前を。「本当にラッキーだよ。オオカミの首に付けた発信機で生息エリアを把握していながら、実物には3年間も遇っていない野生動物の研究者もいるんだ」と、インタープリター氏。

▲ハイイロオオカミ。何時間でも走り続けられるオオカミの行動半径は、驚くほど広い
Courtesy of Northwest Trek Wildlife Park
北西部のオオカミ
1800年代より、米北西部ではオオカミを銃殺、薬殺してきた。当初は毛皮を獲る目的で、続いて家畜を襲う有害獣として。1900年代初頭に北西部のオオカミは絶滅する。時代を下って現在、米北西部にオオカミはいるのだろうか? 答えはイエス。
モンタナ、アイダホ、ワイオミング各州に広がるロッキー山脈には、140の群れ、約1,000頭のオオカミが生息している。※3ワシントン州では州北東部、カナダ国境沿いの森林と、カスケード山脈の北部、ノース・カスケード国立公園、オカノガン国有林などでオオカミが観察されている。少数のオオカミが生息していると推定されている。
オレゴン州では、ヘルズ・キャニオンを越えてアイダホ州から移動して来たオオカミの群れが確認されており、今後、オレゴン州北東部にオオカミが定住するだろうと予想されている。現在の米北西部のオオカミはいずれもカナダから、そして隣接する他州を経て入って来たものだ。

▲イヌは元々、オオカミを人間が長い間に分化させてきた動物だ。
遺伝的にはシベリアンハスキーがもっともオオカミに近いとされる
虚像と実像
アジアや北米の先住民にとって、オオカミは人間に害を与える動物ではなかった。それどころか、森の生態系の頂点に立つ強者として、特に畏敬の念が持たれていたのである。中国語の「狼=ケモノへんに良い=良い獣」、日本語の「おおかみ=大神」を見れば、そのことがわかるだろう。
しかし、「赤ずきん」の物語に象徴されるように、ヨーロッパではオオカミは「悪賢い、凶暴、危険」「人間の敵」というイメージができ上がっていた。それは、ひとえに「オオカミが家畜を襲う」ことが最大の理由である。でも、隊長はこう思うのだ。「人間が鉄砲を手にする前は、ヨーロッパでもオオカミと人間は敵対していなかったのではないか?」
脱線するが、「人間はモノを持つと考えが変わる」と思う。素手の人間とこん棒、刀、槍、弓矢、銃を手にした人間。兵器、軍事力、核兵器を持った人間は、その得物に応じて考え方を変えてきてはいまいか。卑近な例では、街中やスーパーの駐車場で車を運転している時と降りた時とで、私達は「運転者」から「歩行者」へ意識の違いを感じる。車を得ただけでも、あるいは乗る車の大きさやランクにによってすら(悲しいかな愚かにも)人の考えは変わるのである。銃を手にした人間がオオカミに対する考えを変えたとしても、不思議ではない。あくまで隊長の仮説である。
さて、野生生物学者によるとオオカミは通常2頭から10数頭からなるパック(Pack)と呼ばれる家族集団(=群れ)を作る。パックはα(アルファ)と呼ばれるつがいのひと組によって統率される。個々のパックは、それぞれのにおいによるマーキングと遠吠えなどで、ほかのパックとの縄張りを分け合う。オオカミの狩りはパックによるチーム・プレーである。パックは獲物の群れを分散させ、疲れさせ、逃げ足の遅い落伍者を全員で仕留めるという、なかなかの頭脳プレーを試みるらしい。しかし、観察によると、獲物を見つけても捕食率は10%くらいだそうだ。大半は縄張り外へ逃げられ、カリブーやジャコウウシにはスクラムを組んでキックの円陣を組まれ、ムースにも得意の前足蹴りで撃退されることが多い。餌にありつくのは大変なことなのだ。運良く大動物を1頭仕留めると、遠吠えで群れの全員を呼び、タラフク食べる。巣に帰って吐き戻して、子に与えたりもする。残りの肉は埋めておいてマーキングをし、また食べに戻る。パックの中には序列があり、αは狩りの獲物を真っ先に食べる。パックの長として群れを守るため、強く健康でなくてはいけないからである。ほかのメンバーは、αが食べるのを待っている。次に、β(ベータ)のツガイが食べ、残りをΩ(オメガ)、そのほかのメンバーが食べる。観察によると、オオカミは賢く忠誠心があり、序列に忠実で、社交的でもあるという。※4ひとつのつがいからは1年に平均6匹の子が生まれるが、大半は最初の年に死んでしまう。生後10カ月くらいから子も見習いとして狩りに付いていく。こうして2、3年、若いオオカミはパックと行動を共にする。やがて成犬になったオスとメスは、パックを引き継いだり、別のパックを作ったりしていく。パックから離れ、単独で行動するオオカミ(Lone Wolf)も出てくる。
天敵、絶滅、復活、論争
「天敵」とは、なんと的を得た言い方だろう。それぞれの種を健全で適正に保つため、天が配った役回りである。かつて、オオカミは北アメリカ大陸のどこにでもいた。ムースなどの天敵であるオオカミは、それらの大型動物を種としての生息数を減らすまでには捕食しない。そして、オオカミがいることで、大型動物は餌場を絶えず移動する。草食獣の餌場が一定しないおかげで、植物相は自ずと復元する。こうして森林と草原の植物相と、そこに棲むムースなどの大型草食動物とオオカミとは、ずっと均衡を保ってきた。さらに、先住民はそのいずれにもインパクトを与えずに、何千年も共存してきたのである。ヨーロッパから白人が入って来るまでは。
アメリカに入植して来た人々は「オオカミは家畜を襲う」という当然の理由でオオカミを駆逐した。その一方で、オオカミの餌であった大型動物(バッファロー、ムース、エルク、ジャコウウシなど)も絶滅寸前にまで減らしたのである。※5
1930年代には、アメリカ本土のオオカミは、銃と毒と罠で完全に駆逐された。つまり絶滅した。他方の、いったん絶滅あるいは絶滅に瀕した大型動物は保護し、移動・復活させてきた結果……今度は、それら草食動物による植生破壊の問題が1970年代から表面化してくる。この失われた自然界の均衡を取り戻すために、西部でオオカミの移動・復活が図られるのは1990年代である。しかしながら、それに対して牧畜業者を中心に猛烈な反対の声が上がった。実際に、オオカミによる家畜の被害が起きている。ただし、昔と今で変わった状況がある。大きくは、オオカミに対する人々の理解の変化。そして(これが大きいのだが)オオカミの復活による経済的得失の変化である。現在、ミネソタ、ワイオミング各州でオオカミ・ウォッチャー達がもたらす経済効果は、年間数百万ドルと推定されている。一方、オオカミによる家畜の被害額はおそらく年間十万ドル単位であろう。
それでも、自然保護のさまざまな局面と同じく、心情的なものを含めて、今後北西部ではそれぞれの州で、親オオカミ対反オオカミの論争が法廷と政治の場面で続けられるだろう。
オオカミと人は共存できるか
20世紀に人間が考えていたほど、自然は単純に成り立ってはいなかった。新しい発見がひとつあれば、その先にさらに十の未知の扉が待っていた。現代はむしろ、自然のメカニズムの不可知さを前に、ようやく人間が謙虚になり始めた時期だと言える。オオカミには、群れ同士の縄張り争いと、群れの中でのオス同士の戦いがある。パピーの生存率も低い。ほかの高等生物と同じように、オオカミはねずみ算的には増えないし、際限なくほかの動物を殺すこともしないのである。際限がないのは、「おいしいプライム・リブやサーロインを安く、たくさん食べたい」という人間の欲や、「採算、利潤、競争」などの経済システムのほうではなかろうか。
牧場がほとんどないアラスカ州では、オオカミは人間に被害を及ぼしてはいない。だが毎年、何百頭ものオオカミが、ヘリコプターやセスナの機上から、そして地上でも、銃で撃ち殺されている。この「オオカミ駆除」の理由は、オオカミがムースを襲うからである。ムースを保護しているのではない。ハンティング用のムースを増やすためである。つまりハンターは、オオカミとムースで2回楽しめるわけだ。欲望の際限のなさにおいても、悪賢さにおいても、オオカミは人間にかなわないようだ。生殺与奪の手段(銃でも罠でも)は、すべて人間が持っている。オオカミと人が共存できるかは、我々次第だ。温暖化や環境ホルモンの問題に比べると、オオカミとの共存はなんとも易しい問題のように隊長には見える。
動物写真家の星野道夫は、アラスカ州での撮影旅行中、何回かオオカミと出合っている。そのシーンを回想したエッセイ『長い旅の途上』の最後にこう述べている。
「われわれの生活のなかで大切な環境のひとつは、人間をとりまく生物の多様性であると僕はつねづね思っている。彼ら(オオカミ)の存在は、われわれ自身をほっとさせ、そして何より僕たちが何なのかを教えてくれるような気がする。一生のうちで、オオカミに出会える人はほんのひとにぎりにすぎないかもしれない。だが、出会える、出会えないは別にして、同じ地球上のどこかにオオカミの棲んでいる世界があるということ、また、それを意識できるということは、とても貴重なことのように思える。」(原文のまま)

▲デナリ国立公園内を進むツンドラ・ウィルダネス・ツアー(TWT)のバス。動物が現れると双眼鏡で観察する
※1 ツンドラ・ウィルダネス・ツアー(Tundra Wilderness Tour=TWT)と呼ばれる。
※2デナリはアフリカのサファリ・パークより、ずっと高緯度にあり、太陽高度が低い。植物の生育量は南の5分の1しかなく、それで養えるだけの生物しか生息していない。
※3 ハイイロオオカミ、シンリン(森林)オオカミとも称されている。
※4 人類の祖先が野生のオオカミから徐々に野性を取り除いてイヌを分化させたのはその特性のためだ。猟犬、番犬、ネコとイヌの違いなどを思い浮べるとそれはうなずけるだろう。また、家庭のイヌが家長は誰かをよくわきまえるのは、オオカミのこの序列に忠実な性向を引き継いでいるからである。
※5 ヨーロッパから北米に人々が入って来る前、バッファロー(別名バイソン)は6,000万頭もいた。初めは移住民の食用に、そしてただ殺すだけのゲーム・ハンティングの対象として、絶滅寸前まで射殺されていった。
■ウルフ・ヘイブン・インターナショナル
オオカミの正当な復権(地域的に、世界的に)を目指して活動するNPO。オオカミに関する啓蒙活動と、情報発信を行っている。オリンピアの南で、オオカミの保護を目的とした飼育場を運営。ガイド付きで見学可能。
Wolf Haven International
ウェブサイト:www.wolfhaven.org/adopt.html
■ノースウエスト・トレック・ワイルドライフ・パーク
湖、道、草地、森林からなる715エーカーの公園には、ノースウエストを始めとする北米の30種以上の動物が自然に近い環境で飼育されている。
Northwest Trek Wildlife Park
ウェブサイト:www.nwtrek.org
■国立公園
イエローストーンとデナリでは、実際にオオカミを見る機会がある(必ず見られるわけではない)。ノース・カスケードにもオオカミは生息しているが、目にすることは難しい。下記ウェブサイトで現地情報に接することができる。
Yellowstone National Park
ウェブサイト:www.nps.gov/yell/naturescience/wildlife.htm
Denali National Park
ウェブサイト:www.nps.gov/dena/naturescience/animals.htm
North Cascades National Park
ウェブサイト:www.nps.gov/archive/noca/wolf.htm
| Reiichiro Kosugi 1954年、富山県生まれ。学生時代から世界中の山に登り、1977年には日本山岳協会K2登山隊に参加。商社勤務を経て1988年よりオレゴン州在住。アメリカ北西部の自然を紹介する「エコ・キャラバン」を主宰。北米の国立公園や自然公園を中心とするエコ・ツアーや、トレイル・ウォーク、キャンプを基本とするネイチャー・ツアーを提唱している。ウェブサイトをリメイク中。近日公開予定。 |




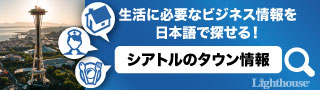


コメントを書く