静岡県は焼津市という小さな漁師町で細々と寿司屋を営む両親の元で育った僕は、やはり寿司とは切っても切れない縁で結ばれていると思う。地方の田舎でよく見られる光景だが、うちの田舎も例外ではなく、外国人が道を歩いていると指をさして「外人、外人」と大騒ぎをするようなド田舎であった。そんな環境で育った僕が、まさかアメリカで店を持つようになるとは……。そんな人生を、今一度振り返ってみたいと思う。 3人姉弟の長男として生まれた僕は、小さいころから店を継ぐ跡取りとして育てられてきた。店を継いでさえくれたら良いと思っていたのかどうかはわからないが、「勉強しろ」などと両親から言われたことは全くなく、またそれを良いことにダラダラとした学生時代を過ごしていた。一度、高校生の時に「やっぱり、大学なんていうのも良いのでは?」と思い、その旨を伝えると、「そんな風に勉強好きに育てた覚えはない」と即却下され、確かにそうだよなとえらく納得したことを覚えている。 弱小家族経営の寿司屋にありがちなことだが、僕ら姉弟はいつも店のためにコキ使われていた。近所の出前持ちは当たり前で、箸袋に割り箸を入れる仕事は子供の担当部署だったし、寿司酢を作る砂糖がまだまだ高価だった当時は、スーパーに家族全員で行き、「1人1袋まで」という砂糖だけを買うために何度も長い列に並ぶこともあった(その後、「1家族1袋まで」という風に変わったが、うちの家族が原因なのかどうかは定かでない)。 幼いころは店と自宅が一緒だったのだが、道路事情などもあり、駅前(と言っても、やっぱり田舎)にテナントを借りて、新たに寿司屋をやり始めたころには高校生になっていたので、それまで以上に働かされた。平日は学校があり、平和だったが、週末は夜中の2時過ぎまで手伝わされるのはザラ。「早く運転免許を取れ」と妙に親らしいことを言うなと思ったら早速、出前の担当範囲が広がった。 しかし、その当時は、自分が異国の地で寿司屋を出すとは、微塵にも思わなかった。
(次号につづく) | 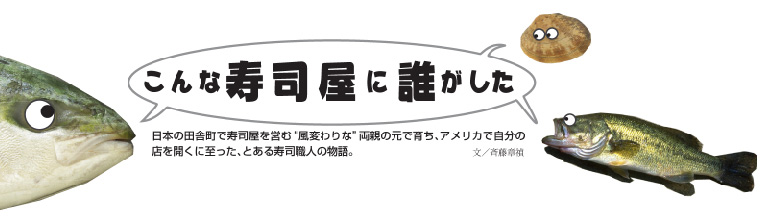
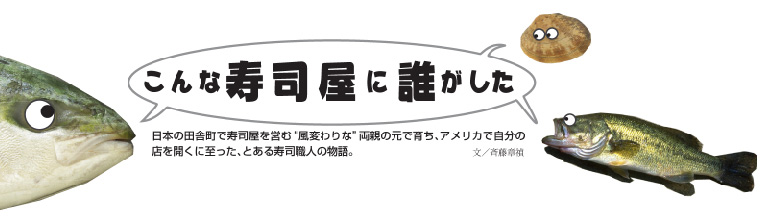
コメントを書く